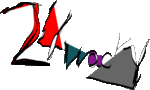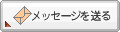2016年08月19日
『物語消滅論 キャラクター化する「私」、イデオロギー化する「物語」』その1

本書は次の2点について書かれている。一つは、小説やコミック、映画やゲームといった物語を創作・消費していく過程で、作者や読者のあり方が1990年代以降変わり揺らいでいること。二つめは、冷戦構造の崩壊によって「物語」が「イデオロギー」にとって代わり、社会や現実を設計する枠組みとして援用されていく事態が生まれているということ。いずれも私にとって切実な関心事である。
第一章 創作する読者と物語るコンピュータ
「第一章 創作する読者と物語るコンピュータ」は一つめの問題が論じられる。80年代末、電通によるストーリー・マーケティング(商品に対して使用価値ではなく「物語」という記号的価値を付加させる手法)の展開、おたくの特異な文化現象としてのコミケや二次創作、テーブルトークRPGといった現象がバラバラに発生していた。これらはみな、与えられた情報を一定の枠組みの中で受け手に創作させていく消費の形式であり、著者は前著のタイトルにあるように「物語消費」と定義した。
そしてここからが著者による鋭い指摘なのであるが、「冷戦」や「昭和天皇の崩御」といった「大きな物語」の崩壊が嘯かれるのに対して、消費という限定的な領域とはいえ、現実を説話論的に管理していこうという動きとしてこれらの現象はあったのだと。「大きな物語」に対応する形で、「物語」によってミニマムな社会領域や消費者を管理していけるのではないかと。
さらに著者はここから一気に近代文学批判へと論を展開する。すなわち、「物語消費」は近代小説を終わらせると。与えられた枠組みの中で創作する大衆消費がありえるならば、「作者」という固有性は大きく揺らぐ。「著作権」も疑わしくなる。というのは、近代文学という制度内では、作者は固有性、独創性を特権的に与えられ、他者は「受け手」に甘んじていたが、「物語消費」はこれらの関係を根底から揺るがすものだから。自己表出の欲望や自己表現といった、私たちにとってあまりにも自明の、小説や文学とはこういうものだとする規定が氷解する。
ぼくの近代文学批判の大前提は、「私」と書きはじめてしまえば「私」があることを保証してしまうこの国の「文学」への懐疑です。つまり「私であること」と「作者であること」が日本の近代文学の中で、あまりに不可分のものとしてある。私小説への評価という問題を置いておいても、「私」という一人称で「私」について書くことが、「私」がそこにいることの立証になると同時に、作者として社会的に自己実現もできる、という不可分の結びつきが、日本の近代小説の一つの特徴になっています。
近代文学が「私」という枠組みを用意した制度であるならば、それとは違う形、つまり消費という形で物語りながら自己表出の欲求を拡散させていく形もあるのではないか、80年代末はそれへの移行期としてあったのではないかというのが著者の見立てである。この段階では、著者は「物語消費」へのカウンターの可能性に期待している。
ところで「物語消費」にはある傾向があった。それは、ある大きな架空の歴史像の中で物語が展開され、受け手もその架空の歴史像を共有する中で歴史の代わりとして遊んでいくという共有・交換の関係が。架空の歴史、すなわちフェイクヒストリーの担い手として村上春樹や「紀州サーガ」の中上健次がいる。その背景には、1970年代初頭に左翼運動が示したマルクス主義的な歴史像や未来設計が政治的に頓挫したことにがある。それよって、つまり「大きな物語」の消滅によって「歴史」の代替物として必要とされたのだと。言葉を換えれば、それらは転向文学といってよく、同じ意味で連合赤軍に行きそこなった安彦良和による『機動戦士ガンダム』は転向アニメーションと呼ぶことができる。
しかしながら、この現象がある時期から変化していったことに著者は注意を呼びかける。「歴史」を実感し、それを失ったので「替わり」を求めてしまう世代から、もはや最初からそれを求めない世代にシフトするという。彼らは歴史や地勢図として情報が有機的に配置された「場」で二次創作することはせず、データベース的に配置された情報群からサンプリングする(東浩紀「データベース消費」)。《そこでは因果律としての「歴史」はもはや求められないわけですから、代わりに因果律として、物語の構造が露出するか、あるいは物語が「情報」あるいは単に「刺激」としてしか受けとめられなくなります》。一言でいえば、それは一種のサプリメントとして読まれる。
こういった、いわばサブカルチャー領域における「歴史の消滅」と併行して、もう一つの大きな問題が、創作支援ソフトの実用化であると著者は述べる。その例として、ハリウッド映画のシナリオ作成ソフト「Doramatica」がある。「Doramatica」のように物語という行為をシステマティックに構築する技術が日本のソフト産業には圧倒的に足りず、その再構築が求められよう。そのような危惧から、著者は専門学校で物語の構造の反復トレーニングを生徒に身体化させる試みまでする。
しかしこの実践は著者にとって一つのジレンマとしてある。創作支援ソフトの実用化は近代文学を支えていた「作者」を根源的に無化させる、つまり、作者がアプリケーション化するということを意味するのであれば。それは著者にとっての根本的な問題であるところの近代文学の「私」についての問いそのものを無化させる恐れがある。「私」がどうなるもこうなるも、すでに必要性が奪われているのだから。
ところがそうはいっても、たとえ「私」の99%がアプリエーション化されたとしても、それを管理する主体はどうしても残るだろう、言い換えれば、近代的自我は揺るがないだろう、と著者は、守旧派としてギリギリのところで踏みとどまる。
『物語消滅論 キャラクター化する「私」、イデオロギー化する「物語」』
著者:大塚英志
発行所:角川書店
発行:2004年10月10日
Posted by 24wacky at 21:43│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした