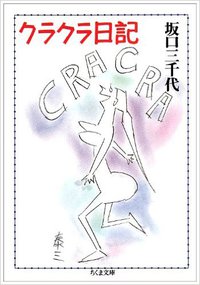2018年01月08日
『坂口安吾論』柄谷行人

柄谷行人はこれまで常に「え?どうしてこんなふうに読めるの?そんなこと書いてないだろう!」といった驚くべき読み=書きをわれわれに示してきた。漱石然り、マルクス然り、カント然り、フロイト然り、柳田國男然り。私は各々の原典にあたり、難儀して読み通し(たりできなかったり)、柄谷独自の読みとの違いを再度確認させられる。その結果、原典と柄谷の批評が私にとって等価的な「価値」と感じられたのが漱石であり、その他は未だそれほど読み込めていない。安吾はというと、依然柄谷の批評との距離が遠い。つまり、柄谷の読みを通した理解ができているとはいえない。だから柄谷の安吾論は面白いのだが、安吾はそうでもない。作品によって面白いものもあるが、そうでないものも多い、となってしまう。
安吾の原典と柄谷の安吾論についての私の読みの「ズレ」について、本書を読むと理解できる。柄谷によれば、そもそも安吾の書いたものは近代文学の規範に収まらない。それは安吾が意図的にその文学的ジャンルを破壊しようと企んでいたからに他ならない。そのスタイルは、小説が批評的エッセイのようであり、批評的エッセイが小説的であった。それらはファルス、説話、推理小説、歴史小説、古代史論、社会評論など幅広いジャンルにわたる。つまり、安吾のテキストは、私のように近代小説の規範に中途半端に侵食された文学青年崩れの「影響」の「深さ」と「浅さ」を露呈させる。
本書はいくつかの年代に書かれたものをまとめたもので、その時代ごとに興味深い批評がなされているが、その中からファルスと「穴吊し」についての視点を挙げる。ファルスとは、『風博士』『黒谷村』など安吾初期の作品にみられる「馬鹿バナシ」の系譜をさす。柄谷は、ファルスは安吾の初期作品に限ったことではなく、そういった一般的なジャンルの区分けが安吾にとって成り立たたずに書かれたものがファルス的であるという。さらに、それに近いものとして、漱石論で刺激的に論じられた正岡子規の「写生文」を例に出す。
「穴吊し」とは、キリスト教殉教者に対して幕府が考え出した処刑法である。それまでの拷問の苦痛はかえって殉教者たちの「死の欲動」を掻き立てさらなる殉教へと向かわせるが、「穴吊し」は吊された側は苦痛でも他人には滑稽にしか見えない。それを見て殉教者は減ったという。安吾は、殉教が与える効果を無化させてしまう装置を考案した者の洞察に着目する。自分は苦しんでいるが他人には滑稽にしか見えない、という。柄谷は、安吾がそれまで自分がやってきたことをそこに重ねることで、文学の出発点にしたのだと指摘する。ファルスと「穴吊し」をアクロバティックにつなげる次の引用には、ただ唸るしかない。
安吾は最初に鬱病を脱したあと、「ファルスの文学」を唱えた。以後、彼は狭義のファルスを書き続けたわけではない。しかし、ある意味で、彼のすべての仕事がファルスであったといえる。ファルスとはいわば、自らを穴吊しにかけることによって、生を肯定することだ。安吾は「生きよ」という言葉をくりかえす。しかし、いつも死のそばにいた。たとえば、東京に空襲が始まって人々が疎開し始めたとしても、彼はそこに残った。それは別にヒロイックな行為ではない。一方で逃げ回り生き延びることを考えていたからだ。戦争を見届けようという意志があったのでもない。彼は自らを「穴吊し」の刑に処したのだ、といってもよい。もちろん、生きるために、である。
(99ページ)
《自らを穴吊しにかけることによって、生を肯定すること》とは、嗜虐的になることでも自虐的になることでも、むろん、ない。だが、私はそれを積極的に指摘することができない。強いていえば、ノンシャランな文体から読み取れる古山高麗雄の《自己放棄》の形がそれに近い。それはいつもまわりの他人から少しだけ遅れてみえる。それは戦争を経験しているからこそ得られた深い認識などでは、ない。
余談になるが、私は1年ほど前『坂口安吾全集』(筑摩書房)月報に掲載された柄谷論考を読み漁っていた。それぞれが大部なので図書館で借りるのは持ち運びできる1回3冊までとし、該当部分をコピー。それを全回集まるまで繰り返して。それが本書の第一部として収められている。ほんの1年前に通読した内容だからそれを確認する程度とたかをくくってそれが"売り"の本書を手にしたものの、初めて読むような錯覚に陥る箇所が多かった。前回の読み方が浅かったといえばそれまでだが、全集の月報という媒体のユニークさと一冊の書籍の編集という仕事に対して新しい思いが生じた。
『坂口安吾論』
著者:柄谷行人
発行:インスクリプト
発行年月:2017年10月15日
2017/12/17
著者の散在したこれまでの書評を集めた本書は三部構成になっている。さしずめ晩期・早期・中期という区分をさせてもらうが、時系列が攪拌されている。そこがニクい。私はⅡ部に不意打ちを食らった。若き文学批評の言葉、レトリックの切れ味の鋭さに。あとがきにはこう書かれている。それら(ブログ主注・Ⅱ部・Ⅲ部…
2018/01/04
分厚い『柄谷行人書評集』のなかで最も面白かったのが本書の解説として書かれた一文であった。恥ずかしながら古山高麗雄という作家をそこで初めて知ったのだが、まだ知らぬ作家についての批評が面白く、その作家に俄然興味が湧き、しかもこの作家は自分の趣味に合っているに違いないという根拠の薄い確信が伴い、実…
2017/02/04
本書の言いつくせぬ魅力についてつらつらと思い巡らすのが愉しい。安吾の「無頼」ぶりが側近の妻によって私小説的に綴られ、日本文学史的価値がある?安吾に劣らずの三千代の「非常識」ぶりがノー天気な解放感を読む者に与える?そんなことよりも、はじめに確認しておこう。著者の「書く」ことの豊穣な力量について…
2017/01/27
正岡子規の「写生」概念の生成過程を夏目漱石との創造的「交換」をも交え読み解く試み。自分に俳句の教養があればと恨めしくなるほど想像力を刺激する。 俳句ジャーナリズム。それは子規による短詩型ジャンルの革新である。当時の日本の「短篇韻文」が、単純な「叙情」と「叙景」だけだったことに対して、子規…
2017/01/20
英文科の大学生だった頃の思い出。3年になるといよいよ本格的に専門科目を学ぶようになり、同時に、同じ文学部内で他の学科の単位も限定的に履修できるというシステムがあった。それを利用して履修した仏文科の「フランス文化」という単位は、シュールレアリズムの専門家であり、あのブルトンの『ナジャ』などの翻…
2017/01/18
岩波書店の全集刊行などで漱石リバイバルがあった1990年代(今の話ではなく)、雑誌『漱石研究』の編集など、著者はその中心にいた。本書『漱石を読みなおす』は新書版ではあるが、独自の読みをフル稼働させている。当時その仕事には大きな刺激を受けたものだ。さて、小森陽一は『猫』をどう読んでいるか。 小…
2017/01/17
年末年始から現在まで坂口安吾について考え、読み漁っている。それに関連して、国民的作家のデビュー作について考えたいことがあり、久方ぶりに本書を紐解く。 『吾輩は猫である』誕生の以下の経緯は有名である。当時本人認めるところの「神経衰弱にして兼狂人のよしなり」であった漱石を見かね、俳人仲間の高…
2016/12/31
坂口安吾といえば、「戦争に負けたから堕ちるのではないのだ。人間だから堕ちるのであり、生きてゐるから堕ちるだけだ。」というエッセイ『堕落論』が著名であるように、戦争体験を独特なデカダンスで表現した「無頼派」の作家として有名である。『白痴』『桜の森の満開の下』などが評価が高く、その他にも歴史小説…
Posted by 24wacky at 10:52│Comments(1)
│今日は一日本を読んで暮らした
この記事へのコメント
激しく同意しながら読ませてもらいました!!!
本当に、何でそんなふうに読めるんじゃあ〜〜〜!!!!!!
の連続ですよね。柄谷って。笑
わたしはあらゆる作家の中で坂口安吾がもっとも好きですが、この人物を正面から取り上げて本格的に論じた人って意外に少なくて驚きです。その中でも安吾の文章そのものと独立した形で、安吾論を優れた作品として読ませてくれる柄谷には本当に尊敬しかありません。んでもって、こちらのブログにはその柄谷の安吾論の面白さが面白く語られていて、強く共感した次第です。穴吊るしとファルスをつなげるところ、本当に唸りますね!!
本当に、何でそんなふうに読めるんじゃあ〜〜〜!!!!!!
の連続ですよね。柄谷って。笑
わたしはあらゆる作家の中で坂口安吾がもっとも好きですが、この人物を正面から取り上げて本格的に論じた人って意外に少なくて驚きです。その中でも安吾の文章そのものと独立した形で、安吾論を優れた作品として読ませてくれる柄谷には本当に尊敬しかありません。んでもって、こちらのブログにはその柄谷の安吾論の面白さが面白く語られていて、強く共感した次第です。穴吊るしとファルスをつなげるところ、本当に唸りますね!!
Posted by 安吾好き at 2021年10月19日 12:23