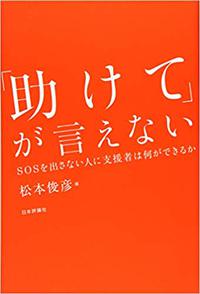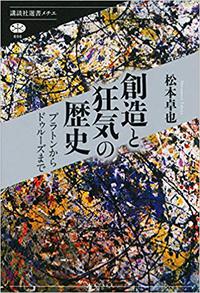2019年12月23日
2019年 本ベスト10
医学書院の〈シリーズケアを開く〉(毎日出版文化賞を受賞)の3冊を含め、はっきりと傾向が現れた今年。あとは沖縄と女性作家。

『共同の力 一九七〇〜八〇年代の金武湾闘争とその生存思想』
著者:上原こずえ
発行:世織書房
発行年月:2019年5月24日
掲載:沖縄タイムス2019年7月6日
本書は沖縄が施政権返還時に推進された石油備蓄基地(CTS)建設と東海岸埋立に対して組織された金武湾闘争についての研究書である。著者が着目するこの運動の意義とは、基地経済の代替=「平和産業」として石油産業の誘致を推進した屋良朝苗革新県政とそれを擁立した革新政党、労組に抗し、「豊かさとは何か」を問い、価値観の転換を迫る新たな方向性を示した「住民運動」という点にある。開発=経済発展=平和というイデオロギーに対して、当時の県民の多くが盲目的だったことを、今を生きる我々は批判できるだろうか。

『共同の力 一九七〇〜八〇年代の金武湾闘争とその生存思想』
著者:上原こずえ
発行:世織書房
発行年月:2019年5月24日
掲載:沖縄タイムス2019年7月6日
本書は沖縄が施政権返還時に推進された石油備蓄基地(CTS)建設と東海岸埋立に対して組織された金武湾闘争についての研究書である。著者が着目するこの運動の意義とは、基地経済の代替=「平和産業」として石油産業の誘致を推進した屋良朝苗革新県政とそれを擁立した革新政党、労組に抗し、「豊かさとは何か」を問い、価値観の転換を迫る新たな方向性を示した「住民運動」という点にある。開発=経済発展=平和というイデオロギーに対して、当時の県民の多くが盲目的だったことを、今を生きる我々は批判できるだろうか。
2019/12/14
「カント通り」「カール・マルクス通り」「マルティン・ルター通り」・・・というようにベルリンの通りの名前が各篇についた短篇集。「わたし」は「百年」の歴史を現在形で「散歩」する。目にする外部からの刺激のひとつひとつに対し、あるいは異物としてのコトバについて、初発の物語を想像しては戯れる「わたし」…
2019/09/30
子どもの自殺予防においてなされる「SOSを出してほしい」、「援助希求能力を高める」というスローガン。確かにそれは間違っていないが、ちょっと待ってほしいと、編者であり、自殺予防や薬物依存症の問題に取り組む精神科医の松本俊彦氏は危機感を露わにする。援助希求能力が乏しいとすれば、そこにはそれなりに理由…
2019/09/15
注目される「発見」された作家の作品集。その中から「どうにもならない」を例に、初見の雑感。 アルコール依存症の女に深夜、発作が始まる。彼女は部屋中の現金をかき集め、歩くと45分はかかる酒屋へと向かう。失神寸前になりながらもたどり着いた開店前の酒屋の前には黒人の男たちがたむろしている。男たちは…
2019/09/14
精神病理学・精神分析が専門の著者が訪問看護師へのインタビューをもとに、倫理的な問いとして何を発見し、何を学んだかが書かれている。特徴的なその手法は、多数のデータを材料に客観的な視点から比較するのではなく、看護師の実践を尊重し、あくまでその視点から記述するというもの。その聞き取りから、「快適さ…
2019/08/15
本書は生活史についての理論書である。ポップでキャッチーなタイトルに騙されてはいけない(私は騙された)。ガチガチの理論書である。著者はこれまでの著作において、生活史の聞き取りとは何かを、学術書、語りの「ダダ漏れ」、エッセイ、小説といった多岐にわたるスタイルで伝える試みをしてきたが、まだ伝わって…
2019/07/18
西洋思想史に「創造と狂気」という論点を設定し、体系的に読みやすく、しかも読み応えある内容に仕上げている。臨床的なワードと思想が交差され、「こんな本が読みたかった」と思える一冊。 統合失調症中心主義。それは、統合失調症者は普通の人間では到達できないような真理を手に入れているという考え。悲劇…
2019/05/11
沖縄の精神科デイケア施設で心理士として勤務した4年間をエッセイ形式で綴った学術書。現在の自分の関心領域にあまりにもハマり過ぎる内容であり、時間を忘れて一気に読んでしまった。その関心とは、1に設定が沖縄であること、2に精神疾患のケア(とセラピー)についてのリアルな現場報告であることの切実さ、3…
2019/03/09
文庫にして570頁の大著、著者のまわりくどさここに極まれりという感がある。初見では100頁あたりで挫折、しばらくデスク上に“積ん読”状態にしたが、ふと、あるとき、「とって読め」との命令が下され(聖アウグスティヌスか俺は!?)、再読後、一気に読み終え、それで終わらず、直後にメモを取った何ヶ所もの重要部…
2019/01/06
中学に入学し、初めて英語を学び、能動態と受動態という2つの態がある(それだけしかない)と教えられた。だが、日常的に用いている言動として、この2つでは括れない場合があるのではという漠たる疑問があった。本書によれば、中動態という態が、古代からインド=ヨーロッパ語に存在したという。中動態というと、…
Posted by 24wacky at 21:08│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした