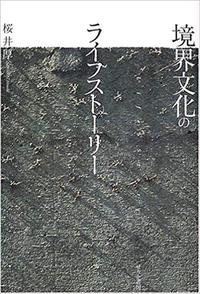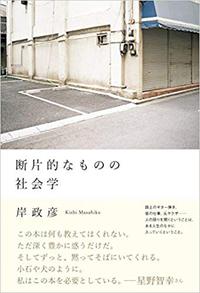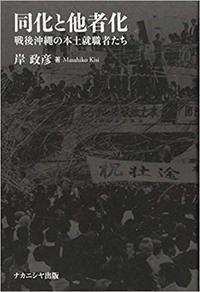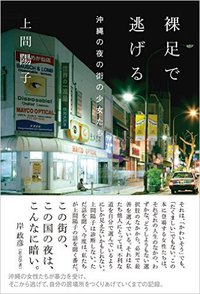2019年08月15日
『マンゴーと手榴弾─生活史の理論─』岸政彦

本書は生活史についての理論書である。ポップでキャッチーなタイトルに騙されてはいけない(私は騙された)。ガチガチの理論書である。著者はこれまでの著作において、生活史の聞き取りとは何かを、学術書、語りの「ダダ漏れ」、エッセイ、小説といった多岐にわたるスタイルで伝える試みをしてきたが、まだ伝わっていないだろうという強迫観念からか、あるいはたんにしつこく書きたいだけなのか定かでないが、今回は「これでもか」とばかりに、先行する生活史法の批判も徹底させながら展開している。
それは一言でいえば、語りを聞くということは、鉤括弧を外すということである。鉤括弧を外すといえば、語り手の語りに施す引用符をつけないことかと思う。なるほど、これまでの著作は、どれもそのようなスタイルをとっている。地の文とはスペース、インデントなどによって一応の区分けはされるが、地の文との混入による一体感のような独特の印象を読者に与えているが。
しかしそれは表面的な問題であり、鉤括弧を施すことによって、語られている内容と語りそのもの(形式)が切り離されてしまうのではないか、そもそも両者は切り離すことができないのではないかといっている。それは語り手と聞き手による共同作業であり、「私たちは、あるひとつの、あるいは複数の規範的な関係性のなかに、長い時間をかけて引き込まれるのである」(〈マンゴーと手榴弾──語りが生まれる瞬間の長さ〉)というように、持続的な実感そして実践としてある。「引き込まれる」という言葉からは、「中動態の世界」(國分功一郎)さえ、私は想像してしまう。
本書で語られる生活史は沖縄での聞き取り調査によるものがほとんどである。興味深いのは、著者にとって沖縄の語りを聞くことが、理論をより促すと思えるところである。というか、それこそ両者は相補的な関係にある。生活史を含む、沖縄についてのあらゆる定説的な言説と著者が聞き取る語りとの違和が、鉤括弧を外すその瞬間にあらわになる、というように。
飢えで苦しむ沖縄戦の渦中に貴重な食料補給となっ小麦粉が、日本軍の特攻機の攻撃で撃沈した米軍の軍艦から浜辺に流れてきたものであった、その小麦粉。普天間基地の近くに新築した家に住む女性の語りからは、「嫌なら出ていけばいい」という排除の言葉でその責任を負わせることの軽さとは比較にならない、そこで生きている個人の日々の暮らしがある。ヤンキーグループの男と半ばレイプのような初体験をした後に、女子中学生が友だちの家に逃れ、飲みたいというココア。これらのディテールはどれも、「何かについて自分たちも何か言いたくなる」瞬間に現れる。それは同時に「一般的なもの、普遍的なもの、実在するものに触れた瞬間である」。
これらの語りの多くが沖縄戦体験者、基地周辺住民、下層に属する若者というように、マイノリティといってよい人たちによるものであるのに対し、〈沖縄の語り方を変える──実在への信念〉の語りはやや異なる。それは地域誌の編纂に関わる若い世代の語りとして紹介される。これまでの沖縄の地域誌そして民俗学は、沖縄戦によって壊滅的な被害を受けたことで奪われてしまった独自の文化を対象としてきた。これらの書き手たちにとって、その独自の文化は自明でありずっと前からそうだったものとしてある。ところが、著者によれば、それはむしろ逆で、沖縄戦で奪われた後に実体化され、研究の対象となり、再び見出されたというのが正しいのではないか、と。
それに対し、中南部にある合併されてできた「A市」史編纂室のM氏は、新興住宅地を現代版の「屋取(ヤードウイ)」(琉球士族出身の寄留民たちが作った村)であると語り、それを聞き取りの対象とする、これまでにない画期的な取り組みを実践している。著者はこの語りかえを、従来のそれらに比べ、「より事実に合致したもの」「より真正なもの」として捉えられ、沖縄の語り方を変えることを意味すると評価する。
「沖縄らしさが失われていく」という語りから距離を置いたこの手の認識は、沖縄のある年代から下の世代において、むしろありふれているというのが、私の沖縄での生活感覚としてある。ただ、それは公的な場で語られることが少ない。だから外から見れば、新しく感じられるだろう。著者もそれはわかったうえで、あえて「実在への信念」という見得を切るような言葉でアジテートしている。その「世俗化」された語りについて、今後多くの議論が生まれることを期待したい。
『マンゴーと手榴弾─生活史の理論─』
著者:岸政彦
発行:勁草書房
発行年月:2018年10月20日
2019/08/13
タイトル通り、ライフヒストリーについてのわかりやすいガイドブックである。社会学の研究者を主な対象としているが、その外へ開いていく工夫のある編集となっている。 〈2章 ライフヒストリーの可能性〉(谷富夫)はその中でもガイダンス的な役割を与えられた章である。ライフヒストリーとは何か、どんな意…
2019/08/12
滋賀県琵琶湖東側の被差別部落地域への生活史調査である。 「境界文化」とは、被差別部落の生活が、国家、官僚、大企業などの支配的文化の制度や規範から自由であるだけでなく、それらに抵触し、矛盾し、侵犯し合うことがある「生活の論理」を持っていることを指す。 それを描くには、研究者によるので…
2019/08/11
社会学者として多くの生活史の聞き取りをしてきた著者には、社会学の枠から外れる断片的なエピソードの数々が忘れられない。分析や解釈を施さぬ無意味な断片への偏愛。 最初の章「人生は、断片的なものが集まってできている」でも、お互いに関連性のないエピソードのいくつかが改行を挟んで記される。その中の…
2019/08/10
2013年の発行時に、本書を当時主宰していた沖縄オルタナティブメディア(OAM)の「沖縄本レビュー」寄稿のために読み、レビューした(データはなぜか探し出せなかった)。今回、本書を含め、その後注目を集めることになる岸政彦氏の著作をまとめて読むことにした。それは、これから着手する新しい仕事の参照とするた…
2017/02/28
「裸足で逃げる」とは、なんと沖縄の「現実」に刺さるタイトルだろう。あの亜熱帯の夜の、生暖かい、しかしひんやりとしたアスファルトを思わず踏みしめたときの素足の触覚が、混濁したいくつものエモーションを拓き、一条の微かな光線の可能性を喚起させる。コザのゲート通りをゲート側から捉えた夜景の表紙写真と…
Posted by 24wacky at 19:54│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした