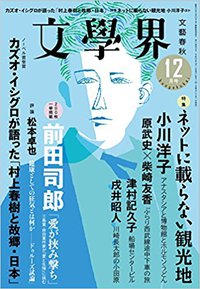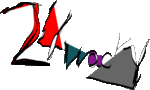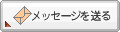2019年01月06日
『中動態の世界 意志と責任の考古学』國分功一郎

中学に入学し、初めて英語を学び、能動態と受動態という2つの態がある(それだけしかない)と教えられた。だが、日常的に用いている言動として、この2つでは括れない場合があるのではという漠たる疑問があった。本書によれば、中動態という態が、古代からインド=ヨーロッパ語に存在したという。中動態というと、能動態と受動態の中間のような態なのかといえば、そうではない。中動態は能動態と対立するものとして先に生まれ、その後中動態から受動態が派生したというのだから。
能動態と受動態の対立が「する」と「される」だとすれば、能動態と中動態の対立では、主語が過程の外にあるか内にあるかが問われる。前者の主語が過程の外に、後者は内に。本書にあるギリシア語から中動態の具体例を挙げてみる。ものが「できあがる」。これは生成の過程が表現されている。誰かが何かを「欲する」。心のなかから欲望がわき起こり、それによって突き動かされる過程のなかに主語はある。
そもそも中動態への著者の関心は、意志という概念への疑いが根本にある。能動態と受動態の対立には、それが強くある。「私が私の意志でそうする」、「私は彼女の意志によってそうされた」というように。
〈第5章 意志と選択〉で、著者はハンナ・アーレントを参照しながら、「意志」と「選択」の違いについて論じる。選択は諸々の要素の相互作用の結果として現れる。その行為が過去からの帰結であれば、それは選択である。これに対して意志は、過去から切断された絶対的な始まりという場があるとき生まれる(いかにもアーレントが言いそうなことだ)。だから、何らかの行為を自らの意志で開始したと想定されるとき、その人はその行為の責任を問われる。
日常において、両者はしばしば混同される。というか、あらゆる行為は選択である。しかし、その選択に責任が生じた場合、それは意志とみなされる。あなたがその行為をしたのはあなたの意志でやったのだから責任を負うべきである、というロジックで。意志とは《過去からの帰結としてある選択の脇に突然現れて、無理やりにそれを過去から切り離そうとする概念である。しかもこの概念は自然とそこに現れてくるのではない。それは呼び出される》(132ページ)。
言語学の歴史をみれば、その後中動態は失われ、能動態と受動態が対立するようになる。現在のわれわれが持ってしまっているパースペクティヴである。そのときに現れたのは、単に行為者を確定するだけではない、行為を行為者に帰属させる言語が誕生したということだ。逆にいえば、中動態とは、行為を行為者に帰属させない言語、ということになる。
本書で最も力の込められた〈第8章 中動態と自由の哲学──スピノザ〉では、中動態が重要な観念であることを『エチカ』の著者が意識していたという論が展開される。有名な一節「神はあらゆるものの内在原因であって、超越原因ではない」の「超越」は、「他動詞の」と訳すこともできる。超越原因とは、その作用が他に及ぶ原因のことを指す。これに対し「内在原因」とはこういうことだ。神なる実体とは、宇宙あるいは自然そのものに他ならず、実態が「変状」したものとして万物は存在している。あらゆるものは神の一部であり、神の内にある。神は作用するが、その作用は神以外の何物にも届かない、と。著者はこの内在原因こそ中動態的だという。
「変状」することによって、神は何かしらの刺激を受ける。《しかしそれらは神自身から発したものである。つまり神は自らを刺激している。刺激を受けるのだから、神はそれら刺激を有することになる。有するというと自らの外にあるものを手に取るというニュアンスが出てしまうが、もちろんそういうことではなくて、神はその刺激によってある状態へともたらされるということである。しかし、繰り返しになるが、神に刺激を与えているのは神自身なのだから、「される」という言い方は不正確である。神がそうした状態になるのだ》(241ページ)。
このような引用をすると、「中動態とは神のレベルのことで、われわれ人間には無理なのか」という声が聞こえてきそうだが、そうではない。中動態はわれわれの日常にありふれている。その点、第5章でミシェル・フーコーの権力論とアーレントのそれとの違いから発展させて論じられる「仕方なく〜する」というわれわれの態度が参考になる。「不良から脅されたので仕方なく金を渡す」。「食うために仕方なく働く」。強制はないが自発的でもなく、自発的ではないが同意している。このような事態は能動態と受動態の対立として捉えるのには無理がある。能動態と中動態の対立として捉えることですんなりと記述できる。
冒頭の〈プロローグ〉は、薬物依存症当事者と「僕」との架空の会話で成立している。薬物依存症は病気だということを理解する「僕」は、一方で、自分の意志でクスリをやめられないのかと思ってしまうと言い、当事者は、むしろそう思うとダメだと返す。絶えずズレている二人の会話の終わり近く、当事者は「しゃべってる言葉が違う」と、救いのないオチのようにこぼす。著者に本書を書かせたのはこの「対話」の衝撃であろうし、本書が医学書院〈シリーズ ケアをひらく〉の一冊として発行されたことも確信犯的である。
「する」と「される」の外側に出たいと希求すること。その内側に囲われた息苦しさが私のまわりにあるのがみえる。1つは、障害当事者と支援者とのあいだに。2つは、沖縄とヤマトの対立における「意志」と「責任」について。
『中動態の世界 意志と責任の考古学』
著者:國分功一郎
発行:医学書院
発行年月:2017年4月1日
2018/12/08
対談─来るべき当事者研究─当事者研究の未来と中動態の世界熊谷晋一郎+國分功一郎 興味深い二人の対談において、2つの対立軸を乗り越える方向性が確認できた。1つは、能動/受動の対立軸、2つは、運動と研究の対立軸である。 まずは、能動/受動の対立軸について。 熊谷晋一郎は國分功一郎著『中…
2018/06/02
認知の方法を著者は二つのタイプに分ける。頭の中の映像を使って思考する視覚優位と、言葉を聴覚で聴き覚え、理解し、思考する聴覚優位とに。これらの特徴は普通の人々にもあるが、発達障害ではその偏りが強くなる。著者は「偏り」を「優位性」とポジティブに表現する。自身映像思考の著者が室内設計家として成り立…
2018/01/02
今もっとも注目する松本卓也論考の概要。 ドゥルーズは「健康としての狂気」に導かれている。その導き手として真っ先に挙げられるのが、『意味の論理学』(1969年)におけるアントナン・アルトーとルイス・キャロルであろう。アルトーが統合失調症であるのに対し、キャロルを自閉症スペクトラム(アスペルガー症…
2017/09/08
対話を実践する試み「ミーティング文化」では、〈自分の言葉で語ること〉に価値が置かれる。 ハンナ・アーレントは「言葉と行為によって私たちは自分自身を人間世界のなかに挿入する」といった(『人間の条件』)。アーレントが面白いのは、ひとが言葉によって自分を表すときに、自分がいったいどんな自分を明…
2017/09/06
オープンダイアローグではポリフォニーが強調される。そこでは「すべての声」に等しく価値があり、それらが一緒になって新しい意味を生み出していくと。しかし、実際のミーティングにおいて、多くの声が響いていたとしても、それのみで既存の文脈がはらむ力関係を無効化できるものではない。 リフレクティング…
2017/09/05
オープンダイアローグの前提は「わかりあえないからこそ対話が可能になる」。コミュ力の対象は「想像的他者」、すなわち自己愛的な同質性を前提とする他者。その対極はラカン的な「現実的他者」で、決定的な異質性が前提となるため対話もコミュニケーションも不可能。それに対しダイアローグの対象は「象徴的他者」…
2017/09/04
エビデンス主義は多様な解釈を許さず、いくつかのパラメータで固定されている。それはメタファーなき時代に向かうことを意味する。メタファーとは、目の前に現れているものが見えていない何かを表すということ。かつては「心の闇」が2ちゃんねるのような空間に一応は隔離されていた。松本卓也がいうように、本来だ…
2018/10/08
精神病理学には3つの立場がある。記述精神病理学、現象学的精神病理学、そして力動精神医学(精神分析)という。 ヤスパースに始まる記述的精神病理学は、患者に生じている心的体験(心の状態や動き)を的確に記述し、命名し、分類する。その際、「了解」という方法がとられる。「了解」とは、医師=主体が患…
2018/04/09
精神分析を可能にした条件とは、近代精神医学が依拠した人間の狂気(非理性)とのあいだの関係を、言語と、言語の限界としての「表象不可能なもの」の裂け目というパラダイムによって捉え直すことであった。1950〜60年代のラカンの仕事は、フロイトが発見した無意識の二重構造を、超越論的システムとして次のように…
2018/01/02
今もっとも注目する松本卓也論考の概要。 ドゥルーズは「健康としての狂気」に導かれている。その導き手として真っ先に挙げられるのが、『意味の論理学』(1969年)におけるアントナン・アルトーとルイス・キャロルであろう。アルトーが統合失調症であるのに対し、キャロルを自閉症スペクトラム(アスペルガー症…
2017/02/12
『atプラス 31号 2017.2 【特集】他者の理解』では、編集部から依頼されたお題に対し、著者はそれが強いられているとアンチテーゼを掲げる。「他者の理解」こそ、共生社会にとって不可欠ではないのか。いったいどういうことか? 急増する発達障害、ASD(自閉スペクトラム症)は、最近になって急に障害者とされ…
2017/03/08
本書は思想家の「入門もの」であるが、ハンナ・アーレントがドイツを離れて亡命するきっかけに切り口をしぼっている。アーレントが亡命したのはナチスの迫害を逃れるためであったことはいうまでもないが、「出来事」としてより注目すべき点がある。それは、それまで信頼していた友人たちがナチスのイデオロギーに幻…
2008/12/14
「『世界共和国へ』に関するノート」のためのメモ その4『暴力について』でアーレントが「評議会」をモデルにした世界連邦に国家の揚棄を見出していることは注目すべきだ。そこでは、現在の国家機構の上に立つようなものではなく、各地にできた評議会国家の連邦が語られている。現在の国家を前提にするのではなく、…
Posted by 24wacky at 11:42│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした