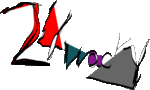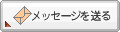2017年03月08日
『アレント入門』中山元

本書は思想家の「入門もの」であるが、ハンナ・アーレントがドイツを離れて亡命するきっかけに切り口をしぼっている。アーレントが亡命したのはナチスの迫害を逃れるためであったことはいうまでもないが、「出来事」としてより注目すべき点がある。それは、それまで信頼していた友人たちがナチスのイデオロギーに幻想を抱いたことに衝撃を受けたことにある。ドイツの良心的な善良な市民が、なぜユダヤ人の迫害に目をつぶり、ナチスの道徳規範を受け入れたのか、という。
そもそも大衆は政治的・公的な問題に無関心であり、そのため孤立する。全体主義は孤立した人間たちを支配するため、「一切の経験に依存しない」イデオロギーを用いる(『全体主義の起原』)。
人間には三つの活動性がある。労働(labor)、仕事(work)、活動(action)という。活動は、わたしたちが他者と対話をするとき、集会で発言するとき、他者に働きかけ、生きる世界をよりよいものにしようとする。生命の維持を目的とした労働や、作品を製作する仕事とは異なる。
活動によって生み出される「世界」は、政治的な活動が展開される公共的な領域よりも広い。他者とのあいだである場が開かれるとき、そこに「現れの空間」が生み出される。「わたしが他人の目の前に現れ、他人がわたしの目の前に現れる空間」である。人々は活動と言論において、自分が誰であるかを示し、「わたし」というアイデンティティを獲得できる。
古代ギリシアのポリスでは、自己の家族の生存のための私的な領域と、ポリスにかかわる市民の公的な活動のための公的な領域が明確に分離していた。
しかし、近代に入ると「社会」が誕生する。社会の特徴は、人々が顔のない群衆であり、画一主義である。画一主義によって、すべての人が自分の利益を守るという原則に従って「行動する」(behavior)。行動が活動にとって代わる(『人間の条件』)。
「悪の凡庸さ」とは、ユダヤ人を強制収容所へ移送する指揮者だったアイヒマンの犯した悪は巨悪であるが、その人物は凡庸な人物だったという逆説をいう(『イェルサレムのアイヒマン』)。
ここで冒頭の問いに戻る。アーレントは、アイヒマンに見出した「悪の凡庸さ」を、アイヒマン個人の問題に矮小化するのでなく、ナチスのイデオロギーに幻想を抱いた彼女の友人たち、当時の全ドイツ国民、さらには近代社会に普遍的な問題として見出す。
なぜ「悪の凡庸さ」は生まれるのか。一言でいうと、「考える」という営みを放棄するからであると、アーレントは結論づける。では「考える」とはどういうことかを「考える」のが、連続講義「道徳哲学のいくつかの問題」を取り上げた、最もスリリングな「第4章 悪の道徳的な考察」である。
道徳が崩壊したナチス時代のドイツにも、親衛隊に入れられようとしてこれを拒み死刑を宣告された二人の兄弟がいた。「ぼくたち二人は、あのような重荷を心に負うくらいなら、死んだほうがいいと思います。親衛隊の隊員がどのようなことをしなければならないかを、ぼくたちは知っています」という言葉を遺して。
アーレントはこの言葉から三つの原則を立てる。すなわち、自己愛の否定、他者の立場に立つ想像力の重視、自己のうちのパートナーをある種の「手本」として選択する。この思考はカントの『判断力批判』から導き出される。
「わたしにはそのようなことはできない」という判断を、たんに直観によるものでなく、そこに道徳的な原理があるはずだと再構築すること。これがアーレントの仕事であった。だが、著者は最後にこう付け加える。「ただし人々がつねにこうした道徳的な判断を下すとは限らない。現代では、自分の自己のパートナーがどのような人でも別に気にならないという人が多くなっているかもしれないからである」と。だからこそ、本書はアーレントの原典と併せて読まれねばならないだろう。
ここで付言すれば、ヒトラー・ユーゲント来日を目撃したときのおじやおばたちの子ども時代のおぞましい記憶と共にある「フテキカクシャ」という言葉に、人生をかけて拘泥する主人公を描いた津島佑子『狩りの時代』を同時代に読むことの意味を考えざるをえない。
2016/10/09
3章では、障害を負って生まれた兄の耕一郎と絵美子が自宅二階の物干し台から屋根へと冒険し、となりの風呂場の開け放たれた窓から若い女性が水浴びしているのを盗み見するところから始まる。規範から「自由な」兄とその援助者の妹がとる行動は、かつての国民的作家の「猫」がそうであったように、移動して見るとい…
2017/03/04
津島佑子の遺作『ジャッカ・ドフニ 海の記憶の物語』(2016年)は、なぜ、3・11後の状況とアイヌの「生存の歴史」を結びつけながら書かれたかと問う刺激的な論考である。 同作品への評価としては、少数民族に対する日本人の無理解と無関心への「悲しみと憤り」が津島の執筆動機だとする川村湊の論考「”ジャ…
2008/12/14
「『世界共和国へ』に関するノート」のためのメモ その4『暴力について』でアーレントが「評議会」をモデルにした世界連邦に国家の揚棄を見出していることは注目すべきだ。そこでは、現在の国家機構の上に立つようなものではなく、各地にできた評議会国家の連邦が語られている。現在の国家を前提にするのではなく、…
2008/12/10
『世界共和国へ』に関するノートのためのメモ その1チョムスキーはThe future government(1971)という講演の中で4つの政体を論じたが、柄谷はそれを次の図のように展開した。Dのリバタリアン社会主義は、反資本主義的であるのみならず、スターリニズム(国家社会主義)を、また福祉国家と柔らかな国家管理を…
2008/06/06
第Ⅳ部 世界共和国1 主権国家と帝国主義これまで「世界帝国」から「世界経済」への過程で、資本=ネーション=国家が形成されたことをみてきたが、第Ⅳ部では、それがその後に、どのように変容したか、あるいはしなかったかを考えたい。それは20世紀に顕著になった帝国主義の問題にかかわっている。レー…
『アレント入門』
著者:中山元
発行所:ちくま新書
発行年月:2017年1月10日
Posted by 24wacky at 19:38│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした