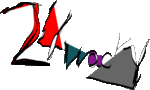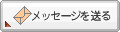2016年10月09日
『狩りの時代』

3章では、障害を負って生まれた兄の耕一郎と絵美子が自宅二階の物干し台から屋根へと冒険し、となりの風呂場の開け放たれた窓から若い女性が水浴びしているのを盗み見するところから始まる。規範から「自由な」兄とその援助者の妹がとる行動は、かつての国民的作家の「猫」がそうであったように、移動して見るという文体を可能にする。それは絵美子にとって耕一郎との追憶の日々である。
いとこの晃がかつて耳元でささやいたというおぼろげな記憶でしかない「フテキカクシャ」という言葉に、絵美子はその後の人生を通して拘泥する。どうして晃はあんな恐ろしい言葉をささやいたのか、と。その記憶の曖昧さが装置として小説を牽引する。小説の後半で、それをささやいたのが晃ではなくもう一人のいとこの秋雄であったらしいことがようやく判明するが、それとて三人とも遠い昔の記憶にもとづくため曖昧さが残る。つまり、その言葉を発したのは、あなただったかもしれないしわたしだったかもしれない、と読むことが可能だ。小説前半でほのめかされるヒトラー・ユーゲント来日を目撃したときのおじやおばたちの子ども時代のおぞましい記憶が後半で明らかにされるが、それも同じようにあなたやわたしなのだ。
小説は絵美子の父、母、おじ、おばといった大家族のとぎれとぎれの歴史的記憶で構成される。そのなかで彼女や彼らは、敗戦国日本が戦勝国アメリカに対して抱く転倒した憧憬をほぼ無反省に保持し隠そうとしない。まさに「敗北に抱かれて」生きる。彼女らそして彼らは「敗北に抱かれ」つつ、同時に「狩り」(差別)をなかば無自覚にする。それが日本人だ、と作家は記しているのか。
最後の9章では、長年のアメリカ生活の末、意識を失い倒れたおじの永一郎が、病室で意識朦朧としながら、その若き日に新妻の寛子と共にアメリカへ旅立つ羽田空港での門出のスピーチを追憶する。そのとき大きな揺れが起こり、原子力発電所が爆発したという声が聞こえる。その後演説の記憶に戻るが、核物理学者の永一郎は原子力と人類は共存できないと語り、自らの傲慢さを反省している。ここで「3・11」が現れるのはあまりにも唐突である。
「差別」と原発時代の生。この二つの関係性をどう認識し、書くか。作家が病魔に犯されなければ、おそらく紙数をより費やして書かれたであろう大きなテーマとして、われわれの前に提示された。
『狩りの時代』
著者:津島佑子
発行所:文藝春秋
発行:2016年8月5日
Posted by 24wacky at 09:59│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした