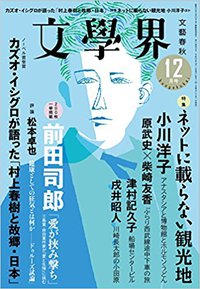2018年04月09日
『享楽社会論 現代ラカン派の展開』松本卓也

精神分析を可能にした条件とは、近代精神医学が依拠した人間の狂気(非理性)とのあいだの関係を、言語と、言語の限界としての「表象不可能なもの」の裂け目というパラダイムによって捉え直すことであった。1950〜60年代のラカンの仕事は、フロイトが発見した無意識の二重構造を、超越論的システムとして次のように体系化することにあった。つまり、一方では、言語使用のメカニズムを支配する象徴界があり、それは〈父の名〉という特権的シニフィアンによって統御されることで初めて正常に作動する。他方では、象徴化に抗する「表象不可能なもの」としての現実界があり、そこで一瞬だけ垣間見られる真理を、「対象α」、あるいは「テュケー(偶然)」と呼んだ。
このシステムは神経症と精神病を区分けすることを可能とする。無意識に支配される神経症者は「正常者」から地続きのものとされ、無意識に支配されない=〈父の名〉によって統御されない精神病者は、排除された〈父の名〉をめぐって生じる「過程」に従い妄想を発展させる。それにより精神病者のみがエディプスコンプレクスから逃れる例外者として機能するのだ、と(『人はみな妄想する━━ジャック・ラカンと鑑別診断の思想』松本卓也)。
ドゥルーズとガタリはこの二分法に異議を唱えた。彼らによれば、無意識はすべてエディプスコンプレクスに支配されているわけではなく、神経症・精神病・倒錯を含むあらゆる人間が自らの「過程」を生きうる。それらの臨床的形態は、「過程」がエディプス的な壁に突き当たった結果として生じるものに過ぎないのだ、と(『アンチ・オイディプス 資本主義と分裂症 上・下』ジル・ドゥルーズ+フェリックス・ガタリ)。
しかし、このようなドゥルーズ+ガタリによる批判は、1958年までのラカン理論に対してまでがその有効期限であり、後期ラカンはドゥルーズ+ガタリによる「エディプス的でないような仕方で生きる」というモチーフを共有していたことに著者は注意を促す。70年代のラカンは、エディプスコンプレクスは人間の心的構造のトポロジカルな結び目をつなぎあわせる複数の方法の一つにすぎないとし、非エディプス的で倒錯的な欲望を重視するように態度を変えていたのだから。
『アンチ・オイディプス』とその後の『千のプラトー』『哲学とは何か』がドゥルーズ+ガタリによる資本主義打倒の戦術書だとすれば(『三つの革命 ドゥルーズ=ガタリの政治革命』佐藤嘉幸 廣瀬純)、ラカンにとって精神分析は「資本主義からの出口」という位置づけであった(91ページ)。
これはどういうことか。ラカンによれば、「資本主義のディスクール」に喪失は存在しない。
つまり、資本主義のディスクールに喪失は存在しないのである。これは、資本主義のディスクールでは次々と新しい商品が主体にあてがわれることによって主体の欲求や要求がすぐに満足させられてしまい、欲求の彼岸に穿たれる欠如を介してあらわれるはずの欲望の領野があらわれてこない、ということを意味する。このような体制においては、主体を構成する存在欠如への接近が不可能になる。つまりそこでは、喪失なしに享楽の復元が可能であるという空想(幻想)が主体に与えられることになるのである。
(90ページ)
振り返っておこう。ラカン理論にとって欲望とは、「満足を求める欲求〔要求1〕ではなく、愛の要求〔要求2〕でもなく、後者から前者を引き算することに由来する差異」、二者間に生じるうまくいかなさのことを指した(『人はみな妄想する━━ジャック・ラカンと鑑別診断の思想』松本卓也)。これが「欲求の彼岸に穿たれる欠如」のことである。資本主義体制における主体は、その彼岸に接近する前に絶えず新しい商品があてがわれ満足してしまう。よって欲求や要求は満たされても、それは欲望には達しない、すなわち享楽は復元されない。私たちは無限の「享楽(エンジョイ)」を際限なく課せられる。そこで精神分析が資本主義からの出口となるのは、「資本主義のディスクールが排除した去勢、すなわちシニフィアンと享楽の両立不可能性をふたたび主体のなかに書き込むこと」(91ページ)にある。
このようにして、日本では翻訳すら十分でない後期ラカン、そして現代ラカン派の仕事を前半で丁寧に紹介したうえで、後半では現代的な課題について著者自身の問題意識を打ち出しているところが本書の意義と大きな魅力である。3部構成の「第Ⅰ部 理論」に続く「第Ⅱ部 臨床」では、DSM、うつ、羞恥の構造、自閉症などがラカン派理論から吟味される。「第Ⅲ部 政治」では、ヘイトスピーチ、集団的同一化における享楽の動員、否認とシニシズムといったアクチュアルな問題が緊張感をもって照射される。
最終章で著者は突然政治の現場に立ち、ジャーナリスティックな文体を挿入する。2015年8月30日に行われた安保法案に反対する国会議事堂前デモの最前線から振り返った著者が目にしたのは、「安倍やめろ」と書かれた黒と白の風船が浮遊している不吉なそれであった。
そして、安倍政権に死亡宣告を行うその喪章の周囲にひしめく「九条守れ」のプラカードにまざって、「脱原発」「反差別」「辺野古新基地建設反対」などを主張するプラカードが自然に共存していたことに私は目を奪われた。そう、「八・三〇」は、それまでの多様なイシューが「安倍やめろ」の喪章のもとでひとつになる瞬間を生み出したのである。さまざまな政治的要求から生み出された個別のシニフィアンが、政治的アイデンテティとしてのお互いの差異を強調するのではなく、むしろ等価性の連鎖によってつながり、「安倍辞めろ」という一つのイシューへと接合されていく過程が、そこには凝縮されていた。この意味で、「安倍やめろ」というシニフィアンは、ひとりの政治家をやめさせろ、という個別の要求ではなく、彼が象徴する政治における「安倍的なもの」の廃棄と、それに代わる政治的オルタナティヴを求める要求全てが帰着する潜在性そのもののシニフィアン、すなわち意味作用の全体が帰着する空虚なシニフィアンとなっていたのである。
(264ページ)
なるほど、これが「シニフィアンと享楽の両立不可能性をふたたび主体のなかに書き込むこと」の潜在なのか。私は不意をつかれた。なぜなら、まさに同じこの時、この場所で、私自身も振り返り同じ風景を目にしていたひとりだったのだから。
『享楽社会論 現代ラカン派の展開』
著者:松本卓也
発行:人文書院
発行年月:2018年3月10日
2018/01/02
今もっとも注目する松本卓也論考の概要。 ドゥルーズは「健康としての狂気」に導かれている。その導き手として真っ先に挙げられるのが、『意味の論理学』(1969年)におけるアントナン・アルトーとルイス・キャロルであろう。アルトーが統合失調症であるのに対し、キャロルを自閉症スペクトラム(アスペルガー症…
2017/02/12
『atプラス 31号 2017.2 【特集】他者の理解』では、編集部から依頼されたお題に対し、著者はそれが強いられているとアンチテーゼを掲げる。「他者の理解」こそ、共生社会にとって不可欠ではないのか。いったいどういうことか? 急増する発達障害、ASD(自閉スペクトラム症)は、最近になって急に障害者とされ…
2017/01/05
本書は、ドゥルーズとガタリやデリダといったポスト構造主義の思想家からすでに乗り越えられたとみなされる、哲学者で精神科医のラカンのテキストを読み直す試みとしてある。その核心点は「神経症と精神病の鑑別診断」である。ラカンは、フロイトの鑑別診断論を体系化しながら、神経症ではエディプスコンプレクスが…
2018/03/21
『アンチ・オイディプス』は、「欲望機械」「器官なき身体」「分裂分析」「接続と切断」といった言葉の発明をもとに、無意識論、欲望論、精神病理論、身体論、家族論、国家論、世界史論、資本論、記号論、権力論など様々な領域へ思考を横断していくところに最大の特徴がある。「あとがき」で翻訳者の宇野邦一は、…
2018/01/03
朝日新聞の興味深い新年特集記事「逃走闘争2018」で、『逃走論』(1984年)の著者浅田彰は述べている。重厚長大型から軽薄短小型への変化がある一方で、古い価値観やイデオロギーに固執する人々も相変わらず多いという当時の社会状況に対し、資本主義を半ば肯定しつつ、パラノ(偏執)的な鋳型を捨てて、スキゾ的(…
2016/11/20
ドゥルーズは認知症についてどう語っていたかという切り口は、認知症の母と共生する私にとって、あまりにも関心度の高過ぎる論考である。といってはみたものの、まず、私はドゥルーズを一冊たりとも読んだことがないことを白状しなければならない。次に、この論考は、引用されるドゥルーズの著作を読んでいないと認識が…
2016/11/19
「水平方向の精神病理学」とは、精神病理学者ビンスワンガーの学説による。彼によれば、私たちが生きる空間には、垂直方向と水平方向の二種類の方向性があるという。前者は「父」や「神」あるいは「理想」などを追い求め、自らを高みへ導くよう目指し、後者は世界の各地を見て回り視野を広げるようなベクトルを描く。通…
2018/02/18
ドゥルーズ=ガタリ連名による著作『アンチ・オイディプス』(1972年)、『千のプラトー』(1980年)、『哲学とは何か』(1991年)は、いずれも資本主義打倒のための書である。三作は利害の闘争から欲望の闘争へという戦略(ストラテジー)において共通するが、戦術(タクティクス)が各々で異なる。『アンチ・オイ…
2018/02/03
私が知る限り、柄谷行人がNAMについて公的な場でまとまった話をするのは、2002年のNAM解散後初めてではなかろうか。なぜ今になって語るかといえば、中国のアクティビストから『NAMの原理』中国語版を出したいという打診があり、NAMについて改めて考えることになったからだという。つまり、現実からの要請に対する応…
2016/10/28
2015年に国会議事堂の周囲で起こされた安保関連法案に反対するデモは、敗戦後70年間で最大のレベルだった。その中心となったSEALDsという学生たちの団体は、本書で論じてきた社会や政治への指向をもつ若者像を裏付ける。しかしその間安倍内閣の支持率はほとんど下がらず、デモは敗北だったといわざるをえない。 同…
2009/02/26
「『世界共和国へ』に関するノート」のためのメモ その29多くの未開社会には、世帯の上に上位集団である氏族社会が存在するため、世帯が基礎的な単位のようにみえる。だが、それはすでに上位集団によって変形されたものである。つまり、上位集団を作る互酬制の原理が世帯の中に浸透するということだ。これと似てい…
Posted by 24wacky at 20:05│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした