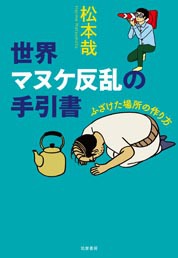2018年02月18日
『三つの革命 ドゥルーズ=ガタリの政治革命』佐藤嘉幸 廣瀬純

ドゥルーズ=ガタリ連名による著作『アンチ・オイディプス』(1972年)、『千のプラトー』(1980年)、『哲学とは何か』(1991年)は、いずれも資本主義打倒のための書である。三作は利害の闘争から欲望の闘争へという戦略(ストラテジー)において共通するが、戦術(タクティクス)が各々で異なる。『アンチ・オイディプス』ではプロレタリアによる階級闘争が、『千のプラトー』ではマイノリティによる公理闘争(諸権利や等価交換を求める闘争)が、そして『哲学とは何か』では動物(マイノリティ)を眼前にした人間(マジョリティ)による政治哲学(哲学の政治化)がその主戦場に選ばれる。
しかし、それら自体では資本主義打倒に不十分である。『アンチ・オイディプス』では、ブルジョワジーからプロレタリアートが割って出る「レーニン的切断」のなかで、さらにプロレタリアートから分裂者(スキゾ)が割って出る「切断の切断」が遂行され、階級外の「主体集団」が形成される必要がある。『千のプラトー』では、マイノリティがマジョリティあるいはその下部集合へと自らを再領土化しようとする公理闘争のなかで、「マイノリティ性への生成変化」を経なければならない。『哲学とは何か』では、「人間」としてのマジョリティは、「動物」あるいは「犠牲者」としてのマイノリティを眼前にして、人間であることの恥辱を感じ、「動物になる」過程に入らなければならない。
以下、ここでのマジョリティ/マイノリティという議論を、私の唯一の関心事である沖縄-ヤマトの二項対立構造に照らし合わせてみる。
『千のプラトー』で論じられるマイノリティ性への「生成変化」(devenir)は「・・・・になること」と言い換えることもできる。ドゥルーズ=ガタリは「黒人たちも黒人になる必要がある」と宣言したブラック・パンサー党を例に出す。それに倣い、女性たちも女性になる必要があり、ユダヤ人もユダヤ人になる必要があるとすれば、沖縄人も沖縄人になる必要がある、ということになる。
なぜ「生成変化」「・・・・になること」が必要かといえば、資本主義によって不等価交換の対象とされたマイノリティが公理闘争によって等価交換の対象としての承認を勝ち取ったとしても、それは資本主義を些かも脅かさないからだ。そこではマイノリティがマジョリティの中に下位集合として新たにカウントされるだけであり、また、新たな不等価交換の対象として別のマイノリティがカウントされるのを妨げることもできない。
ドゥルーズ=ガタリがユニークなのは、ここでマイノリティとマジョリティによる二重の運動が同時進行すると述べている点にある。『千のプラトー』からの長い孫引きになるが重要な箇所なのでご容赦願いたい。
しかしそうであるなら、ユダヤ人になること、ユダヤ人への生成変化は、ユダヤ人だけでなく非ユダヤ人にも必然的に関わることになるはずだ。女性になること、女性への生成変化だけでなく男性たちにも必然的に関わることになるはずだ。ある意味では、生成変化の主体は常に homme [人間=男性]だと言える。ただし homme がそのような主体となるのは、何らかのマイノリティ性への生成変化に入り、自らのメジャーな同一性から引き剥がされる限りにおいてのことだ。[…]他方で逆に、ユダヤ人たちがユダヤ人になり、女性たちが女性になり、子供たちが子供になり、黒人たちが黒人にならなければならないのは、マイノリティだけが生成変化を始動させる媒体となるからだが、ただし、そうしたアクティヴな媒体となるためにはマイノリティもまた、マジョリティとの関係において規定される集合であることをやめなければならない。従って、ユダヤ人への生成変化や女性への生成変化では、二重の運動が同時に進行すると言える。一方には、一つの項(主体)がマジョリティから逃れる運動があり、他方には、もう一つの項(媒体あるいは代行者エイジェント)がマイノリティから外れる運動がある。不可分かつ非対称的な生成変化のブロック、同盟ブロックが形成されるのだ。[…]女性は女性へと生成変化しなければならないが、この生成変化は人間全体が女性へと生成変化する中でなされなければならない。ユダヤ人はユダヤ人へと生成変化するが、それはあくまでも、非ユダヤ人のユダヤ人への生成変化の直中においてのことだ。マイノリティ性への生成変化は、共に脱領土化された一対の媒体と主体とをその要素とすることで初めて可能になる。生成変化の主体は、マジョリティにおいて脱領土化された変項としてのみ見出され、生成変化の媒体は、何らかのマイノリティにおいて脱領土化する変項としてのみ見出される。
(193〜194ページ)
マイノリティだけが生成変化を始動でき、マジョリティにはそれができないこと。マジョリティが主体であり、マイノリティは媒体であること。マイノリティは生成変化を始動できるが、それはマジョリティが「自らのメジャーな同一性から引き剥がされ」、マイノリティ性に入ることと不可分であること。よってマイノリティがマイノリティになることとマジョリティがマイノリティに入ることは同時進行で初めて成り立つこと。それが資本主義を下部から掘り崩す戦術であると『千のプラトー』の著者はいう。
なぜマイノリティ性への生成変化が資本主義を打倒する戦略となるのか。マイノリティ性へと生成変化することにより、マジョリティ/マイノリティという二項対立が解消され、万人がマイノリティ的になることで、一つの主体的集団が形成される。その限りにおいて、国家装置は機能不全に陥るからである。
付言すれば、ドゥルーズ=ガタリはマイノリティによる公理闘争を決して軽視してはいない。それは資本主義を掘り崩す運動として必然的である。だが、それだけでは足りない。公理闘争という「切断」をさらに「切断」する必要がある、そのための生成変化である。
沖縄による公理闘争とはいうまでもなく、押し付けれらた米軍基地に対するこれまでのあらゆる運動をさす。様々な市民運動、選挙、「県外移設」論、即時撤去論、独立論などなど。ドゥルーズ=ガタリを読む著者によれば、これらは皆資本主義を掘り崩す運動の経るべき道として不可欠であり必然的である。
しかし、同時に、(資本主義を打倒するためには)「切断の切断」が必要である。マイノリティ性への生成変化が。初めに、沖縄人が沖縄人になることが。次に、非沖縄人(「日本人」)が沖縄人になることが(沖縄の運動が「資本主義打倒をスローガンに掲げることはほとんどない。それはそれとして論じるべき問題だがここではひとまず措く)。
ところで、沖縄人が沖縄人になるとはどういうことか。「日本人」が沖縄人になるための「切断の切断」とはいかなる営為か。その問いと「結論」で展開される著者の問題意識は重なる。そこでは現在のこの国の闘いに論が展開され、福島と共に「琉球」が高橋哲哉批判も含みつつ論じられる。私がそれらを吟味するのは、これからドゥルーズ=ガタリの三作を読んでからになるだろう。
『三つの革命 ドゥルーズ=ガタリの政治革命』
著者:佐藤嘉幸 廣瀬純
発行:講談社選書メチエ
発行年月:2017年12月11日
2018/02/03
私が知る限り、柄谷行人がNAMについて公的な場でまとまった話をするのは、2002年のNAM解散後初めてではなかろうか。なぜ今になって語るかといえば、中国のアクティビストから『NAMの原理』中国語版を出したいという打診があり、NAMについて改めて考えることになったからだという。つまり、現実からの要請に対する応…
2017/09/18
「民主主義ってなんだ?」と問われる前に、柄谷行人はそれに答えていた。哲学に関するいくつかの通説を刺激的に覆し、この間探求を続けてきた資本と国家を超える交換様式と遊動性の理論に強引なまでにつなげるというやり方で。 デモクラシーの語源はdemos(大衆・民衆)とcracy(支配)、すなわち多数決原理に…
2017/02/03
「マヌケ」とは何だろう?本書を一読後、マヌケについての思想的意味を問うというマヌケなことを考えてみる。それくらい、本書にはマヌケという言葉が頻出する。しかし、その意味はあいまいである、当然ながら。とりあえず、グローバル資本主義の「敗者」が抵抗の意思を現そうとするその姿勢が、客観的態度からすれば…
2016/12/08
アズミ・ハルコ(蒼井優)を中心とする日常と愛菜(高畑充希)、ユキオ(太賀)、学(葉山奨之)の日常。後者の時制ではすでにアズミ・ハルコは行方不明になっているが、アズミ・ハルコの日常とのカットバックが繰り返される。それは回想という手法ではない。ユキオと学のグラフィティ・アートのユニット”キルロイ”…
2016/12/05
2015年にノーベル文学賞を受賞したスベトラーナ・アレクシエービッチは先日の来日講演の中で、福島第一原発事故の被災地を訪ねたことに触れ、「日本社会には抵抗の文化がないのはなぜか」と問うた(「日本には抵抗の文化がない」 福島訪問したノーベル賞作家が指摘 THE HUFFINGTON POST 2016年11月29日付)。本書…
2016/11/18
2012年10月、普天間基地への米軍機オスプレイ強行配備と阻止行動の敗北は、私自身にとって画期的な出来事としてある。沖縄オルタナティブメディア(OAM)として一連の顛末を現場中継し、目撃し、阻止行動に加わった。阻止行動は排除され、翌日オスプレイは空高く飛来し、沖縄の地に着地した。その時、私は自分…
2016/03/17
このような岡本の倫理からすれば、高橋氏の「県外移設」論に対して、その姿勢は本土の知識人として美しいが、「沖縄に住む人間が、県外移設に反対することは、みずからの担っている過酷な状況を拒否するとともに〜本土側からの県外移設論に同調するわけにはいかないのだ」といえる。 ここで岡本は「沖縄に住むぼく…
2016/03/16
「自分の生命を守る」ことは、その人の経験によって起こされる結果がどのようなものであれ、それに左右されずに従うべき法則である。対照的な「私」と比べてみると理解しやすいだろう。「痛くないだろうか。逮捕されたらどうしよう…」と「私」が恐怖心に支配されるのは「心の傾き」からそうするのであって、それは義務に…
2016/03/15
「『沖縄の米軍基地』を読む」への応答(上)(2015年11月24日付、沖縄タイムス紙文化面)で高橋哲哉氏から拙稿へご指摘いただいた点について応答したい。 はじめに、「基地を引き取れ」だけではない「沖縄からの問いかけ」を指すものとして、「殺すな!」「殺されるな!」という、誰だかわからない他者から…
Posted by 24wacky at 10:10│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした