2017年01月18日
『漱石を読みなおす』小森陽一著の「猫」について
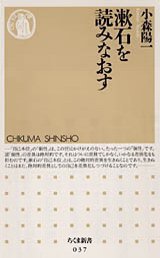
岩波書店の全集刊行などで漱石リバイバルがあった1990年代(今の話ではなく)、雑誌『漱石研究』の編集など、著者はその中心にいた。本書『漱石を読みなおす』は新書版ではあるが、独自の読みをフル稼働させている。当時その仕事には大きな刺激を受けたものだ。さて、小森陽一は『猫』をどう読んでいるか。
小森は「引き裂かれる世界」ということをいっている。人間と猫の世界の二重性に引き裂かれるという意味である。さらにそれは現実と虚構、写生文家と大学教師、日本文学の創作者と英文学の研究者、日本語と英語、明治日本と大英帝国、未開と文明といった多様な二項対立関係を自己増殖させていく、と。
人間の世界と猫の世界は価値体系が異なり、閉じており、その世界は決して開かない、と小森は述べる。それは「名前はまだ無い」からである、と。どういうことか。
小森によれば、「名前」をつけることとは、その対象を言葉に置き換え、認識することのできる指示対象にすることである。「名前」をつけないということは、猫を人間世界に回収することを拒み、人間世界に対する猫の他者性を保持し続けることになり、結果として猫の自由が確保されることにもなる。だからそれは《ひとつの世界を二つに分裂させた領域を、いわば相互に閉じたまま、その異質性と差異性を保持したまま交通させることを可能にしている》(11ページ)といえる。
さらに小森らしい「推理」は続く。「吾輩は漱石である」という。「吾輩」は捨て猫だが、漱石(本名夏目金之助)こそ捨て子であったのだから、と。そして、恥かきっ子としれ生まれ養子に出されるという伝記的事実とテキストが照らし合わされ、その信ぴょう性が裏づけられる。
だが、ここで数多ある文芸批評同様に終わらないところが小森の真骨頂である。
その意味で、『吾輩は猫である』を「吾輩は金之助である」に変換すると、究極の「私小説」になる、ということもできると思います。しかし、いわゆる「私小説」のように、自分のこととして告白してしまえば、自分を里子に出し、後に再び養子に出した両親を恨む言説になりますし、子供の頃のことに、中年になってもこだわりつづけている自分の姿もでてきてしまいます。「私は両親に捨てられた捨て子だ!」という告白は、話題としては悲劇ですが、それを読者に向かって告白する行為の中には、そうすることで同情してもらおうという下心も透けて見えてしまいます。告白するのは、あくまで「猫」なのです。「猫」の世界では、捨て猫の話しはよくあることです。とりたてて悲劇にはなりません(もちろん、人間の側に立ってのことですが)。捨て子であった自分について、捨て猫のこととして語る。そうすることによって、心の中のわだかまりを自己治療していく。そこに「金之助」が「漱石」という名で、「金之助」について「猫」のこととして書くという、幾重にも屈折した回路の意味があったのではないでしょうか。
(20ページ)
捨て子であった自分の心のわだかまりを自己治療する。そのために猫の他者性は保持されなければならない。人間の世界と猫の世界は引き裂かれていなければならない。この自己治療の発見は、《写生文に現れる語り手は主人公や登場人物の自我を柔らかく包み込む超自我である》という島田雅彦の見解の別の表現といえる。
『漱石を読みなおす』
著者:小森陽一
発行:筑摩書房
発行年月:1995年6月20日
2017/01/17
年末年始から現在まで坂口安吾について考え、読み漁っている。それに関連して、国民的作家のデビュー作について考えたいことがあり、久方ぶりに本書を紐解く。 『吾輩は猫である』誕生の以下の経緯は有名である。当時本人認めるところの「神経衰弱にして兼狂人のよしなり」であった漱石を見かね、俳人仲間の高…
2016/12/31
坂口安吾といえば、「戦争に負けたから堕ちるのではないのだ。人間だから堕ちるのであり、生きてゐるから堕ちるだけだ。」というエッセイ『堕落論』が著名であるように、戦争体験を独特なデカダンスで表現した「無頼派」の作家として有名である。『白痴』『桜の森の満開の下』などが評価が高く、その他にも歴史小説…
Posted by 24wacky at 19:34│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした

















書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。