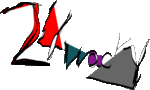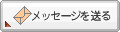2016年08月20日
『物語消滅論 キャラクター化する「私」、イデオロギー化する「物語」』その2

第二章 キャラクターとしての「私」
近代的自我や近代的個人という私たちが共有している「現実」は、実は明治30年代後半に急速に形成されていったものだといってよい。すなわち、「私」であり「心」であり「歴史」と「地勢図」といった要素の組み合わせのことである。この「現実」の背後には、近代を支配してきた進化論的な考え方がある。神様ではなく進化という内在的な因果律が歴史を作っていくという。それは西洋にとって衝撃的だったわけだが、日本の近代化はその衝撃をとっぱらって無邪気に受容していったのが特徴といえる。そのため、人々はこの「私」を記述することに苦労する。
そもそも近代小説とはそういうものである。夏目漱石の『夢十夜」は、曖昧で不定形な「私」を執筆時期からちょうど百年前という時間軸のなかに配置していく。柳田國男の民俗学は自然主義的手法を「風景」に向けながら、「歴史」と「地勢図」の交差する「現在」を固定しようとした。
田山花袋の『蒲団』で明らかになったのは、「私」というものが初めからキャラクターとして作られたことである。私小説の嚆矢とされる『蒲団』では、花袋の同居中の女弟子からわざわざ送られてくる手紙が繰り返し引用される。その手紙は言文一致体で書かれ一人称である「私」が主語となっている。花袋は奔放な女弟子のテキストに心惹かれるが、彼女がいざ現実の世界で奔放に振る舞い「私」を生き始めると逆ギレし、彼女を田舎に返してしまう。田舎から送られてきた彼女の詫状は候文で記されていたというのが結末となっている。つまり、この「私」は文体によってスイッチ可能なキャラクターとしてある。
花袋はなぜ彼女を田舎に追い返したのか、言い換えればなぜ女弟子の「私」を抹殺しようとしたのか。花袋においては、作者だけが「私」になることができる特権を持つのであり、読者としての女弟子に簡単に「私」になられては困るからだ。前述した通りそもそも「私」とは、あくまで近代に構築されたいくつかの書式からなる「現実感」とセットで成立するものであり、そうである以上それは「本当の私」というよりは「置き換え可能のキャラクター」なのである。私小説を開発した花袋はそのことが露わになることを直感的に不快に感じたのではないか。
ところで、人間のパーソナリティーを与えられた設定からなるものとして捉え、それをキャラクターと呼ぶ習慣は、アメリカでは70年代から80年代、日本でもやや遅れて、しかし急速に認知されていった。さらに最近では、性別、年齢、目の色、髪の毛、性格など、キャラクターを構成する特徴を「属性」と呼ぶことがアニメやゲームの世界では習わしとしてある。そこから、キャラクターとは「属性」の順列組み合わせだという感覚が違和感なく受け入れられている。著者(や私)はそのことに違和感がある。
このことを大局的にいうと、進化論的世界から情報論的世界への転換がなされているということになる。進化論的世界では社会設計者としての「私」、あるいは「固有の作者」が求められた。それに比べ情報論的世界では「固有の作者」は成立しにくい。LINUXのように全開放型なモデルを思い浮かばればよい。
著者は自身の立つ基盤を前者にあると前置きした上で、ネットの外側での近代的自我の建て直しが必要であることを強調する。かつての佐世保の小学生の事件を例にとり、アバターというキャラクター同士で喧嘩していた女の子が相手を殺してしまったのは、アバターの背後にいる「私」が、実は古典的で近代的な自我であり、それがむき出しで無防備な状態であったことに起因すると注意を促す。著者にとってサブカルチャーとは、クッション的なもの、不確定な「私」の一時的な避難所と位置づけられる。故に文学をサブカルチャーが代行するのはリスキーであり、抑止としての受け皿として機能する近代的言説は、それに代わる新しいなにかが生まれるまでは当面必要であると。
『物語消滅論 キャラクター化する「私」、イデオロギー化する「物語」』
著者:大塚英志
発行所:角川書店
発行:2004年10月10日
Posted by 24wacky at 19:37│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした