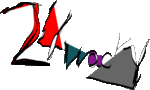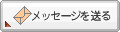2016年10月29日
第12章 「呼びかけ」と〈呼びかけ〉 『可能なる革命』概要 その13

ハーマン・メルヴィルの中編小説『バートルビー━━ウォール街の物語』(1853年)は、資本主義の中心地となる19世紀のウォール街において、語り手の弁護士によって記述される、書記バートルビーの奇妙な生態についての物語である。弁護士が口述や筆記の仕事を頼むと、バートルビーは「私はそれをしないほうがいいと思います」("I would prefer not to...")と言ってあっさりと拒否する。彼はただそういうだけで拒否の理由を言わない。
マックス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』では、ルター訳聖書で、パウロの「召命 klesis」という語にドイツ語の「Beruf(英訳 calling)」が充てられ、さらにこの語が「職業」という意味を獲得したと述べられている。神からの呼びかけに世俗的な職業という意味を加える(つまり職業は天職であるという解釈)ところに、資本主義の精神の原点がある、とヴェーバーは考える。このことは、資本主義のシステムでは、職業を遂行することにおいて、あたかも神からの呼びかけへの応答であるかのように、つまり適切な水準の自己利益を超えた過剰な使命を実行するかのように振舞う者が生き延びる、というように捉えることができる。
ヴェーバーのベルーフに対応するマルクスの概念に「階級」がある。マルクスによれば、「階級 Klasse」は「身分 Stand」ではない。たとえば、貴族という身分は永遠に貴族のままであるのに対し、階級が意味するのは、個人と階級の間には本質的なつながりがないということだ。よって、ブルジョワはブルジョワジーになる。
資本主義において、人は呼びかけられる。しかし、バートルビーの無為はそれを拒否する。《ここで、われわれは、二種類の呼びかけを区別しなくてはならない。一方に、外部の超越的な実体━━具体的であったり抽象的であったりする実体━━に帰せられる「呼びかけ」がある。他方に、行動する者自身の外部に根拠をもたない〈呼びかけ〉がある。〈呼びかけ〉を聞くためには、「呼びかけ」に対して耳を塞がなくてはならない。これがバートルビーである』(383ページ)。
アラン・バディウの『主体の理論』(1982年)は〈存在〉と〈出来事〉の二元論をベースにしている。〈存在〉とは、物事の日常的な秩序のことであり、〈出来事〉とは、日常の秩序に断絶や歪みをもたらし、日常的には隠れていた〈真実〉を露呈させる瞬間である。
革命とは、〈出来事〉の衝撃を制度化し、永続化することである。すると、〈出来事〉の衝撃こそ〈呼びかけ〉ではないのか。〈出来事〉は、それ自体として客観的に存在しない。〈出来事〉は、それを体験する主体との相関でしか存在しない。〈出来事〉は、それを〈出来事〉として認知する者にとってしか存在しない。
〈出来事〉は、経験の前提となっていたことを、つまり超越論的な条件を偶有化する。その感情的な反応が〈不安〉である。
だからこそ、こういうことができる。不安こそ、〈呼びかけ〉を聞いたということにほかならない、と。誰もが〈呼びかけ〉を聞いてしまっている。不安は普遍的である。
『バートルビー』では、上司の命令に部下は従うという前提がある中で、「命じられた仕事をしないことができる」という世界が突如開示された。そのことに対して、人びとは不安を感じる。
〈呼びかけ〉を聞き、不安を感じ、なおかつ、不安が勇気に引き継がれたとき、「革命」と見なしうる大きな変化をもたらす決定的な行動が選択される。だがそれは必ず起きるわけではない。3・11で日本人の多くは不安を覚えたにもかかわらず〈呼びかけ〉が聞こえないふりをしたのだから。
『可能なる革命』
著者:大澤真幸
発行所:太田出版
発行:2016年10月9日
Posted by 24wacky at 09:37│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした