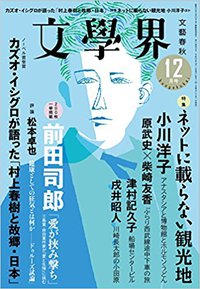2019年05月12日
『ザッヘル=マゾッホ紹介 冷淡なものと残酷なもの』ジル・ドゥルーズ
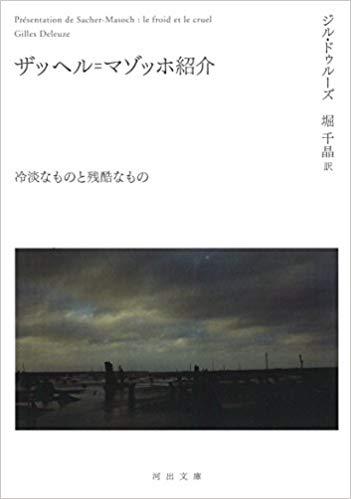
サド=マゾヒズムの一体性、相互補完性をドゥルーズは認めない、倒錯における主体(人物)と要素(本質)とを区別することによって。マゾヒストが幸運にもサディストに遭遇できると信じるのは誤りである!と、きっぱり言い切る。
拷問者の女性がいるとする。この女性は、実はサディストではない。この女性は《マゾヒズムに本質的に帰属していながら、マゾヒズムの主体性を実現することはなく、マゾヒズム以外のものではありえない展望のなかで、「苦痛を与える」要素を体現していることがわかるだろう。だからこそマゾッホの主人公たち、それにマゾッホ自身は、発見するのが困難な女性のある種の「本質」を探し求めることになるのだ。主体としてのマゾヒストは、マゾヒズムのある種の「本質」を必要としているのであり、それはじぶん自身も主体的なマゾヒズムを断念する女性の本質のなかで実現される。主体としてのマゾヒストは、サディスト的な別の主体を必要としているわけでは決してないのだ》(63〜64ページ)。
マゾッホが描く女性には三つの類型がある。第一は、ギリシャ人女性、娼婦(ヘタイラ)、アフロディーテ、秩序壊乱を生みだす女性。他方の極にある第三の類型はサディストである。この二つの主題は、振り子の振幅のように、そのあいだでマゾヒズムの理想が動きまわり、宙吊りにされる両極をなす。この両極は、マゾヒズムがまだその戯れを開始していない極限と、マゾヒズムがその存在理由を失う極限なのである。では理想的な第二の極限とは。それは冷淡ー母性的ー厳格であり、冷酷ー感情的ー残酷という三位一体で現される。《マゾッホ的な理想の機能とは、氷の冷たさのなかで、冷淡さによって感情性を勝利させる点にあるのだ。冷淡さが、異教的な官能性を抑圧するとともに、サド的な官能性からも距離を取るといえるだろう。官能性は否認され、もはや官能性として存在することはない。だからこそマゾッホは「性愛なき」新たな人間の生誕を告知するのである。マゾヒズムの冷淡さとは氷点であり、変身の点である(弁証法)》(79ページ)。
このあたりは、ドゥルーズの「変態」「生成」といった概念との類似を想起させる。何れにせよ、ドゥルーズにおいて、サディズムとマゾヒズムは反対物ではない。両者のあいだには、深遠な非対称がある。
マゾッホの小説的要素として、ドゥルーズは「期待=待機」という概念を美的な側面として提示する。造形芸術において、しぐさや姿勢を宙吊りにすることで、その主題を永遠化するという。振り下ろされることのない乗馬用の鞭、あらわにひらかれることのない毛皮、踏み下ろされつづける踵などなど。ただし、それは時間の形式として理解する必要がある。《マゾヒストとは、期待=待機を純粋状態で生きる者にほかならない。純粋な期待=待機の特性とは、ふたつの同時的な流れへとおのれを二重化することにある。その一方の流れが表象するのは、待望のものであり、本質的に遅れてやって来るもの、つねに遅延し、つねに先延ばしにされるものである。他方の流れが表象するのは、予期される何かであり、待望のものの到来を早めうる唯一のものである。このふたつの流れをともなうかくなる時間の形式、かくなる時間のリズムがまさに、快ー苦の一種の結合物によって満たされるのは、必然的な帰結である。苦痛が予期されるものを実現する一方で、同時に、快が待望のものを実現するのだ。マゾヒストは本質的に遅れてやって来るなにかとして快を待ち望み、最終的に快の到来を(肉体的にも精神的にも)可能にする条件として苦痛を予期する。それゆえマゾヒストは、それじたい待ち望まれるものである苦痛が、快を可能にするまでに必要な時間のあいだ、ずっと快を先送りにするのである。ここでマゾヒストの不安は、快を無限に待ち望みながら、しかし同時に苦痛を強烈に予期してもいるという、二重の規定を帯びる》(109〜110ページ)。ここでマゾッホは、苦痛のうちに快を見いだすというマゾヒズムに対する俗な見方を否定している。
さらに、マゾッホの小説的要素には、法的な側面として、契約と服従のモデルがある。それを契約を否定し制度を擁護したサドとの比較として論じる。
『ザッヘル=マゾッホ紹介 冷淡なものと残酷なもの』
著者:ジル・ドゥルーズ
訳者:堀千晶
発行:河出文庫
発行年月:2018年1月20日
2018/05/20
冒頭からリゾームという言葉のイメージの噴出に息が切れそうになる。リゾームとは樹木やその根とは違い点と点を連結する線からなる。それは極限として逃走線や脱領土化線となる。樹木は血統であるが、リゾームは同盟である。リゾームは多様体である。リゾームは生成変化である。リゾームとは定住性ではなく遊牧性で…
2018/03/21
『アンチ・オイディプス』は、「欲望機械」「器官なき身体」「分裂分析」「接続と切断」といった言葉の発明をもとに、無意識論、欲望論、精神病理論、身体論、家族論、国家論、世界史論、資本論、記号論、権力論など様々な領域へ思考を横断していくところに最大の特徴がある。「あとがき」で翻訳者の宇野邦一は、…
2018/02/18
ドゥルーズ=ガタリ連名による著作『アンチ・オイディプス』(1972年)、『千のプラトー』(1980年)、『哲学とは何か』(1991年)は、いずれも資本主義打倒のための書である。三作は利害の闘争から欲望の闘争へという戦略(ストラテジー)において共通するが、戦術(タクティクス)が各々で異なる。『アンチ・オイ…
2018/01/02
今もっとも注目する松本卓也論考の概要。 ドゥルーズは「健康としての狂気」に導かれている。その導き手として真っ先に挙げられるのが、『意味の論理学』(1969年)におけるアントナン・アルトーとルイス・キャロルであろう。アルトーが統合失調症であるのに対し、キャロルを自閉症スペクトラム(アスペルガー症…
Posted by 24wacky at 09:03│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした