2019年06月29日
『ナジャ』アンドレ・ブルトン
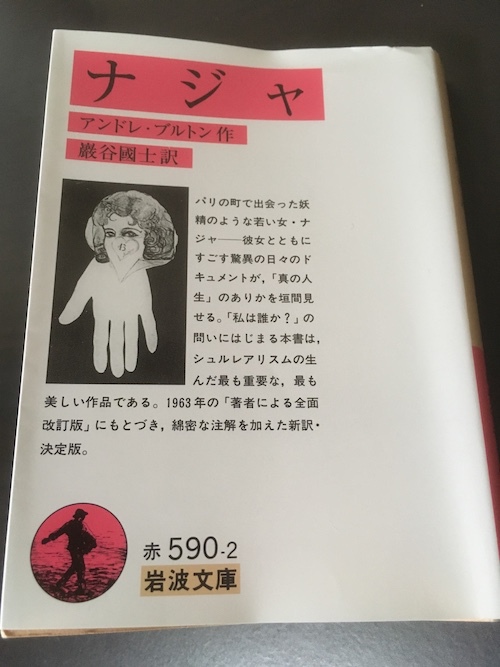
約30年ぶりに再読する。前回読んだ白水社版は原著が1928年版の訳、今回の岩波文庫版は1963年の全面改訂版ということで、著者ブルトンも30年以上経って、この「ドキュメント」を大幅に加筆訂正した(その経緯は末尾で双方の翻訳者の巖谷國士によって解説されている)という偶然に意味を見出したくなるが、「私は誰か?」で始まるシュールレアリスムの代表作の読後としては避けられないか。
それにしても『ナジャ』を読むことの魅力とはなんだろう。時間が経っての再読にも関わらず、今回も初めて読むような興奮を与えられたというのに、それを言語化できないのは歯痒いばかり。巖谷國士いうところの「文学的完成など眼中になく、人生と連続する言語表現の生成」を、読む「私」も追いかける体験のザワザワ感、などといってみるが、陳腐このうえない。
またもや巖谷國士の解説に依るが、「私は誰か?」という問いは、同時に「私は誰を追っているか?」とも読める、「追うこと」は『ナジャ』の主題の一つだという。さらに続く、その問いへの応答、「私が誰と「つきあっている」かを知りさえすればいい」の「つきあう」は、幽霊などが「つきまとう」の意にもなることから、「他者との関係から割り出されるべき未知の「私」が、そして幽霊のように他所や前世に根をおろしているかもしれない未知の「私」が想定されてゆく」。
パリの街角で出逢うナジャとの「つきあい」、そこから派生する様々な他者との「つきあい」と挿入される写真の断片。これらが現在形の動詞で記述されていく。それを読む行為自体がその現在性にいつの間にか加担していく。長い月日が経過した後のブルトンの修正も、きっと生々しい体験だったことだろう。
『ナジャ』
著者:アンドレ・ブルトン
訳者:巖谷國士
発行:岩波文庫
発行年月:2003年7月16日
2019/06/16
「第1章 神経エコノミーの誕生」では「視ることそのものを視る」というあり得ない行為について論じられる。それに似た体験を、アーティストの三上晴子の作品《モレキュラー・インフォマティクス──視線のモルフォロジー》(1996年)を例にとる。同作品では、現在でいえばVRグラスのような大型のゴーグルを体験者が…
2017/01/20
英文科の大学生だった頃の思い出。3年になるといよいよ本格的に専門科目を学ぶようになり、同時に、同じ文学部内で他の学科の単位も限定的に履修できるというシステムがあった。それを利用して履修した仏文科の「フランス文化」という単位は、シュールレアリズムの専門家であり、あのブルトンの『ナジャ』などの翻…
Posted by 24wacky at 09:54│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした

















書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。