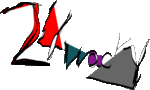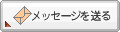2019年10月19日
『チャタレー夫人の恋人』D・H・ロレンス

第一次世界大戦後のイギリス中部を舞台に、上流階級の令夫人コニーと森番メラーズの激しい肉体の結びつきを描き、資本主義の浸食による疎外化に抗い、性における人間関係の根源的な回復の可能性を描いた1928年の作品。
上流社会の女性と野性味あふれる下層社会の男の道ならぬ性愛というモチーフは、その後数多の文学作品や映画などで再生産される。しかし、本書で訳者がわざわざ「まえがき」で詳しく紹介しているように、コニーの属する階級は貴族ではなく、戦争で下半身不随となった夫のクリフォードが貴族であるのとは対称的に、その結婚には階級差が背景にあり、他方でメラーズはといえば、服を脱げば色白で細身の身体、坑夫の経験から咳込む病弱さを持ち、さらには教養がある。つまり、無学な野蛮人ではない。
このような微細な差異を人物造形として固めた上で、なおかつ惹かれ合う男女には、お互いの階層を区別する自意識が容易には拭えない。特に、下層に生きるメラーズにおいては。そのぎくしゃくした互いの思いと言葉のすれ違いの過程が、三人称で見事に描かれる。
だからこそ、二人がお互いの属性を一枚、また一枚と脱ぎ捨てていく様が読者を引き込まずにはいない。コニーが「女になる」につれ、メラーズもまた「女になる」。ドゥルーズ=ガタリの「生成変化」を模倣するように。その過程を経ての最終章のメラーズの手紙における力強い人間宣言は、いささか唐突だが感動的である。
30年以上前に読んだ新潮文庫の伊藤整訳は「チャタレー裁判」の影響から「猥褻」箇所が削除された版であった。歴史を越えて復元された「性描写」は生成変化のそれとして読み直すことで刷新される。
『チャタレー夫人の恋人』
著者:D・H・ロレンス
訳者:木村政則
発行:光文社古典新訳文庫
発行年月:2014年9月20日
2018/05/20
冒頭からリゾームという言葉のイメージの噴出に息が切れそうになる。リゾームとは樹木やその根とは違い点と点を連結する線からなる。それは極限として逃走線や脱領土化線となる。樹木は血統であるが、リゾームは同盟である。リゾームは多様体である。リゾームは生成変化である。リゾームとは定住性ではなく遊牧性で…
2018/02/18
ドゥルーズ=ガタリ連名による著作『アンチ・オイディプス』(1972年)、『千のプラトー』(1980年)、『哲学とは何か』(1991年)は、いずれも資本主義打倒のための書である。三作は利害の闘争から欲望の闘争へという戦略(ストラテジー)において共通するが、戦術(タクティクス)が各々で異なる。『アンチ・オイ…
Posted by 24wacky at 08:08│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした