2010年02月15日
沖縄アソシエーショニズムへ 43
座間味村の地域自治組織
2009年度「自治講座:私たちが創る、沖縄の自治」最終報告書は、沖縄自治研究会2009年度後期の活動を活字化したものである。これに先立ち、各界からの専門家を招いた前期の講座をまとめたものとして、「自治講座:私たちが創る、沖縄の自治」2009年度報告記録も発行されている(私もテープ起こしの作業で関わらせていただいた)。
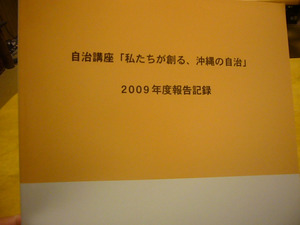
2009年度「自治講座:私たちが創る、沖縄の自治」最終報告書は、沖縄自治研究会2009年度後期の活動を活字化したものである。これに先立ち、各界からの専門家を招いた前期の講座をまとめたものとして、「自治講座:私たちが創る、沖縄の自治」2009年度報告記録も発行されている(私もテープ起こしの作業で関わらせていただいた)。
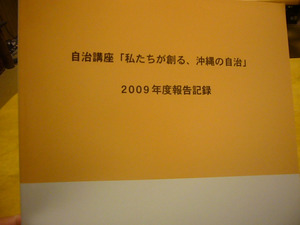
今回は、この中でも特に評判が高かったとされる第3回「沖縄の自治・地域づくりの現状と課題~沖縄の自治の今を見つめる~」の一つ目の講演「①小さな自治体の現状と課題~沖縄の離島自治体の事例~」を取り上げる。それはこれまで論じてきた沖縄の地域自治組織について、具体的な事例として相応しいのみならず、その構造的問題が分かり易く概説されているからだ。
報告者の幸地東氏は福祉行政が専門の優秀な沖縄県庁職員であり、2007年度から2年間座間味村政策調整監を務められた(政策調整監とは副村長職のない座間味村では、実質村長の次に位置するナンバー2のポジションである)。いわば共同体に派遣された余所者の視点、かつ地域自治理論に精通したエリート行政マンとしての立場からの発言は、情報量が少ない離島の実情に関心のある参加者にとって新鮮なものであっただろうし、個人的にも座間味について多少関わりのある者として興味深かった。
幸地氏の話は、共同体に関する話が一つと、行政サービスと社会関係資本に関する話とに大きく分けられる。まずは共同体に関して。
《座間味は一つではない》と幸地氏はいう。座間味村は、座間味島、阿嘉島、慶留島の三島から成り、それぞれに小中学校、港がある。さらに座間味島には座間味、阿真、阿佐という三つの字があり、これもそれぞれ港がある。《みんなバラバラなのですね。そういうふうにして別個の生活圏ができていますので、島以外にも字も自律的な基本単位になっているだろうと考えています》。
その5字の中で人口の多い字座間味に中央集権化する構造がある。それにより座間味村の中で《微妙な感情のバランスがある》と幸地氏は指摘する。その例として、診療所医師が辞職したときのエピソードを紹介する。
役場としては、もう一つの診療所がある阿嘉に行ってもらうことを考え、そのことを阿嘉住民に説明しに行ったときのこと。説明が終わると即座に「絶対だめです」という意見が出た。なぜだめかというと、座間味住民が阿嘉診療所で医療を受けられるということになれば、財政事情が厳しい県としては、阿嘉診療所を閉鎖し、座間味診療所一つに統合するはずであり、それは受け入れられないという。
この二つの話が意味することは明白で、もともと各共同体はバラバラであり一つにまとまっているわけではない。そしてお互い緊張関係にある。
その共同体がなにによってまとまるかというと、座間味の場合、御願所を中心とした伝統的な祭祀に重きを置く。しかしながら、自分たちで地域の課題を解決しようという話し合いにはならないという。島袋純が挙げた地域自治組織の三つの機能の第一が強く、第三は弱いということだ。質疑応答の中で幸地氏は、伝統行事はやってもらって良いが、行政機能も必要であるとし、両者の棲み分けをする必要性を語っている。
「自分たちのことは自分たちで決める」行政機能を高めようと、この後幸地氏は入島税導入がテーマの住民会議を仕掛ける。しかし、その動機は他にもあった。
ここで幸地氏は、会場の参加者に行政職員が多いということも手伝ってか、役人としての本音を正直に語っている。間違っても座間味村民を前にいえないことを。そのことの是非はともかく、そもそも住民の間にはガス抜きしなくてはならない何があったのか?
つづく
報告者の幸地東氏は福祉行政が専門の優秀な沖縄県庁職員であり、2007年度から2年間座間味村政策調整監を務められた(政策調整監とは副村長職のない座間味村では、実質村長の次に位置するナンバー2のポジションである)。いわば共同体に派遣された余所者の視点、かつ地域自治理論に精通したエリート行政マンとしての立場からの発言は、情報量が少ない離島の実情に関心のある参加者にとって新鮮なものであっただろうし、個人的にも座間味について多少関わりのある者として興味深かった。
幸地氏の話は、共同体に関する話が一つと、行政サービスと社会関係資本に関する話とに大きく分けられる。まずは共同体に関して。
《座間味は一つではない》と幸地氏はいう。座間味村は、座間味島、阿嘉島、慶留島の三島から成り、それぞれに小中学校、港がある。さらに座間味島には座間味、阿真、阿佐という三つの字があり、これもそれぞれ港がある。《みんなバラバラなのですね。そういうふうにして別個の生活圏ができていますので、島以外にも字も自律的な基本単位になっているだろうと考えています》。
その5字の中で人口の多い字座間味に中央集権化する構造がある。それにより座間味村の中で《微妙な感情のバランスがある》と幸地氏は指摘する。その例として、診療所医師が辞職したときのエピソードを紹介する。
役場としては、もう一つの診療所がある阿嘉に行ってもらうことを考え、そのことを阿嘉住民に説明しに行ったときのこと。説明が終わると即座に「絶対だめです」という意見が出た。なぜだめかというと、座間味住民が阿嘉診療所で医療を受けられるということになれば、財政事情が厳しい県としては、阿嘉診療所を閉鎖し、座間味診療所一つに統合するはずであり、それは受け入れられないという。
この二つの話が意味することは明白で、もともと各共同体はバラバラであり一つにまとまっているわけではない。そしてお互い緊張関係にある。
その共同体がなにによってまとまるかというと、座間味の場合、御願所を中心とした伝統的な祭祀に重きを置く。しかしながら、自分たちで地域の課題を解決しようという話し合いにはならないという。島袋純が挙げた地域自治組織の三つの機能の第一が強く、第三は弱いということだ。質疑応答の中で幸地氏は、伝統行事はやってもらって良いが、行政機能も必要であるとし、両者の棲み分けをする必要性を語っている。
「自分たちのことは自分たちで決める」行政機能を高めようと、この後幸地氏は入島税導入がテーマの住民会議を仕掛ける。しかし、その動機は他にもあった。
本音ベースでいうと、これで住民の皆さんのガス抜きができればいいのではないか、という気持ちが、100%ではないが、もちろんありました。そうすれば住民のみなさまに説明したことになりますから、その結果として大丈夫だろうな、という気持ちもあった。
ここで幸地氏は、会場の参加者に行政職員が多いということも手伝ってか、役人としての本音を正直に語っている。間違っても座間味村民を前にいえないことを。そのことの是非はともかく、そもそも住民の間にはガス抜きしなくてはならない何があったのか?
つづく
Posted by 24wacky at 20:47│Comments(0)
│アソシエーション














