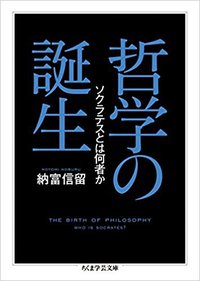2018年12月18日
『考えるとはどういうことか 0歳から100歳までの哲学入門』梶谷真司

みんなで集まって話し合う。一般に、それらは会議、会合、ミーティング、懇談会、ワークショップなどと呼ばれる。本書で扱われるのは「哲学対話」という集いの場である。それはいわゆる教養としての「哲学」について議論する場ではない。目的があるとすれば、「考えることで自由になる」である。「考えることで自由になる」とは、著者の体験によると、対話が哲学的になった瞬間、体が軽くなってふっと浮く感覚なのだそうだ。それが「自由」だ、と。
この体験をして改めて思い返されるのは、私たちがいかに語る自由を奪われてきたか、ということである。それはまず学校教育でなされると、著者はいう。自由に考えるためには「何を言ってもいい」はずであるが、学校では、正しいこと、良いこと、先生の意に沿うことしか言ってはならず、しかもその基準は学校側にしかない。そして同じことは、社会に出てからも職場などで続く。いつしかわれわれは、その場にふさわしいこと、許容されそうなことだけを言うようになる。これに対し「哲学対話」のルールでは、「何を言ってもいい」。そのために「人の言うことに対して否定的な態度を取らない」というもう一つのルールが併用される。
「哲学対話」で重要な概念は、考えることで得られる「自由」である。それは「問う・考える・語る・聞く」というプロセスを経ることで、参加者がお互いを鏡にして、物事を自分から切り離して考えるようになることをさす。それが「体が軽くなってふっと浮く」という体感として触知される。しかも、他者と共に自由になることが重要である。
四つのプロセスのなかで、もっとも大事なのが「問う」ことである。「考える」とは、まず始めに「問う」ことなのだから。とはいえ、私たちは「問う」ことに慣れていない。学校教育では、教科書のなかに「問い」がたくさんあるが、それらは「考えさせられる問い」であって、自分が望んだ「問い」ではない。「問う」とは、自分たちが問いたいことを問うことである。自分で見つけた「問い」は、考えるのも楽しいし、ついつい考えてしまう。
なお、「哲学対話」は、ファシリテーターがリードするワークショップ形式との共通点と相違点がある。進行役(ファシリテーター)がいることや、「人の言うことに対して否定的な態度を取らない」などは両者に共通するが、「哲学対話」では、ホワイトボードの効用に留保がつく。ホワイトボード使用は、発言者とその意見を切り離すことで、意見の表明が相手への批判として捉えられる弊害を避けることができる(「外在化』)。一方「哲学対話」では、ホワイトボードに気を取られ、話されている内容に集中できなくなるのを避けることが優先される。このあたりはやってみないとわからない気がする。
ここまでくれば、あとは〈第4章 哲学対話の実践〉をたよりに、具体的な手順をつかみ、実践を重ねるのみである。さっそくやってみたい。
『考えるとはどういうことか 0歳から100歳までの哲学入門』
著者:梶谷真司
発行:幻冬舎新書
発行年月:2018年9月30日
2017/08/31
「哲学」とはなんだろうか。わたしは「哲学」のなにが気になって本書を手に取るのか。「第1章 生の逆転─『ゴルギアス』─」末尾で、著者は早くもこの答えに応答している。「哲学」とは「生き方を言論で吟味すること」である、と。師・ソクラテスを登場させた数々の対話篇というテクストは、登場人物たちと共に、読…
2017/08/20
ヨーロッパ哲学には3種類あることから本書は始まる。第一に、ソクラテスによる「問答」の哲学、「知の吟味」である。相互に相手の意見を批判的に検討する「討議」という伝統として現在まで伝わる。第二に、「上下に秩序づけられた二世界説」と「真理の探求」ないし「知の探求」である。ピュタゴラス、パルメニデス、…
2017/08/19
わたし(たち)が知っているソクラテスとはプラトンの著作に登場する「哲学者」のイメージとしてある。わたしはソクラテスに関心があるが、その関心の根拠を知りたく本書を手にした。そこでネックになるのがソクラテスはどこまでがソクラテスでどこからがプラトンの創造なのかという問題である。プラトン作は初期・…
Posted by 24wacky at 20:56│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした