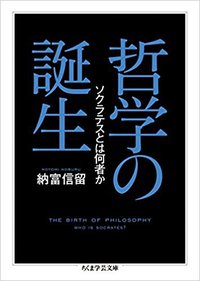2017年08月31日
『プラトンとの哲学 対話篇をよむ』納富信留

「哲学」とはなんだろうか。わたしは「哲学」のなにが気になって本書を手に取るのか。「第1章 生の逆転─『ゴルギアス』─」末尾で、著者は早くもこの答えに応答している。「哲学」とは「生き方を言論で吟味すること」である、と。師・ソクラテスを登場させた数々の対話篇というテクストは、登場人物たちと共に、読者をもこの「哲学」に加わることを強いる。「そこでは、答えを手に入れることではなく、怒ること、ひっくり返すこと、そして人生を賭けること」にこそ意味があり、答えはない。時に論争相手とともにソクラテスに不満をぶつけ、著者をも厳しく批判すること。それが「あなた」(プラトン)が目指した「哲学」である、と。「プラトンとの哲学」というタイトルに、著者の納富信留は文字通り不在のプラトンと対話しつつ、同時に読者参加型の読み方への誘いを込める。
『ゴルギアス』は、当代随一の弁論家ゴルギアスとソクラテスの論争をメインに、ゴルギアスの弟子ポロス、ゴルギアスを逗留させる主人で政治の道に進むことを夢見る青年カリクレスとの対話へと展開していく。
ゴルギアスが操る弁論術とは、言葉で人を説得する技術のことで、その技術を体得したい者に対して対価を得る職業が古代ギリシアの都市アテナイでは成立していた。
若きカリクレスは、それを習得して政治家となり、人々を操る力を得ることを欲望している。だから、ゴルギアスの弁論術は「技術」ではなく「迎合」に過ぎないとし、正と不正についての理想論を掲げてゴルギアスを論破するソクラテスの理想論が気にくわない。もしソクラテスのいうことが正しければ、自分の夢も覆されてしまうと、脅威に感じている。しかしながらその本音は、現代に生きる読者の多くにも共感されるはずだと、納富は指摘する。
いわば「理想と現実」という対立項の元で、いかに生きるべきかが問われている。ソクラテスの説く「善いこと」は、現実社会に背を向けたお説教以上のものではないと、カリクレス同様私も高を括りたくなる。
ところで「理想」という日本語は、明治初期に啓蒙思想家の西周が造り出した新語であり、西はプラトン哲学の説明のために使った(「第5章 理想への変容─『ポリテイア』─」)。それは近代日本建設のための手本としてあった。ところがその後、戦前の日本では「理想国」の名の下に全体主義にも利用され、ドイツでもナチス・ドイツで同様のことが起こった。その苦い結果ニヒリズムが生まれ、「それは理想論に過ぎない」というように、否定的、軽蔑的にだけ使われるようになったという。わたしたちが常識的に使う「理想と現実」という言葉も、そのように「政治的」に使わされたもので、その起源はすでに忘却されている。
プラトンの対話篇を読むことは、その起源に遡行し、「理想」を刷新する営為に他ならない。本書では「理想」と「イデア」の違いについても書かれているが、それはまた次の機会に吟味しよう。
『プラトンとの哲学 対話篇をよむ』
著者:納富信留
発行:岩波新書
発行年月:2015年7月22日
2017/08/20
ヨーロッパ哲学には3種類あることから本書は始まる。第一に、ソクラテスによる「問答」の哲学、「知の吟味」である。相互に相手の意見を批判的に検討する「討議」という伝統として現在まで伝わる。第二に、「上下に秩序づけられた二世界説」と「真理の探求」ないし「知の探求」である。ピュタゴラス、パルメニデス、…
2017/08/19
わたし(たち)が知っているソクラテスとはプラトンの著作に登場する「哲学者」のイメージとしてある。わたしはソクラテスに関心があるが、その関心の根拠を知りたく本書を手にした。そこでネックになるのがソクラテスはどこまでがソクラテスでどこからがプラトンの創造なのかという問題である。プラトン作は初期・…
2017/02/09
この20年とは、かつての文学批評の仕事をやめて哲学的なそれへ移る時期に重なる。しかし、その「変遷」が時系列でグラデーションのように読み取れる、というわけにはいかない。それが本書の魅力といえる。 ところで私が柄谷行人を読み始めたのは、記憶に間違えがなければ、当時住んでいた田無の図書館で借りた…
Posted by 24wacky at 20:52│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした