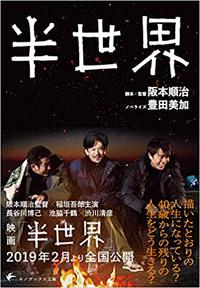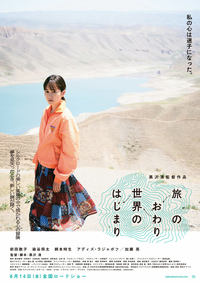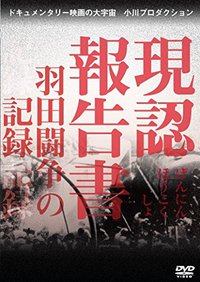2009年04月27日
『グラン・トリノ』
シネマスQに『グラン・トリノ』を観にいく。
クリント・イーストウッド監督の一貫した「メッセージ」とはこうだ。“この世界では、やられたらやり返すタフさが必要だ”。そこで発動される暴力はいったんは肯定されるが、それが人間にとって容易に拭うことのできない性の無い「悪」であるという余韻を残しエンディングを迎える。
その暴力の表現として、『ダーティー・ハリー』シリーズやマカロニ・ウエスタンシリーズなどであればガンが肯定され、『ダーティ・ファイター』『ミリオン・ダラー・ベイビー』などであればベア・ナックルがサウスポーからこれでもかと繰り出される。あるいは本作品のようにその両者が駆使されることもある。
イーストウッドは、偏執的にまで暴力に執着する。「いったん」それを肯定する、「やられたらやり返す」という作法において。彼にとってやっかいなことは、この作法がカタルシスという映画文法と不可分の関係にあることであり、彼はそうとは知らずと見事にハマってしまい、このデーモンに乗り移られ、次々と製作に勤しみ、ハリウッド一の映画作家と呼ばれる結果となった。
「平和ボケした」日本人である私から見れば、銃社会の肯定には眉を顰めざるをえないし、一面的なマッチョな世界(This is a man's world !!)に対してなされるであろう女性からの批判に対しては、あまりにも無防備ではないか。
これらの批判は恐らく正当である。正当である「にもかかわらず」余韻として残される「メッセージ」が、教訓臭のしないピュアなものとして、多才な彼自身によるオーケストレーションと共に差し出される。そのギリギリの「あやまち」(ハマルティアー)こそ、観る者を撃ち続ける。
ところでここからが最も重要なのであり、ネタバレになるので詳しく書かないが、『グラン・トリノ』においては、これまで一貫した、この「ギリギリのあやまち」の箍が外されてしまっている。これは驚きである。さらにいえば、この外され方を、ここ沖縄という地で観ることのローカリティの優位さに私は身震いさせられる。多少のほのめかしをしよう。
イーストウッド演じる主人公ウォルトは偏屈なガンコ親父だ。周囲の非白人コミュニティーに対し、差別的な言葉を連発する。彼の家には星条旗が誇らしげに立てられている。特に、隣人のモン族一家に対して、アジア人全般に対しての蔑称'gooks'を連発する。彼はかつて朝鮮戦争を経験し、何人もの朝鮮人を殺害してきた経歴を持つ。
モン族とは、ラオス、ベトナム、タイなどに散在する少数民族で、ベトナム戦争時にアメリカに加担し、戦後共産勢力からの迫害を逃れてアメリカに避難した人たちをいう。アメリカのために血を流したわりには、そのことがアメリカ人にほとんど知られていない。それどころか、マイノリティ故の差別・迫害を受けてきた人々だ(実際のモン族からオーディションによって抜擢された配役がそれぞれ素晴らしい!)。
物語は両者の衝突から和解という基本構造によって進んでいく。とりわけ、弱虫のタオとマッチョなウォルトの人種を超えた師弟関係のドラマはアメリカ的である。また、活発で利発な姉のスーはいち早くウォルトの警戒を解く。アメリカで生まれ育った彼女は、親の世代に比べアメリカナイズされている。皮肉なことに、ガンコなウォルトにアメリカ的自由をみている。彼女が発した四文字言葉をたしなめるのは、汚い差別言葉を日常連発しているウォルトだ。
私は、この映画を観ながら、隣の席に若い米兵がいるところを想像した。後ろに若い米兵と若い沖縄の女の子のカップルが座っているところを夢想してしまった。いったい彼ら・彼女らは終演後何を感じるだろうか?それに比べれば、エンディングで暗示されるキリスト教的救済の是非、あるいは作家に向けられるかもしれないポスト・コロニアル批判も重要ではあるが、私にとってどうでもよい。

クリント・イーストウッド監督の一貫した「メッセージ」とはこうだ。“この世界では、やられたらやり返すタフさが必要だ”。そこで発動される暴力はいったんは肯定されるが、それが人間にとって容易に拭うことのできない性の無い「悪」であるという余韻を残しエンディングを迎える。
その暴力の表現として、『ダーティー・ハリー』シリーズやマカロニ・ウエスタンシリーズなどであればガンが肯定され、『ダーティ・ファイター』『ミリオン・ダラー・ベイビー』などであればベア・ナックルがサウスポーからこれでもかと繰り出される。あるいは本作品のようにその両者が駆使されることもある。
イーストウッドは、偏執的にまで暴力に執着する。「いったん」それを肯定する、「やられたらやり返す」という作法において。彼にとってやっかいなことは、この作法がカタルシスという映画文法と不可分の関係にあることであり、彼はそうとは知らずと見事にハマってしまい、このデーモンに乗り移られ、次々と製作に勤しみ、ハリウッド一の映画作家と呼ばれる結果となった。
「平和ボケした」日本人である私から見れば、銃社会の肯定には眉を顰めざるをえないし、一面的なマッチョな世界(This is a man's world !!)に対してなされるであろう女性からの批判に対しては、あまりにも無防備ではないか。
これらの批判は恐らく正当である。正当である「にもかかわらず」余韻として残される「メッセージ」が、教訓臭のしないピュアなものとして、多才な彼自身によるオーケストレーションと共に差し出される。そのギリギリの「あやまち」(ハマルティアー)こそ、観る者を撃ち続ける。
ところでここからが最も重要なのであり、ネタバレになるので詳しく書かないが、『グラン・トリノ』においては、これまで一貫した、この「ギリギリのあやまち」の箍が外されてしまっている。これは驚きである。さらにいえば、この外され方を、ここ沖縄という地で観ることのローカリティの優位さに私は身震いさせられる。多少のほのめかしをしよう。
イーストウッド演じる主人公ウォルトは偏屈なガンコ親父だ。周囲の非白人コミュニティーに対し、差別的な言葉を連発する。彼の家には星条旗が誇らしげに立てられている。特に、隣人のモン族一家に対して、アジア人全般に対しての蔑称'gooks'を連発する。彼はかつて朝鮮戦争を経験し、何人もの朝鮮人を殺害してきた経歴を持つ。
モン族とは、ラオス、ベトナム、タイなどに散在する少数民族で、ベトナム戦争時にアメリカに加担し、戦後共産勢力からの迫害を逃れてアメリカに避難した人たちをいう。アメリカのために血を流したわりには、そのことがアメリカ人にほとんど知られていない。それどころか、マイノリティ故の差別・迫害を受けてきた人々だ(実際のモン族からオーディションによって抜擢された配役がそれぞれ素晴らしい!)。
物語は両者の衝突から和解という基本構造によって進んでいく。とりわけ、弱虫のタオとマッチョなウォルトの人種を超えた師弟関係のドラマはアメリカ的である。また、活発で利発な姉のスーはいち早くウォルトの警戒を解く。アメリカで生まれ育った彼女は、親の世代に比べアメリカナイズされている。皮肉なことに、ガンコなウォルトにアメリカ的自由をみている。彼女が発した四文字言葉をたしなめるのは、汚い差別言葉を日常連発しているウォルトだ。
私は、この映画を観ながら、隣の席に若い米兵がいるところを想像した。後ろに若い米兵と若い沖縄の女の子のカップルが座っているところを夢想してしまった。いったい彼ら・彼女らは終演後何を感じるだろうか?それに比べれば、エンディングで暗示されるキリスト教的救済の是非、あるいは作家に向けられるかもしれないポスト・コロニアル批判も重要ではあるが、私にとってどうでもよい。

Posted by 24wacky at 21:27│Comments(5)
│いつか観た映画みたいに
この記事へのコメント
『与那国カウボーイズ』の島監督に出くわした。桜坂劇場ではかなりの確率で出くわすが、シネマスQではこれが初めて。観終わった後、だらだらとゆんたくする。島監督は、全体的には良いが、エンディングに対しやや否定的な意見。それにも頷く。公開中の『スラムドッグ$ミリオネア』を薦められたので、観にいこうか・・・
Posted by 24wacky at 2009年04月27日 21:38
24wackyさん!
なるほど、その分析には納得させられました。最近のイーストウッド作にはどうも近づけないのですが、またぼちぼち観てみようかなと思った次第です。
なるほど、その分析には納得させられました。最近のイーストウッド作にはどうも近づけないのですが、またぼちぼち観てみようかなと思った次第です。
Posted by 齊藤 at 2009年04月30日 23:34
齊藤さん
「役者としてはこれが最後だ」とか言ってるくらいですから、観ておいた方がいいかもしれませんよ(笑)。
「役者としてはこれが最後だ」とか言ってるくらいですから、観ておいた方がいいかもしれませんよ(笑)。
Posted by 24wacky at 2009年05月01日 00:39
清志郎追悼
Posted by tyoshinaga at 2009年05月03日 00:24
教えてくれてありがとう。
Posted by 24wacky at 2009年05月03日 01:53