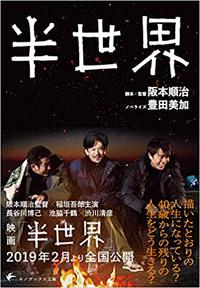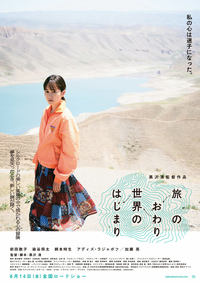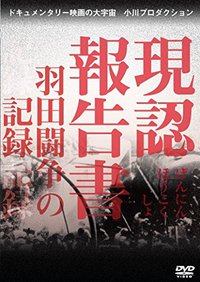2009年06月05日
『ユッスー・ンドゥール 魂の帰郷』
桜坂劇場で『ユッスー・ンドゥール 魂の帰郷』を観る。
 セネガルからワールド・マーケットへ進出し成功を収めたユッスー・ンドゥールは、魂が乾いていたのだろう。アトランタからニューオリンズ、ニューヨークからルクセンブルグ、そしてダカールへと、彼のsoul searchin'にカメラは寄り添う。その結果、アフリカ音楽と奴隷制、文化の伝播、音楽の力などが刻まれた熱いロード・ムービーが生まれた。
セネガルからワールド・マーケットへ進出し成功を収めたユッスー・ンドゥールは、魂が乾いていたのだろう。アトランタからニューオリンズ、ニューヨークからルクセンブルグ、そしてダカールへと、彼のsoul searchin'にカメラは寄り添う。その結果、アフリカ音楽と奴隷制、文化の伝播、音楽の力などが刻まれた熱いロード・ムービーが生まれた。
 セネガルからワールド・マーケットへ進出し成功を収めたユッスー・ンドゥールは、魂が乾いていたのだろう。アトランタからニューオリンズ、ニューヨークからルクセンブルグ、そしてダカールへと、彼のsoul searchin'にカメラは寄り添う。その結果、アフリカ音楽と奴隷制、文化の伝播、音楽の力などが刻まれた熱いロード・ムービーが生まれた。
セネガルからワールド・マーケットへ進出し成功を収めたユッスー・ンドゥールは、魂が乾いていたのだろう。アトランタからニューオリンズ、ニューヨークからルクセンブルグ、そしてダカールへと、彼のsoul searchin'にカメラは寄り添う。その結果、アフリカ音楽と奴隷制、文化の伝播、音楽の力などが刻まれた熱いロード・ムービーが生まれた。最初の移動地アトランタでは、3人のゴスペルシンガーがスピリチュアルな美しいハーモニーの曲を用意し、万全の体制で待ち受けているのだが、ユッスーはいきなりダメ出しをする。それは、彼に寄り添う盲目のピアニスト、モンセフ・ジュヌの通訳によって伝えられる。「特定の神がどうとかそういうことではない」。
3人は曇った顔をつき合せる。「おいおい、どうするね?」「Jesusを否定されて黙っているわけにはいかないぞ」。もめそうになるが結局はユッスーに従う。ゴスペルの歌い手に向かって特定の神(キリスト)について歌うなというのも滅茶苦茶な話しに思えるが、逆にいうと、ここからユッスーの求めているもの=映画のテーマの輪郭が観客に与えられる。
興味深いのはこの後のゴスペル教会でのライブ場面だ。会場全体がゴスペルの合唱で熱気に包まれ、ボルテージが上がる。そこへ待ってましたとばかり、ユッスーたちが登場し、演奏が始まる。ここでユッスーのワールド・ワイド・ヒット My Hope Is In You がかっこよく演奏されるのだが、そこそこにカットされ、次の移動地ニューオーリンズの外観ショットに繋げられる。見せ場を取り上げてしまうようなアレレ…というカッティングなのだ。しかし、その後の旅のシークエンスの連なりにおいて、ユッスーとバンドのメンバーたちの魂の行方が深化していくのが分かり、これが演出者の伝えたいことでもあると理解できると、この部分が「ヒット曲で盛り上がるライブシーン」として、むしろ全体の基調にそぐわなかったのではないか、などと想像させられる。
ニューオリンズのドラマー(名前を忘れた)が興味深い。マルディグラ・インディアンに扮した写真を自慢げにユッスーに見せるシーンがあるが、彼の出自がとても気になる。
ニューヨークでの圧巻は詩人ルロイ・ジョーンズとの共演だ。晩年のバロウズをも髣髴とさせるヤバそうなジジイ。彼の詩の朗読(というかほとんどラップ)に、ユッスーもリスペクトを惜しまない。
この映画で初めて思い知らされたのが、ユッスーの詩のすばらしさだ。これは字幕翻訳のすばらしさにも因る。正確に思い出せないのだが、おれの山羊がどうしたこうしたみたいな土地に根ざした詩が普遍的なサビ部分に繋げられた曲など、棍棒で後頭部を殴られたような衝撃が走る。
ユッスー・ンドゥールといえば、90年代当時ワールド・ミュージック・ブームに乗ったアーティストという印象への反感から、メジャーになる前の初期のバンド編成時代のCDを買って聴く程度で深入りしなかった。詩を疎かにしてはいけないと痛感する。
最後にこの映画のトーク・イベントで語ったピーター・バラカンの言葉を引用する。桜坂劇場での上映は残念ながら明日が最終日となってしまったが、時間がある方は是非!観にいってほしい。
公式サイトが閉鎖されていて映画に関する情報が得難いのが残念。ユッスー・ンドゥールについてはこちらのページが初心者向けとして参考になる。ワールド・ミュージック批判は沖縄音楽批判にも援用できるなど話が広がりそうだが、この辺でひとまず筆をおく。
3人は曇った顔をつき合せる。「おいおい、どうするね?」「Jesusを否定されて黙っているわけにはいかないぞ」。もめそうになるが結局はユッスーに従う。ゴスペルの歌い手に向かって特定の神(キリスト)について歌うなというのも滅茶苦茶な話しに思えるが、逆にいうと、ここからユッスーの求めているもの=映画のテーマの輪郭が観客に与えられる。
興味深いのはこの後のゴスペル教会でのライブ場面だ。会場全体がゴスペルの合唱で熱気に包まれ、ボルテージが上がる。そこへ待ってましたとばかり、ユッスーたちが登場し、演奏が始まる。ここでユッスーのワールド・ワイド・ヒット My Hope Is In You がかっこよく演奏されるのだが、そこそこにカットされ、次の移動地ニューオーリンズの外観ショットに繋げられる。見せ場を取り上げてしまうようなアレレ…というカッティングなのだ。しかし、その後の旅のシークエンスの連なりにおいて、ユッスーとバンドのメンバーたちの魂の行方が深化していくのが分かり、これが演出者の伝えたいことでもあると理解できると、この部分が「ヒット曲で盛り上がるライブシーン」として、むしろ全体の基調にそぐわなかったのではないか、などと想像させられる。
ニューオリンズのドラマー(名前を忘れた)が興味深い。マルディグラ・インディアンに扮した写真を自慢げにユッスーに見せるシーンがあるが、彼の出自がとても気になる。
ニューヨークでの圧巻は詩人ルロイ・ジョーンズとの共演だ。晩年のバロウズをも髣髴とさせるヤバそうなジジイ。彼の詩の朗読(というかほとんどラップ)に、ユッスーもリスペクトを惜しまない。
この映画で初めて思い知らされたのが、ユッスーの詩のすばらしさだ。これは字幕翻訳のすばらしさにも因る。正確に思い出せないのだが、おれの山羊がどうしたこうしたみたいな土地に根ざした詩が普遍的なサビ部分に繋げられた曲など、棍棒で後頭部を殴られたような衝撃が走る。
ユッスー・ンドゥールといえば、90年代当時ワールド・ミュージック・ブームに乗ったアーティストという印象への反感から、メジャーになる前の初期のバンド編成時代のCDを買って聴く程度で深入りしなかった。詩を疎かにしてはいけないと痛感する。
最後にこの映画のトーク・イベントで語ったピーター・バラカンの言葉を引用する。桜坂劇場での上映は残念ながら明日が最終日となってしまったが、時間がある方は是非!観にいってほしい。
奴隷制がなければ、アフリカン・アメリカンの文化は無かった。アフリカン・アメリカンの文化が無ければ、当時のアメリカには文化と呼べるものは何も無かった。決して奴隷貿易を肯定するわけではないが、それが今の音楽文化を生んだと思うと、複雑な気持ちになります。
公式サイトが閉鎖されていて映画に関する情報が得難いのが残念。ユッスー・ンドゥールについてはこちらのページが初心者向けとして参考になる。ワールド・ミュージック批判は沖縄音楽批判にも援用できるなど話が広がりそうだが、この辺でひとまず筆をおく。
タグ :ユッスー・ンドゥール
Posted by 24wacky at 02:28│Comments(0)
│いつか観た映画みたいに