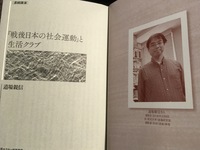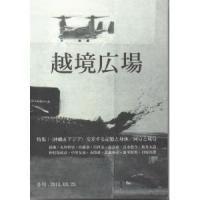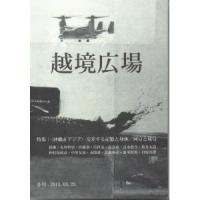2009年10月18日
「江戸上り」の唐装束は強制ではなかった
昨日17日は、沖縄県立博物館・美術館での博物館文化講座『琉球使節像の変遷と対日本関係-屈辱・偏見から「御取り合い(おとりあい)」へ-』を聴きに行った。今回の講座は開催中の特別展「琉球使節、江戸へ行く!」の関連講座として行われた。講師の豊見山和行氏(琉球大学教授)は、江戸幕府に派遣された琉球使節の見方をめぐる戦前以来の言説(中国装束を強制されたなど)の誤解・誤読の考え方に対して、文書や絵巻物などの丹念な研究から引き出された新たな琉球使節像を平易に説明した。
まず豊見山氏は「江戸上り」という言葉は、琉球・沖縄の人びとにとって、「屈辱」あるいは「恥ずかしい」というイメージを伴うものであることについて触れ、「そういうことを聞いたことがある方はいらっしやいますか?」とフロアに問うと、年配の方々が数名手を挙げた。
「上り」(あるいはその逆の「下り」)というと、中央(江戸・東京)に向う(あるいは離れる)ことを意味するために現在でも用いられる政治的な言葉である。しかし、この言葉が琉球国で使われた形跡は無く、公的表現としては「江戸立」(旅立ちの意)が用いられた。
そもそも「江戸上り」=「屈辱」説のルーツは、真境名安興『沖縄一千年史』(1923年)に遡る。そこで真境名は、新しく琉球王が決まった時に、薩摩守に伴われて謝恩使を江戸へ派遣することについて触れ、「琉球及び支那の音楽を奏し且つ服装儀仗等は悉く支那に模擬したりしなり」としたことを「欺瞞するに努めたるが如し」と書いている。薩摩藩に強制され唐装束を纏い「江戸上り」をさせられたのは「屈辱」であり、偏見を被る結果となったという。
この説は、以降伊波普猷による「琉球=薩摩藩の奴隷」論などでいっそう固定化され、省みられることなく現在まで通説となってしまった。これらの誤解が生まれたのは、日本の近代化に包摂される琉球=沖縄という時代に生きた彼らが、同時代に感じていた抑圧、苦しみを過去に投影していたことに起因する。
豊見山は、この誤解をまずは文書の精査を通じて反証する。1681年(延宝9年)江戸への使節の装束についての指示では、江戸は以前と変わり交際向きが華やかになっており、先年の琉球使節の小姓の服装が貧相であることが目につくので改めて欲しいと書かれている。つまりは華美さが求められているに過ぎない。異国風を強制されたとされる1709年(宝永6年)堀興達書も良く読めば、唐風の強制ではなくあくまで強調であることが分かる。
次に豊見山は絵巻物を紹介する。これらは特別展「琉球使節、江戸へ行く!」で観ることができるし、沖縄歴史情報というサイトから見ることも出来る。「これを見れば一目瞭然。真境名がこの絵巻物を見ていたら屈辱説はとらなかっただろう」と豊見山。

宝永七年寅十一月十八日 琉球中山王両使者登城行列 023
身分の高い豊見城王子は唐装束、低い従者は琉装と唐一辺倒の強制でないことが分かる
琉球の中国指向は国家戦略としてあり、そこに琉球の自立意識を認めるべきである。「屈辱的」という歴史認識を克服し、「大和の御取り合い」=対幕府外交としての「江戸立」を多面的、多角的に検討することを豊見山はまとめの言葉とした。
薩摩藩による琉球の唐装束は強制ではなく異国風の強調である。それは琉球にとっても国家としての自立意識に基づいた、プラスの要素を伴ったパフォーマンスですらあった。それを「屈辱」と捉えるべきではない。この豊見山の解説は明快である。
それにほぼ同意した上で、その異国風の強調にオリエンタリズム(サイード)を見出す批判もまた成り立つかもしれない。さらに興味が尽きないのは「御取り合い」(外交)という「交換」の様式についてであるが、とりあえずこのあたりで筆をおく。
「上り」(あるいはその逆の「下り」)というと、中央(江戸・東京)に向う(あるいは離れる)ことを意味するために現在でも用いられる政治的な言葉である。しかし、この言葉が琉球国で使われた形跡は無く、公的表現としては「江戸立」(旅立ちの意)が用いられた。
そもそも「江戸上り」=「屈辱」説のルーツは、真境名安興『沖縄一千年史』(1923年)に遡る。そこで真境名は、新しく琉球王が決まった時に、薩摩守に伴われて謝恩使を江戸へ派遣することについて触れ、「琉球及び支那の音楽を奏し且つ服装儀仗等は悉く支那に模擬したりしなり」としたことを「欺瞞するに努めたるが如し」と書いている。薩摩藩に強制され唐装束を纏い「江戸上り」をさせられたのは「屈辱」であり、偏見を被る結果となったという。
この説は、以降伊波普猷による「琉球=薩摩藩の奴隷」論などでいっそう固定化され、省みられることなく現在まで通説となってしまった。これらの誤解が生まれたのは、日本の近代化に包摂される琉球=沖縄という時代に生きた彼らが、同時代に感じていた抑圧、苦しみを過去に投影していたことに起因する。
豊見山は、この誤解をまずは文書の精査を通じて反証する。1681年(延宝9年)江戸への使節の装束についての指示では、江戸は以前と変わり交際向きが華やかになっており、先年の琉球使節の小姓の服装が貧相であることが目につくので改めて欲しいと書かれている。つまりは華美さが求められているに過ぎない。異国風を強制されたとされる1709年(宝永6年)堀興達書も良く読めば、唐風の強制ではなくあくまで強調であることが分かる。
次に豊見山は絵巻物を紹介する。これらは特別展「琉球使節、江戸へ行く!」で観ることができるし、沖縄歴史情報というサイトから見ることも出来る。「これを見れば一目瞭然。真境名がこの絵巻物を見ていたら屈辱説はとらなかっただろう」と豊見山。

宝永七年寅十一月十八日 琉球中山王両使者登城行列 023
身分の高い豊見城王子は唐装束、低い従者は琉装と唐一辺倒の強制でないことが分かる
琉球の中国指向は国家戦略としてあり、そこに琉球の自立意識を認めるべきである。「屈辱的」という歴史認識を克服し、「大和の御取り合い」=対幕府外交としての「江戸立」を多面的、多角的に検討することを豊見山はまとめの言葉とした。
薩摩藩による琉球の唐装束は強制ではなく異国風の強調である。それは琉球にとっても国家としての自立意識に基づいた、プラスの要素を伴ったパフォーマンスですらあった。それを「屈辱」と捉えるべきではない。この豊見山の解説は明快である。
それにほぼ同意した上で、その異国風の強調にオリエンタリズム(サイード)を見出す批判もまた成り立つかもしれない。さらに興味が尽きないのは「御取り合い」(外交)という「交換」の様式についてであるが、とりあえずこのあたりで筆をおく。
タグ :豊見山和行
Posted by 24wacky at 00:40│Comments(4)
│シンポレポートなど
この記事へのコメント
24wackyさんのご紹介で私も興味をもっ持ちましたが、結局足を運べませんでした…。
それはさておき、ウチナーンチュにとって大事なコトは歴史認識ももちろんなんですが、歴史認識のもたらすもの、あるいはその先にあるものではないかと思います。
洗練された側にいる研究者たち、特に最近各種マスコミにおいて露出度の高い若手の方が新聞その他の場において、ウチナーンチュがヤマトゥンチューに対して持ちがちな?軽い被害者意識や敵愾心のようなモノ(というと語弊があるでしょうか?語彙力が貧相なので適切な表現が浮かびませんでした…)を払拭するような言説を歴史認識から一歩進めたカタチで展開しているのをたびたび見掛けます。
その辺り、私には安易な「同化」や、沖縄・ウチナーンチュが抱える現実的な問題を留保し、なあなあで済まそうとする態度に思えてなりません。
それはさておき、ウチナーンチュにとって大事なコトは歴史認識ももちろんなんですが、歴史認識のもたらすもの、あるいはその先にあるものではないかと思います。
洗練された側にいる研究者たち、特に最近各種マスコミにおいて露出度の高い若手の方が新聞その他の場において、ウチナーンチュがヤマトゥンチューに対して持ちがちな?軽い被害者意識や敵愾心のようなモノ(というと語弊があるでしょうか?語彙力が貧相なので適切な表現が浮かびませんでした…)を払拭するような言説を歴史認識から一歩進めたカタチで展開しているのをたびたび見掛けます。
その辺り、私には安易な「同化」や、沖縄・ウチナーンチュが抱える現実的な問題を留保し、なあなあで済まそうとする態度に思えてなりません。
Posted by じゅげむ at 2009年10月21日 21:01
>じゅげむさん
>それはさておき、ウチナーンチュにとって大事なコトは歴史認識ももちろんなんですが、歴史認識のもたらすもの、あるいはその先にあるものではないかと思います。
このへんは多少議論しましたよね。
恐らくじゅげむさんと似たようなことを自分なりに言い換えると、歴史学にしてもあるいは民俗学にしても、極めて政治的なスタンスがその背後に潜んでいるものであり、それを学ぶ者、あるいはそれを伝える者はまず第一にそのことに自覚的であるべきだということ。第二にそのように自覚的に(つまり政治的意図を持って)学者が歴史を伝えようとすること(このことをじゅげむさんは「歴史認識から一歩進めたカタチで展開している」と表現しているのではと捉えています)はたびたび起こることであり、それに対する批判を(その露出度が高ければ高いほど)すべきである。それをするのは歴史学者はもとより、それ以外の人々によって、自由に公然となされるべきだということ。『目からウロコ・・・』の著者への批判・論争は小林何某などと不毛になされるより、それこそウチナーンチュ間でまずはなされるべきではないでしょうか。それらが公然となされない隙に乗じて、ヤマトゥンチューが我が物顔で口を突っ込んできますから(笑)。
>それはさておき、ウチナーンチュにとって大事なコトは歴史認識ももちろんなんですが、歴史認識のもたらすもの、あるいはその先にあるものではないかと思います。
このへんは多少議論しましたよね。
恐らくじゅげむさんと似たようなことを自分なりに言い換えると、歴史学にしてもあるいは民俗学にしても、極めて政治的なスタンスがその背後に潜んでいるものであり、それを学ぶ者、あるいはそれを伝える者はまず第一にそのことに自覚的であるべきだということ。第二にそのように自覚的に(つまり政治的意図を持って)学者が歴史を伝えようとすること(このことをじゅげむさんは「歴史認識から一歩進めたカタチで展開している」と表現しているのではと捉えています)はたびたび起こることであり、それに対する批判を(その露出度が高ければ高いほど)すべきである。それをするのは歴史学者はもとより、それ以外の人々によって、自由に公然となされるべきだということ。『目からウロコ・・・』の著者への批判・論争は小林何某などと不毛になされるより、それこそウチナーンチュ間でまずはなされるべきではないでしょうか。それらが公然となされない隙に乗じて、ヤマトゥンチューが我が物顔で口を突っ込んできますから(笑)。
Posted by 24wacky at 2009年10月21日 22:44
まさしく仰るとおりで。補足説明ありがとうございます。
まずはウチナーンチュ間で議論するコトが思考停止状態から抜け出す一歩なのでしょう。そしてそれ自体が「同調圧力」云々の喧伝を打ち消すコトにもつながる。
まぁ、若い頃の不勉強を反省する、泥臭い側の遠吠えです…(^~^)
まずはウチナーンチュ間で議論するコトが思考停止状態から抜け出す一歩なのでしょう。そしてそれ自体が「同調圧力」云々の喧伝を打ち消すコトにもつながる。
まぁ、若い頃の不勉強を反省する、泥臭い側の遠吠えです…(^~^)
Posted by じゅげむ at 2009年10月21日 23:22
恐らくそのような実践・試行の場としてあったのが、次の日同じ博物館・美術館での方言札に関したしまくとぅばワークショップだったのではと勝手に想像しています。私は上に述べたような理由から、ウチナーンチュ間で議論する場に同席することを敢えて控えました。
Posted by 24wacky at 2009年10月21日 23:37