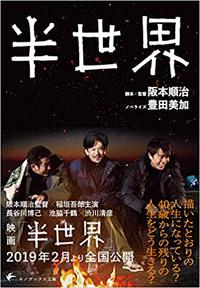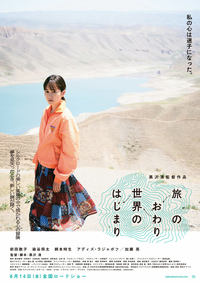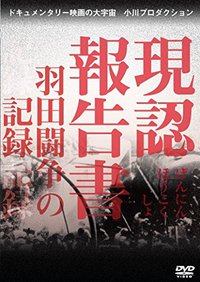2015年02月14日
『沖縄/大和』

11日、座・高円寺にて座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバルのコンペテシション部門入賞作品3作を観る。なお、大賞は時間がなくて見逃した綿井健陽監督の『イラク チグリスに浮かぶ平和』だったとか。
『沖縄/大和』
監督:比嘉賢多
99分
沖縄出身大学生の卒業制作。本土に出て直面する沖縄アイデンティティー。「内地の人」と沖縄人の間にひく「ライン」は何なのかという自らの問いを投げかける。オスプレイ配備に揺れる普天間基地ゲート前でのパートが半分、そして沖縄の友人知人親戚のパートが半分。
前者ではカメラは賛成・反対双方へ「中立」な立場で向けられる。オスプレイファンクラブという「カウンター」の出現によって、基地をめぐる沖縄の政治的対立が明確にあることがいちおう表象されている。作家のまなざしは、作家にとって現場で目につく人へあてられる。反対運動では飄々とした小橋川さんに焦点化され、現場ではおなじみの彼のパフォーマンスもカメラはとらえる。ジャーナリスティックな視点とは異なる表出といえるが、それがなにを現しているのかは不明だ。
他方で、オスプレイファンクラブリーダーへのインタビューは、「中立」の視点から彼ら/彼女らへインタビューする資料がほとんどない現在においては、それなりに貴重といえる。
いずれにせよ、対立した意見をいわれるたびに自身が揺れる、そのポジションをつなぎあわせているというのが「編集されたもの」となっている。その提示は、それを観る沖縄人、「日本人」にどう捉えられるのか。それが上映会という場なのだろうが、私にはそれを積極的に語ろうという意志は生まれにくかった。
それよりもこのドキュメンタリーをドキュメンタリーたらしめているのは、友人の女性の表象の変化と変わらない、そして言語化できない「内面」にある。彼女は、沖縄ではカジマヤーを祝おうという祖母や家族が茶の間にいて談笑する場面に現れる。また、別のアパートの一室のような別の場面では、同じ女友だちと二人で作家からインタビューを受ける。「沖縄と大和のあいだにラインがあるか?」と。彼女は、「ある」と答える。それは観光の問題だといって感情を噴出させる。「ていうか、なんで観光客は沖縄に来る?」という彼女の疑問はダブルバインド状態にある沖縄の固定化を非論理的に崩そうとする。
もう一つの場面は、雪が積もった外観、そして屋内のストーブというインサートカットの後に、その部屋に独り生活しているらしい彼女へのインタビューとなっている。彼女のファッションからも、時間の経過がうかがえる。「なんで観光客は沖縄に来る?」と答えたときの自身の映像をパソコンで観た彼女に、カメラはそのときと今の彼女へ変化を捉える。あのときの自分と今の自分がいること。今はあのときと変わり、「勉強」した自分がいること。しかし、それ以上彼女はその心情をどう語ればよいのか戸惑い、口ごもる。そして目に涙を浮かべつつ漏らす。「笑顔でいたい…」と。
上映後の舞台挨拶で、作家の比嘉賢多は語っている。彼女はかつての映像で自身の攻撃性をみせつけられショックを受け、本当は笑っていたいのだといったと。私はそれに加えて、大和での慣れない生活で、寒くて、こころもからだも強張り、いつしか笑えなくなってしまった自分が哀しくてそういったのではないかと解釈した。いずれにせよ、このシーンは際立っている。まぎれもなく彼女を言いよどみさせるそのなかに、「沖縄/大和」の植民地的差別構造がひそんでいるのだから。
『ヘイトスピーチ』
監督:佐々木航弥
92分
「カウンター」というアクションを起こした人たちを丁寧に追いかけている。この国の多元主義の可能性を表現してくれたことに感謝したい。
『風和里 -平成の駄菓子屋物語-』
監督:田中健太
80分
大阪府富田林市にある小さな駄菓子屋「風和里(ふわり)」を営む親子と、そこに来る、家庭の問題や学校でのイジメなどの問題を抱えた子どもたち。居場所というテーマを見事に描ききっている。
関連サイト:
座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル
Posted by 24wacky at 11:03│Comments(3)
│いつか観た映画みたいに
この記事へのコメント
こんにちは。読んでいます。
映画を観ることが出来ないので、24wackyさんのブログがとても有難いです。
私事で恐縮なのですが、母が癌になりました。
お医者さんのお話では、本人の身体の状態からいくと、
通常の場合に行う癌の治療は難しい、と。
弟が生まれ変わろうとするかのように、癌が子宮の中にあります。
言葉を失くしています。
そのような経緯の中で、母に代わり、
母が行っていた文字を書く勉強会になぜか参加する羽目に。
先生の目標は「最終的に(勉強してる人が)50枚~60枚を書くこと」
既に今からイチフーフー(息フウフウ)です。
書いた直後すぐに他のかたと比較されるので気づくのですが、
「この貧困な語彙で、どうやって場面を書くんだろう」って泣きそうです。
最初から「耳の記憶」って切って捨てないと何も書けない、
って誰よりも24wackyさんがご存知でしょう。
恐らく、そこでの最後の段階で、
24wackyさんにお渡しした膨大な紙の中から、
何かを取りだして膨らませる作業をすることになると思います。
ただ、自身の身体(と記憶の障害 ―― 脳に損傷を受けたことのない人から見ればそうでしょう ―― )に纏わることを軸にしたい、と思っています。
というより、元々、それを臨床例として残したくて島に戻ったのですから、
それ抜きには出来ません。
なので、ご迷惑をおかけするようなことはないです。
ただ、あれを読んだ人は夫以外には24wackyさんだけです。
誰かに読んで頂くことを前提としておらず、それでも書こう、と考えたのは
24wackyさんがおられたからだ、って自分で判ってたので。
24wackyさんがいなければ、絶対に書こうとは思わなかった。
なので、その旨、お許しを頂けますでしょうか。
今、島にいる時間がとても大切なものに思えます。
なんというか、それは、哀しいことも辛いことも沢山あるのですけど、
それでもやっぱり帰って来て良かった、と思ってます。
24wackyさんと一緒に夜に歩いて
「ここは街灯もないし(一人で引き返す時に)危ないからダメー!」って怒られた
小さな森の「主」みたいなでっかい猫がいるんですけど、
なぜか懐いてくれて、一緒にいるだけで和みます。
先日は、その猫と遊んでいる時に
何度か見かけた鳥がベランダにやってきて、パンくずをねだられ、水をせがまれ……。
人がベランダにいるのにやって来たんです。
島にはよくいる小さな鳥なのですが、記憶してる限り、
人が傍に寄り過ぎるとビビって逃げて行くのが典型的行動パターン。不思議です。
「この小さな森が、その全てで一生懸命に励ましてくれてる」
そう思えて仕方がありません。
そういう時間を失うと、たとえ暖かいところでも島の人はガチガチに固まるような気がします。
ちょっとお話をする機会があった同年代の女性ですけど
その方は寒いところにお仕事に行って3ヶ月で戻った、と。
理由は「波の音が聞こえないから」。
お母様が、糸満の方だったんです。
なんで「10年、島にいなかった」っていう話に、とてもびっくりされておられました。
(言外に「よく生きてたね~」っていう感じが……)
「地の記憶」それは「血の記憶」と深く結びつき、そう簡単に切り離せない。
そういう経験をしてきた人間にすると、攻撃的(口撃的)になれるとは、
「生きようとしてる、その力がまだある、表現力が追いつかないだけ」
ってことにも思えます。
むしろ、口ごもり、目に涙を浮かべてしまうまでになると、最後、身体にくる。
この映画に出てらした女性が、生まれた島の踊り一つでいいから踊れるのなら、
唄一つでいいから唄えるなら、少し楽になれるのじゃあないか、
と、そればかりを祈ってます。生きてほしいです。
ただこれは、別に島の人に限らずそうなのかもしれませんが。
どうぞ、お身体を労わりながら、
お母様と過ごされる時間を大事にされて下さいませ。
追伸:今日、この間のコメント欄にお話を書いた、
以前から良く存じ上げている先生のご意見が、新報の「論壇」に掲載されてました。
24wackyさんは全てご存知のお話なので内容までは書きませんが、ご連絡まで。
映画を観ることが出来ないので、24wackyさんのブログがとても有難いです。
私事で恐縮なのですが、母が癌になりました。
お医者さんのお話では、本人の身体の状態からいくと、
通常の場合に行う癌の治療は難しい、と。
弟が生まれ変わろうとするかのように、癌が子宮の中にあります。
言葉を失くしています。
そのような経緯の中で、母に代わり、
母が行っていた文字を書く勉強会になぜか参加する羽目に。
先生の目標は「最終的に(勉強してる人が)50枚~60枚を書くこと」
既に今からイチフーフー(息フウフウ)です。
書いた直後すぐに他のかたと比較されるので気づくのですが、
「この貧困な語彙で、どうやって場面を書くんだろう」って泣きそうです。
最初から「耳の記憶」って切って捨てないと何も書けない、
って誰よりも24wackyさんがご存知でしょう。
恐らく、そこでの最後の段階で、
24wackyさんにお渡しした膨大な紙の中から、
何かを取りだして膨らませる作業をすることになると思います。
ただ、自身の身体(と記憶の障害 ―― 脳に損傷を受けたことのない人から見ればそうでしょう ―― )に纏わることを軸にしたい、と思っています。
というより、元々、それを臨床例として残したくて島に戻ったのですから、
それ抜きには出来ません。
なので、ご迷惑をおかけするようなことはないです。
ただ、あれを読んだ人は夫以外には24wackyさんだけです。
誰かに読んで頂くことを前提としておらず、それでも書こう、と考えたのは
24wackyさんがおられたからだ、って自分で判ってたので。
24wackyさんがいなければ、絶対に書こうとは思わなかった。
なので、その旨、お許しを頂けますでしょうか。
今、島にいる時間がとても大切なものに思えます。
なんというか、それは、哀しいことも辛いことも沢山あるのですけど、
それでもやっぱり帰って来て良かった、と思ってます。
24wackyさんと一緒に夜に歩いて
「ここは街灯もないし(一人で引き返す時に)危ないからダメー!」って怒られた
小さな森の「主」みたいなでっかい猫がいるんですけど、
なぜか懐いてくれて、一緒にいるだけで和みます。
先日は、その猫と遊んでいる時に
何度か見かけた鳥がベランダにやってきて、パンくずをねだられ、水をせがまれ……。
人がベランダにいるのにやって来たんです。
島にはよくいる小さな鳥なのですが、記憶してる限り、
人が傍に寄り過ぎるとビビって逃げて行くのが典型的行動パターン。不思議です。
「この小さな森が、その全てで一生懸命に励ましてくれてる」
そう思えて仕方がありません。
そういう時間を失うと、たとえ暖かいところでも島の人はガチガチに固まるような気がします。
ちょっとお話をする機会があった同年代の女性ですけど
その方は寒いところにお仕事に行って3ヶ月で戻った、と。
理由は「波の音が聞こえないから」。
お母様が、糸満の方だったんです。
なんで「10年、島にいなかった」っていう話に、とてもびっくりされておられました。
(言外に「よく生きてたね~」っていう感じが……)
「地の記憶」それは「血の記憶」と深く結びつき、そう簡単に切り離せない。
そういう経験をしてきた人間にすると、攻撃的(口撃的)になれるとは、
「生きようとしてる、その力がまだある、表現力が追いつかないだけ」
ってことにも思えます。
むしろ、口ごもり、目に涙を浮かべてしまうまでになると、最後、身体にくる。
この映画に出てらした女性が、生まれた島の踊り一つでいいから踊れるのなら、
唄一つでいいから唄えるなら、少し楽になれるのじゃあないか、
と、そればかりを祈ってます。生きてほしいです。
ただこれは、別に島の人に限らずそうなのかもしれませんが。
どうぞ、お身体を労わりながら、
お母様と過ごされる時間を大事にされて下さいませ。
追伸:今日、この間のコメント欄にお話を書いた、
以前から良く存じ上げている先生のご意見が、新報の「論壇」に掲載されてました。
24wackyさんは全てご存知のお話なので内容までは書きませんが、ご連絡まで。
Posted by ブーウジぬイナグングヮ at 2015年03月15日 16:47
ブーウジぬイナグングヮさん
近況報告ありがとうございます。
お母様のこと、なんといってよいか…
またお会いしたらゆっくり話しましょう。
近況報告ありがとうございます。
お母様のこと、なんといってよいか…
またお会いしたらゆっくり話しましょう。
Posted by 24wacky at 2015年03月15日 17:34
こんにちは。
先日はご連絡有難うございました。
記事、拝読しました。
「代表制がもたらす欠陥から来る不満は、自らが主体的に「われわれ」や「みんな」をつくっていくプロセスに関わることによってしか解消されない」
という理解をしました。
メディア側の人間でない、恣意性を持ちえない「沖縄の人々」の一人としては、
このような理解が妥当かと。
島の新聞に対する「このウルサイ<左翼っていうよりホンネはこちらでしょう。自分たちが軍事植民地持ってるという事実を広げられたら困る。右であれ左であれ、これは同じ。沖縄メディアに冠される「左翼」とは「ヤマトを統治する時、知られたら都合の悪いもの」であり同時に「大多数が直視したくないこと」ということだと理解してます>新聞潰せ」
という圧力は大昔からあるみたいで、
そこから来る慎重過ぎるまでの慎重な姿勢は、
投書が掲載された際の熾烈なまでのご担当の方のツッコミという、
自らの経験を以て何となく推測がつきます。
ただ、それが本来拾うべき声まで潰してしまったら、
地元紙ゆえに持ちうる島の公器としての役割
<古代ギリシャの民会が持つ「みんなが納得しない」を底で支える機能>
もまた削がれることになる、という島の新聞への警鐘にも読めます。
(書きながら、まるで病気を治す時に必要な運動の強弱の取り方に似ている、と
―― 機能の回復には有効だけれど、身体にストレスをもたらさない、そのギリギリの強度を見つけないといけない。
バランスの難しさを思って<考えるだけで>なんか足元が崩れそうな感じです。
なぜかここ最近、めまいと耳鳴りが凄くてオバサン街道を突っ走っている気が……・汗)
経験からの推測に過ぎませんが、
「書けること、書かないこと、書けないこと、色々あるんだろうなあ」って思ってます。
本当はもっと早くご連絡を差し上げたかったのですけど、
その深読みを文章化しようとして、結果、挫折し、その分時間がかかりました。
すみません。
実は、私もまたメールを受けとった「彼」に、
メールを差し上げた「沖縄の人々」の中の一人です。
私の場合、恐らく決定的に「彼女」と違うのは、
そこに質問の束が含まれていることです。
「自らが主体的に「われわれ」や「みんな」をつくっていくプロセスに関わる」
「沖縄の人々」の一人としての願いや役割を果たすためなら、
それこそ仰るように島の新聞に投書した方が効果的です。
なのに、なぜ「彼」でなければならなかったか。
詰まるところ、その質問の束への答えを知りたかったのです。
メールを送った時には、そのことにとても無自覚でしたが、
「この疑問への答えは、島の新聞をどんなに読んでも絶対に得られない」
と、薄ぼんやり ―― それこそ皮膚感覚で ―― 判ってました。
どうやらネット見てる限り、私の質問への答えは、
全国紙、しかも全くワケの判らん全国紙にさえ載ってなくて、
最近(それもここ2・3日)発行された学術書にしか載ってないらしいんです。
そして、島の新聞には、その前提になる基礎知識の「き」の字も載ってない。
だけど、それが沖縄にないか、ったら全然違います。あるのは事実です。
まさしく島の新聞がレッテル張られて疎外されるのと同じ構図で無視されてます。
そして、「なんだかワケの判らない怖ろしい何か」
が蠢いてる(事実だと思いますが)感覚だけがある。
それを記事にして新聞に載せることは広告にもなってしまう危惧もまたあるわけで、
それを避けようとする島の新聞の考えも判らないではないです。
またしてもバランス。はあ~。もう難儀です。
そんなことを発想の糸口にして、そこから色んなことを考えました。
頭の中に、これまで見聞きした情報の断片が折り重なって出来る
曼荼羅みたいなものがあるのは判ってて、
それを文章化することを目指したんですが、どうにも上手くいきません。限界。
なので、これは、またゆっくりと。
それでは……。
先日はご連絡有難うございました。
記事、拝読しました。
「代表制がもたらす欠陥から来る不満は、自らが主体的に「われわれ」や「みんな」をつくっていくプロセスに関わることによってしか解消されない」
という理解をしました。
メディア側の人間でない、恣意性を持ちえない「沖縄の人々」の一人としては、
このような理解が妥当かと。
島の新聞に対する「このウルサイ<左翼っていうよりホンネはこちらでしょう。自分たちが軍事植民地持ってるという事実を広げられたら困る。右であれ左であれ、これは同じ。沖縄メディアに冠される「左翼」とは「ヤマトを統治する時、知られたら都合の悪いもの」であり同時に「大多数が直視したくないこと」ということだと理解してます>新聞潰せ」
という圧力は大昔からあるみたいで、
そこから来る慎重過ぎるまでの慎重な姿勢は、
投書が掲載された際の熾烈なまでのご担当の方のツッコミという、
自らの経験を以て何となく推測がつきます。
ただ、それが本来拾うべき声まで潰してしまったら、
地元紙ゆえに持ちうる島の公器としての役割
<古代ギリシャの民会が持つ「みんなが納得しない」を底で支える機能>
もまた削がれることになる、という島の新聞への警鐘にも読めます。
(書きながら、まるで病気を治す時に必要な運動の強弱の取り方に似ている、と
―― 機能の回復には有効だけれど、身体にストレスをもたらさない、そのギリギリの強度を見つけないといけない。
バランスの難しさを思って<考えるだけで>なんか足元が崩れそうな感じです。
なぜかここ最近、めまいと耳鳴りが凄くてオバサン街道を突っ走っている気が……・汗)
経験からの推測に過ぎませんが、
「書けること、書かないこと、書けないこと、色々あるんだろうなあ」って思ってます。
本当はもっと早くご連絡を差し上げたかったのですけど、
その深読みを文章化しようとして、結果、挫折し、その分時間がかかりました。
すみません。
実は、私もまたメールを受けとった「彼」に、
メールを差し上げた「沖縄の人々」の中の一人です。
私の場合、恐らく決定的に「彼女」と違うのは、
そこに質問の束が含まれていることです。
「自らが主体的に「われわれ」や「みんな」をつくっていくプロセスに関わる」
「沖縄の人々」の一人としての願いや役割を果たすためなら、
それこそ仰るように島の新聞に投書した方が効果的です。
なのに、なぜ「彼」でなければならなかったか。
詰まるところ、その質問の束への答えを知りたかったのです。
メールを送った時には、そのことにとても無自覚でしたが、
「この疑問への答えは、島の新聞をどんなに読んでも絶対に得られない」
と、薄ぼんやり ―― それこそ皮膚感覚で ―― 判ってました。
どうやらネット見てる限り、私の質問への答えは、
全国紙、しかも全くワケの判らん全国紙にさえ載ってなくて、
最近(それもここ2・3日)発行された学術書にしか載ってないらしいんです。
そして、島の新聞には、その前提になる基礎知識の「き」の字も載ってない。
だけど、それが沖縄にないか、ったら全然違います。あるのは事実です。
まさしく島の新聞がレッテル張られて疎外されるのと同じ構図で無視されてます。
そして、「なんだかワケの判らない怖ろしい何か」
が蠢いてる(事実だと思いますが)感覚だけがある。
それを記事にして新聞に載せることは広告にもなってしまう危惧もまたあるわけで、
それを避けようとする島の新聞の考えも判らないではないです。
またしてもバランス。はあ~。もう難儀です。
そんなことを発想の糸口にして、そこから色んなことを考えました。
頭の中に、これまで見聞きした情報の断片が折り重なって出来る
曼荼羅みたいなものがあるのは判ってて、
それを文章化することを目指したんですが、どうにも上手くいきません。限界。
なので、これは、またゆっくりと。
それでは……。
Posted by ブーウジぬイナグングヮ at 2015年04月11日 10:23