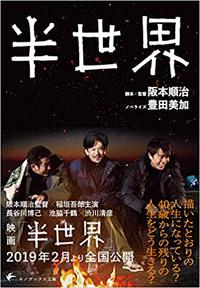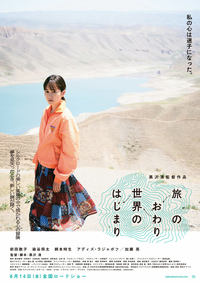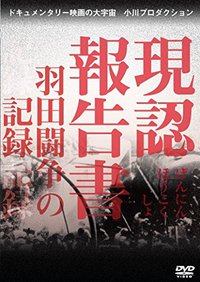2016年09月30日
『オーバー・フェンス』

アリストテレスが『詩学』で定義した「カタルシス」を再確認してしまった。この作品におけるカタルシスの表現、その映画的技法について思わずうなってしまったからだ。
プロットはこんなかんじだろうか。主人公は函館の職業訓練校で土木実習を受けている中年男性の白岩(オダギリジョー)。かつて東京で妻子持ちの生活を送っていたが、仕事に忙しくしているうちに妻が育児ノイローゼとなり、家庭を壊してしまった過去をもつ。函館は郷里だが実家には寄り付かず、アパート住まいの日々を失業手当で食いつなぎ、先の見えない単調な生活を送っている。職業訓練校の同僚代沢(松田翔太)に誘われ入ったキャバクラで出逢った、全身を使って鳥の形態模写をする個性的なホステス聡(さとし)(蒼井優)と互いに惹かれあう。精神安定剤を服用し不安定な聡と白岩は衝突し仲直りを繰り返す。「わたしは壊れているから」と自嘲する聡に対し、「おれは壊す方だ」と省みる白岩(このセリフのやりとりで、なぜお互いが惹かれ合うかが表現される)。職業訓練校のソフトボール大会が開かれ、聡のためにホームランを打つと約束していた白岩のバッターボックス。すでに劣勢な試合展開のなか、ギリギリで駆けつけた聡に見守られながら、白岩のフルスイングは打球を青空に向けかっ飛ばす。
カタルシスを感じたのは、ラストシーンの白岩の打席である。白岩のフルスイング、快音、青空(打球は描かれない)のカットつなぎ。快音と青空のあいだに、驚いた表情で打球の行方を目で追う職業訓練校の仲間たち(と聡)のそれぞれの顔とそれぞれの日常生活の一コマがインサートされる。この瞬間、観る者は、この映画が白岩と聡のラブストーリーであるだけでなく、負け犬の男たちの「オーバー・フェンス」、すなわち再生の可能性の物語であることを発見する。そして瞬時にしてそこにカタルシスを感じる。
それを可能にするのが、丹念にしかも淡々と表現される男たちのキャラクター造形と各々の役者の味のある演技であることを、やはり指摘しなければならない。世代はバラバラ、しかしその社会的不適合性のみ共通する男たちを観るにつけ、およそ共感を得ることは難しいはずだ。そもそも訓練生も、いや教官ですら本気で大工になろう(させよう)と思ってなどいないというしらけた雰囲気が全編漂っている。それなのに、というかそうであるがゆえに、彼らの「ダメさ」という価値観がラストの数カットで宙に浮いてしまう。そこで気づかされることは、社会的不適合といってみたが、その不適合性の割合は少数ではなく、実はあなたやわたしも潜在的にそうであることを薄々知っていたという認知の解放性であろう。
ところで、ソフトボール大会で主人公が起死回生のホームランを打つという、遠い昔に見た青春ドラマのようなクライマックスの設定に心を動かされるなど今更あってはならない。そもそも、ダメな男たちは青春ドラマのようにソフトボール大会に向け熱心に練習に打ち込んできたわけでもない。訓練の合間の喫煙室で教官の悪口や女の話をするしかない、そんなフツーにダメな男たちを映画は淡々と描くのみなのだから。つまり、プロットとして、映画はソフトボール大会をクライマックスに設定するような展開を用意していない。しかしながらそこにカタルシスを感じてしまう。なんともやられてしまった、という以外ない。
そんな(隠された)男たちの物語とは同調もせず、かといって反発もせず、蒼井優の身体性とクローズアップは単独者としてそこに居ることの標章としてあまりにも力がある。
『オーバー・フェンス』
監督:山下敦弘
出演:オダギリジョー/蒼井優/松田翔太/北村有起哉/満島真之介/松澤匠/鈴木常吉/優香
2016年作品
劇場:テアトル新宿
Posted by 24wacky at 10:31│Comments(0)
│いつか観た映画みたいに