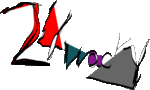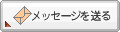2018年07月14日
『自分ひとりの部屋』ヴァージニア・ウルフ

本書はイギリスで男女平等の参政権が認められた1928年に、著者がケンブリッジ大学の女子学生たちに向け開催された「女性と小説(フィクション)」というタイトルの講演を下敷きにしている。語り手として匿名の女性を設定、いわば入れ子構造のメタフィクションという仕掛けがなされているところがいかにも著者らしい。「女性が小説を書こうと思うなら、年収五百ポンドのお金と自分一人の部屋を持たねばならない」(第一章)という有名な一節を引用し、「女性と小説」=「政治と文学」というパラダイムをそこに見出すことは、なるほど間違ってはいない。しかし、両性具有について独自の見解が述べられた後半を読めば、そのパラダイムがいかにも硬直していることがわかる。
第六章は10月のロンドンの朝、語り手が窓から外を眺める場面から始まる。ピタリと人通りがなくなった一瞬の後、それぞれ別方向から「運ばれて」きた男と女とタクシーが窓の真下に一同し、男女はタクシーに乗り、「タクシーはまるで流れに乗せられたかのように、どこかに向かって滑り出」す(167ページ)。語り手はこの「ごくありふれた」光景に対し、「二人の満足感を伝える力」を感じ、「心の緊張感が解けるみたいだ」と捉える。そこから「一方の性別だけをもう一方の性別と切り離して考える」ことの限界を感じ、男女の調和こそ完璧な幸福であると持論を展開する。男性には女性の力があるし、女性には男性の力がある。両者が調和をなして、精神的に協力している状態が理想である、と。
ここで語り手はコールリッジの〈偉大な精神は両性具有である〉という言葉を引用し、その意味するところを、「片方の性別だけの精神と比べると、男女の区別をつけない傾向にあり」、その精神は「共鳴しやすく多孔質であ」り、「何に妨げられることもなく感情を伝達する。無理をしなくても創造的で、白熱していて未分割である」(170ページ)と定義する。両性具有的な作家の例として、シェイクスピアの他、キーツ、スターン、クーパー、ラム、コールリッジなどを挙げる。他方で、男性側の頭脳だけを使って書かれた文章は、「心が二つの小部屋に分離しており、物音一つ、一方の小部屋からもう一方の小部屋に伝わってきません」(175ページ)と表現する。
しかし、こうしたことの(政治的)責任は、一方の性別だけにあるのではなく、もう一方の性別にもあると語り手が付言している部分には注意を要する。ウルフの『船出』『灯台へ』といった作品では、そのサロン的な会話の中でときに政治談義が展開される。女性参政権という主要なイシューに関して、あるいはそれが明示されない議論においても、男性の頭脳だけを使った議論、女性だけの頭脳を使った議論と併記されるように、女性のなかで両義的な、「両性具有的な」感情が発せられる場面がある。いわば、それは男女の調和の前の混沌ともいえる。
さらにそれらの作品において「両性具有的な」「意識の流れ」がときに不安定さを読者に与えることも印象に残る。その点では、本書でも両性具有についての議論の途中に挿入される(ウルフは「挿入」するという意図は持たなかっただろう。それこそが「意識の流れ」的な手法であるのだから)「精神論」は、いささか唐突であるだけに読み飛ばすわけにはいかない。そこで女性に時折あることとして、「急な意識の分裂に驚く」との告白がなされた後、語り手は述べる。
明らかに心はいつも焦点を変えていて、世界をさまざまに異なる視点から眺めています。でもこれらの心の状態の中には、自発的にそうなったとしても比較的不安定なものもあるようです。そうした不安定な状態でいると、無意識に何かを抑圧していることになり、次第にその抑圧も努力を要するようになります。しかし、何も抑圧する必要がなく、努力しないで継続できるような心の状態があるのかもしれません。
(169ページ)
まさにウルフの諸作品の特徴を記した記述として(も)読めてしまう。整理しよう。ウルフにとって、「女性と小説」というアクチュアルな宿命には、精神分析的な「不安定さ」が伴う。後者が前者からの「逃走」手段なのか、それとも「闘争」のための不可欠な戦略なのか。ドゥルーズ=ガタリが『千のプラトー』でたびたびウルフを参照しているのは、この間隙がどうにも気になって仕方なかったからだろう。
『自分ひとりの部屋』
著者:ヴァージニア・ウルフ
翻訳:片山亜紀
発行:平凡社ライブラリー
発行年月:2015年8月25日
2018/06/30
明日灯台に行くことを心待ちにする幼い息子と息子を愛おしむ美しい母親、他愛ないそのやり取りに横やりを入れる不機嫌な哲学者=父親。イギリス人家庭を題材にした小説はそのような情景から始まる。場所はスコットランド孤島の別荘。時代は第一次大戦の頃。母親ラムジー夫人を中心に、別荘に集まる数人の関係を素描…
2018/06/13
モダニズム作家ウルフのデビュー作本邦初訳。ロンドン生まれで世間知らずの若い娘レイチェルを主人公としたビルドゥングスロマン。南米に向けた船上での人々との出会い。到着後のホテルとヴィラ二カ所を拠点に、原住民の棲む奥地へと進む船の小旅行。アメリカへと覇権が移ろうとする大英帝国没落の予兆とオリエンタ…
2018/05/20
冒頭からリゾームという言葉のイメージの噴出に息が切れそうになる。リゾームとは樹木やその根とは違い点と点を連結する線からなる。それは極限として逃走線や脱領土化線となる。樹木は血統であるが、リゾームは同盟である。リゾームは多様体である。リゾームは生成変化である。リゾームとは定住性ではなく遊牧性で…
2018/02/18
ドゥルーズ=ガタリ連名による著作『アンチ・オイディプス』(1972年)、『千のプラトー』(1980年)、『哲学とは何か』(1991年)は、いずれも資本主義打倒のための書である。三作は利害の闘争から欲望の闘争へという戦略(ストラテジー)において共通するが、戦術(タクティクス)が各々で異なる。『アンチ・オイ…
Posted by 24wacky at 19:59│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした