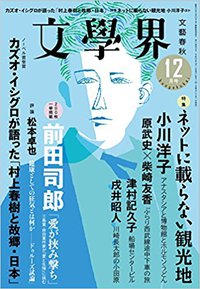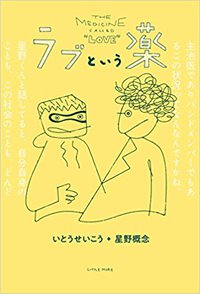2019年03月03日
『技法以前 べてるの家のつくりかた』向谷地生良
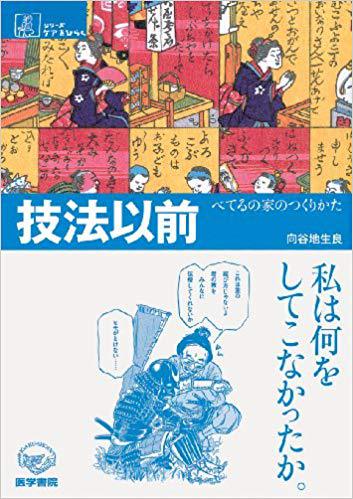
統合失調症など危機的な状況を生きる当事者とその家族。当事者は親と口をきかず部屋に閉じこもる。ときに上がる大声や暴力から、苦しみを回避したいというメッセージが著者には透けて見える。当事者と家族が対立しているように見える構造を一度ばらばらにして、当事者の振る舞いが、結果として全く正反対の暴言や暴力に結びついてしまうからくりを紐解いていく。その時に大事なことは《信じる》こと。
だが、《信じる》ことはたんに《信用する》こととは違うと著者はいう。
《信用する》とは、あくまでもこの目で実際に見て聞いて確認して、「信用に値する現実」を担保としてはじめて私たちがとりうる態度である。そこには、さまざまな打算や駆け引きが介在する。それに対して《信じる》という態度は、目に見えず、将来的な好転や可能性を導き出すのは困難であるという状況のなかで、にもかかわらず私たちが希望をもって見ようとするような振る舞い方である。
つまり、信じることの営みにとって一番大切なのは「根拠なく信じる」姿勢である。
(51〜52ページ)
とはいえ、「根拠なく信じる」姿勢にも根拠はある。それは、困難な状況のなかで、「問題になっていること」ではなく、問題の背後にある「可能性の側面」を見通す力である。荒波にもまれる航海の先に見える灯台のように。
それを見通すための技術として、「言葉を変えていくこと」がある。たとえば、「人と会いたがらない」ではなく「人と会いたいのに会えない」と変える。「支援しに来た」ではなく「相談しに来た」と変える。そうすることで、当事者の振る舞いが変わる。
著者にとって、《信じる》とき、根拠はない。しかし、《信じよう》という姿勢をとれば、言葉が変わる。それは「暗闇の跳躍」である。さらに「根拠なく信じる」姿勢は、大澤真幸の〈自由〉をめぐる議論における「第三者の審級」を、私には想起させられる。「第三者の審級」は灯台であるのか。
『技法以前 べてるの家のつくりかた』
著者:向谷地生良
発行:医学書院
発行年月:2009年11月1日
2018/10/23
社会が多様な人々に対して開放的であろうとすると、自由への制限は大きくなる、言い方を変えれば自由と開放(平等)は矛盾するとされる一般的な考え方を再考する「第3章 〈公共性〉の条件──自由と開放をいかに両立させるのか」を、私は沖縄の政治的状況と関連させて読む。カント、マルクス、アーレント、ハーバーマ…
2018/12/08
対談─来るべき当事者研究─当事者研究の未来と中動態の世界熊谷晋一郎+國分功一郎 興味深い二人の対談において、2つの対立軸を乗り越える方向性が確認できた。1つは、能動/受動の対立軸、2つは、運動と研究の対立軸である。 まずは、能動/受動の対立軸について。 熊谷晋一郎は國分功一郎著『中…
2018/10/08
精神病理学には3つの立場がある。記述精神病理学、現象学的精神病理学、そして力動精神医学(精神分析)という。 ヤスパースに始まる記述的精神病理学は、患者に生じている心的体験(心の状態や動き)を的確に記述し、命名し、分類する。その際、「了解」という方法がとられる。「了解」とは、医師=主体が患…
2018/01/02
今もっとも注目する松本卓也論考の概要。 ドゥルーズは「健康としての狂気」に導かれている。その導き手として真っ先に挙げられるのが、『意味の論理学』(1969年)におけるアントナン・アルトーとルイス・キャロルであろう。アルトーが統合失調症であるのに対し、キャロルを自閉症スペクトラム(アスペルガー症…
2017/01/05
本書は、ドゥルーズとガタリやデリダといったポスト構造主義の思想家からすでに乗り越えられたとみなされる、哲学者で精神科医のラカンのテキストを読み直す試みとしてある。その核心点は「神経症と精神病の鑑別診断」である。ラカンは、フロイトの鑑別診断論を体系化しながら、神経症ではエディプスコンプレクスが…
2016/11/20
ドゥルーズは認知症についてどう語っていたかという切り口は、認知症の母と共生する私にとって、あまりにも関心度の高過ぎる論考である。といってはみたものの、まず、私はドゥルーズを一冊たりとも読んだことがないことを白状しなければならない。次に、この論考は、引用されるドゥルーズの著作を読んでいないと認識が…
2016/11/19
「水平方向の精神病理学」とは、精神病理学者ビンスワンガーの学説による。彼によれば、私たちが生きる空間には、垂直方向と水平方向の二種類の方向性があるという。前者は「父」や「神」あるいは「理想」などを追い求め、自らを高みへ導くよう目指し、後者は世界の各地を見て回り視野を広げるようなベクトルを描く。通…
2019/01/06
中学に入学し、初めて英語を学び、能動態と受動態という2つの態がある(それだけしかない)と教えられた。だが、日常的に用いている言動として、この2つでは括れない場合があるのではという漠たる疑問があった。本書によれば、中動態という態が、古代からインド=ヨーロッパ語に存在したという。中動態というと、…
2018/10/09
統合失調症を病む者の寛解期初期の状態を、著者は角を出しはじめた蝸牛にみたてる。社会の中に座を占めようとするその行動を探索行動と表現する。医師や家族そして支援者、いや、社会は、彼ら個々の行動の成否を性急に判断したり、説教したりすることに慎重になるべきだ、と。 そこから著者には次の問いが生ま…
2018/10/08
精神病理学には3つの立場がある。記述精神病理学、現象学的精神病理学、そして力動精神医学(精神分析)という。 ヤスパースに始まる記述的精神病理学は、患者に生じている心的体験(心の状態や動き)を的確に記述し、命名し、分類する。その際、「了解」という方法がとられる。「了解」とは、医師=主体が患…
2017/02/12
『atプラス 31号 2017.2 【特集】他者の理解』では、編集部から依頼されたお題に対し、著者はそれが強いられているとアンチテーゼを掲げる。「他者の理解」こそ、共生社会にとって不可欠ではないのか。いったいどういうことか? 急増する発達障害、ASD(自閉スペクトラム症)は、最近になって急に障害者とされ…
2018/06/07
自分のバンドのサポート・ギタリストが精神科の主治医。それがいとうせいこうと星野概念の関係である。患者と主治医がいつものカウンセリングを再現するような対談。企画したいとうせいこうのねらいは、ハードルが高いカウンセリングになかなか来られない人たちのために「ちょっとした薬」のようなものを提示したい…
Posted by 24wacky at 10:12│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした