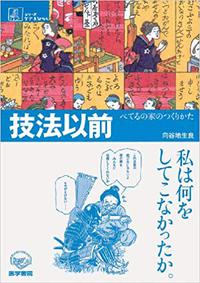2019年03月24日
『暇と退屈の倫理学 増補新版』國分功一郎

ウサギ狩りをする人は、ウサギが欲しいから狩りをするのではなく、気晴らしが欲しいからそうする。つまり、ウサギは〈欲望の対象〉であるが〈欲望の原因〉ではない。それにもかかわらず、人は両者を取り違える。
「暇」と「退屈」は、しばしば混同して使われる。暇とは客観的な条件に関わっているのに対し、退屈は主観的な状態のことをいう。暇な人間が必ず退屈するわけではないし、逆に、退屈しているとき、その人が必ず暇というわけでもない。
浪費と消費は異なる。浪費とは、必要を超えて物を受け取ることであり、贅沢の条件である。人に満足を与え、どこかで限界に達する。一方、消費は物を受け取るわけではなく、物に付与された観念や意味を消費する。そのため限界がなく、決して満足をもたらさない。
消費社会では退屈と消費が相互依存している。終わらない消費は退屈を紛らすためのものだが、同時に退屈を作り出す。退屈は消費を促し、消費は退屈を生む。そこに暇が入り込む余地はない。
消費社会の「疎外」とは、人が終わりなき消費ゲームに参入することを強制されること、言い換えれば、自分で自分のことを疎外している状態をいう。
疎外された状態は、「人間はこのような状態にあるべきではない」という気持ちを人に起こさせる。ここまでは問題ないが、さらに「なぜかといえば、人間はそもそもはこうではなかった」と考えるようになる。つまり、「疎外」は「本来性」を思い起こさせる。しかし、本来性は強制的であり、そこから外れる人を排除するので危険である。
ハイデガーは退屈を三つに分類した。何かによって退屈させられること(退屈の第一形式)、何かに際して退屈すること(退屈の第二形式)、そして「なんとなく退屈だ」(退屈の第三形式)とに。「なんとなく退屈だ」と感じる私たちは、あらゆる可能性を拒絶されている。そしてそうであるがゆえに、自らが有する可能性に目を向けるよう仕向けられている。
第二形式こそ、退屈と切り離せない生を生きる人間の姿そのものである。人間は普段、第二形式がもたらす安定のなかに生きているが、不意に「なんとなく退屈だ」の声が大きく感じられる。たとえば、その声に圧倒され将来を思い悩む学生は、「資格がなければ社会では認めてもらえない」という世間の声に耳を傾け、資格取得という「決断」になびく。その方が楽だからだ。人間はしばしばこの声に悩まされるが、気晴らしと退屈が絡み合った第二形式の退屈を生きることで、それをなんとかやり過ごしている。
『暇と退屈の倫理学 増補新版』
著者:國分功一郎
発行:太田出版
発行年月:2015年3月13日
2019/03/03
統合失調症など危機的な状況を生きる当事者とその家族。当事者は親と口をきかず部屋に閉じこもる。ときに上がる大声や暴力から、苦しみを回避したいというメッセージが著者には透けて見える。当事者と家族が対立しているように見える構造を一度ばらばらにして、当事者の振る舞いが、結果として全く正反対の暴言や暴…
2019/01/06
中学に入学し、初めて英語を学び、能動態と受動態という2つの態がある(それだけしかない)と教えられた。だが、日常的に用いている言動として、この2つでは括れない場合があるのではという漠たる疑問があった。本書によれば、中動態という態が、古代からインド=ヨーロッパ語に存在したという。中動態というと、…
2018/12/08
対談─来るべき当事者研究─当事者研究の未来と中動態の世界熊谷晋一郎+國分功一郎 興味深い二人の対談において、2つの対立軸を乗り越える方向性が確認できた。1つは、能動/受動の対立軸、2つは、運動と研究の対立軸である。 まずは、能動/受動の対立軸について。 熊谷晋一郎は國分功一郎著『中…
2017/09/04
エビデンス主義は多様な解釈を許さず、いくつかのパラメータで固定されている。それはメタファーなき時代に向かうことを意味する。メタファーとは、目の前に現れているものが見えていない何かを表すということ。かつては「心の闇」が2ちゃんねるのような空間に一応は隔離されていた。松本卓也がいうように、本来だ…
Posted by 24wacky at 09:57│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした