2015年10月03日
「沖縄の米軍基地」を読む2
「日本人よ基地を引き取れ」という要求が沖縄で公然と上がっている。著者は「日本人」として応答しなければならないとし、これにイエスと答える。私は同じ「日本人」の1人として、その論理展開のほとんどに同意する。とりわけ日本の戦後リベラルを批判する次の箇所には。「『本土』の反戦平和運動も、戦後民主主義の政治学も、沖縄からの県外移設要求によって従来の姿勢の全面的再検討を迫られているのではないか、と私は思う」(140ページ)。
「本土の反戦平和運動」を私の解釈でいえば、憲法9条があるから戦後日本は平和でいられた、だから戦争を忌避し憲法を守ろうという立場である。実際は憲法より上位にある日米安保条約があることで米軍の存在を認め、軍事に関わる負の要素の大部分を沖縄に押しつけてきたことによる「平和」に過ぎないというのに。そのことに触れずに沖縄に「連帯」を求める独善性は運動として致命的である。この立場の「日本人」は、沖縄とのあいだにある差別的で非対称的な関係性、そして自分たちの当事者性を自覚しないで済ませている。私はこの当事者性を議論の前提とする。
しかしながら同時に、「基地を引き取れ」という要求だけが「沖縄からの問いかけ」ではないだろうと考える。それに対するイエスかノーが唯一の「応答」とはいえないと思わざるをえない。なぜそういうかといえば、それは私のわずかな基地反対運動その他の現場での経験を想起することによる。
直接阻止行動は、沖縄防衛局職員、その指揮下の業者などが工事を強行しようとするのに対し非暴力で相対する。その膠着(こうちゃく)した状態がピークに達した瞬間に、県警が市民を(時に国政議員をも)力づくで排除する。その瞬間日常では視えにくい国家権力の暴力性が顕(あら)わとなる。
それを目前にした私を支配するのはただただ恐怖心である。痛くないだろうか。逮捕されたらどうしよう…。それでも数の力で工事は強行されてしまう。悔しい。心身共に疲れ果て家に帰る。そして明日はどうしようか思案する。行きたくない。それでも行く。そしてびくびくしながら現場に立つ。
向こう側から制服を着た能面たちが隊列を組んで近づいてくるのを目にしながら、「自分はどうしてここにいるのだろう?」と、呆(ほう)けたように問う。曖昧な私に明確な答えは出ないが、しいて言えば「殺すな!」「殺されるな!」という、誰だかわからない他者からの命令に従っているという気がする。
私はこの思いがそこで共に行動している人々の多くに共有されている、だからそれも「沖縄からの問いかけ」であるといいたいのではない。図らずも集まってしまった雑多な人々に揉(も)まれながらそこにいる私の外部の声として、そこで唐突に聞こえるとしかいいようがない。ウチナーンチュでもヤマトンチュでもない単独者としての声。私はそれをも「沖縄からの問いかけ」とみなす。それは「反戦平和」を刷新し、ヤマトであれどこに対してであれ「応分の負担」を求めることを拒む。
現場には「基地を引き取れ」という立場の人たちを含め、微妙に異なるさまざまな考えや感情を持つ人たちがいる。沖縄の人びとの他に「日本人」もそれ以外の民族もいる。現場以外にもいる。現場に座り込むことだけが正しいわけではない。離れた「本土」にいる知識人に対し現場至上主義からいっているのではない。
本書の「県外移設論」のポイントは、日米安保条約を支持するならば、米軍基地は「本土」で「応分の負担」をするべきというものである。「~ならば」を確証するために全国紙の世論調査が引用され、「日本人」の8割が日米安保を支持していると指摘される。確かにそのように読むことが可能である。ただし確認すべきは、60年代の安保闘争以降、日本の政治史において日米安保条約が全国的な議論となったことはなく、むしろそれを忘却することで受動的に認めてきたという方が正確ではないだろうか(その程度のことは著者とて承知のことだろう)。
安保の是非について全国的な議論をすること。そのプロセスを経ずに一足飛びに引き受け運動をした場合、「思考停止」状態の「日本人」は感情的な反発を強固にするのみだろう。「それまで沖縄は待たねばならないのか?」という切実な意見も本書にはある。しかし実際の運動をしようとすれば、そうならざるをえないのではないか。
私は日本全体で日米安保の是非について議論をする試みを模索したい、基地の引き取り論を退けずに。同時にさまざまな「現場」で「殺すな!」という命令に従う行動を続けるだろう。「基地を沖縄に押しつけているのは誰だ?」「私たちだ!」。そんなコール&レスポンスが官邸前デモで聞こえることを想像しながら。この凡庸でどっちつかずの「決定」が、現在の私の応答責任である。
(了)
【沖縄タイムス文化欄 2015年10月2日掲載】
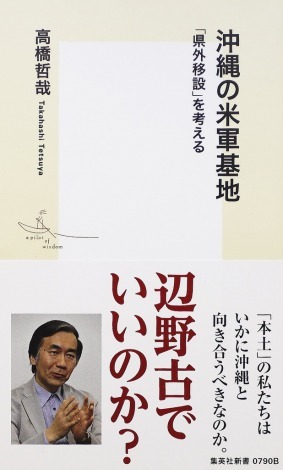
「本土の反戦平和運動」を私の解釈でいえば、憲法9条があるから戦後日本は平和でいられた、だから戦争を忌避し憲法を守ろうという立場である。実際は憲法より上位にある日米安保条約があることで米軍の存在を認め、軍事に関わる負の要素の大部分を沖縄に押しつけてきたことによる「平和」に過ぎないというのに。そのことに触れずに沖縄に「連帯」を求める独善性は運動として致命的である。この立場の「日本人」は、沖縄とのあいだにある差別的で非対称的な関係性、そして自分たちの当事者性を自覚しないで済ませている。私はこの当事者性を議論の前提とする。
しかしながら同時に、「基地を引き取れ」という要求だけが「沖縄からの問いかけ」ではないだろうと考える。それに対するイエスかノーが唯一の「応答」とはいえないと思わざるをえない。なぜそういうかといえば、それは私のわずかな基地反対運動その他の現場での経験を想起することによる。
直接阻止行動は、沖縄防衛局職員、その指揮下の業者などが工事を強行しようとするのに対し非暴力で相対する。その膠着(こうちゃく)した状態がピークに達した瞬間に、県警が市民を(時に国政議員をも)力づくで排除する。その瞬間日常では視えにくい国家権力の暴力性が顕(あら)わとなる。
それを目前にした私を支配するのはただただ恐怖心である。痛くないだろうか。逮捕されたらどうしよう…。それでも数の力で工事は強行されてしまう。悔しい。心身共に疲れ果て家に帰る。そして明日はどうしようか思案する。行きたくない。それでも行く。そしてびくびくしながら現場に立つ。
向こう側から制服を着た能面たちが隊列を組んで近づいてくるのを目にしながら、「自分はどうしてここにいるのだろう?」と、呆(ほう)けたように問う。曖昧な私に明確な答えは出ないが、しいて言えば「殺すな!」「殺されるな!」という、誰だかわからない他者からの命令に従っているという気がする。
私はこの思いがそこで共に行動している人々の多くに共有されている、だからそれも「沖縄からの問いかけ」であるといいたいのではない。図らずも集まってしまった雑多な人々に揉(も)まれながらそこにいる私の外部の声として、そこで唐突に聞こえるとしかいいようがない。ウチナーンチュでもヤマトンチュでもない単独者としての声。私はそれをも「沖縄からの問いかけ」とみなす。それは「反戦平和」を刷新し、ヤマトであれどこに対してであれ「応分の負担」を求めることを拒む。
現場には「基地を引き取れ」という立場の人たちを含め、微妙に異なるさまざまな考えや感情を持つ人たちがいる。沖縄の人びとの他に「日本人」もそれ以外の民族もいる。現場以外にもいる。現場に座り込むことだけが正しいわけではない。離れた「本土」にいる知識人に対し現場至上主義からいっているのではない。
本書の「県外移設論」のポイントは、日米安保条約を支持するならば、米軍基地は「本土」で「応分の負担」をするべきというものである。「~ならば」を確証するために全国紙の世論調査が引用され、「日本人」の8割が日米安保を支持していると指摘される。確かにそのように読むことが可能である。ただし確認すべきは、60年代の安保闘争以降、日本の政治史において日米安保条約が全国的な議論となったことはなく、むしろそれを忘却することで受動的に認めてきたという方が正確ではないだろうか(その程度のことは著者とて承知のことだろう)。
安保の是非について全国的な議論をすること。そのプロセスを経ずに一足飛びに引き受け運動をした場合、「思考停止」状態の「日本人」は感情的な反発を強固にするのみだろう。「それまで沖縄は待たねばならないのか?」という切実な意見も本書にはある。しかし実際の運動をしようとすれば、そうならざるをえないのではないか。
私は日本全体で日米安保の是非について議論をする試みを模索したい、基地の引き取り論を退けずに。同時にさまざまな「現場」で「殺すな!」という命令に従う行動を続けるだろう。「基地を沖縄に押しつけているのは誰だ?」「私たちだ!」。そんなコール&レスポンスが官邸前デモで聞こえることを想像しながら。この凡庸でどっちつかずの「決定」が、現在の私の応答責任である。
(了)
【沖縄タイムス文化欄 2015年10月2日掲載】
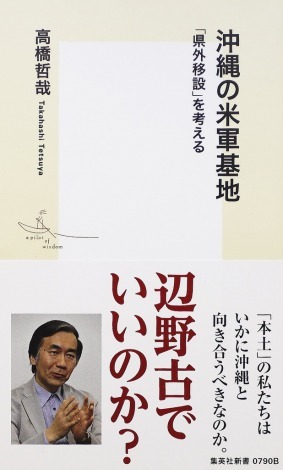
Posted by 24wacky at 10:00│Comments(2)
│メディア寄稿
この記事へのコメント
通りすがりにお初に書き込みさせていただきます
本土から移住された方々、地縁が無いのにもっと声をあげて欲しいな〜と思います。
有名無名問わず…
普天間○○、辺野古○○、埋立○○の見出しのニュースが毎度映されても、沖縄以外の視聴者にはインパクトなくて通り過ぎるだけじゃないかしらと思います
はっきり、新基地建設工事と言っちゃって欲しいです
○地議員だったか、誰かが辺野古出来ても小さすぎて代替になんかならない、というようなお話されてました。私は日米合同演習場になるような気がしてなりません。
幼稚ですみません
本土から移住された方々、地縁が無いのにもっと声をあげて欲しいな〜と思います。
有名無名問わず…
普天間○○、辺野古○○、埋立○○の見出しのニュースが毎度映されても、沖縄以外の視聴者にはインパクトなくて通り過ぎるだけじゃないかしらと思います
はっきり、新基地建設工事と言っちゃって欲しいです
○地議員だったか、誰かが辺野古出来ても小さすぎて代替になんかならない、というようなお話されてました。私は日米合同演習場になるような気がしてなりません。
幼稚ですみません
Posted by 栗原みかん at 2015年10月29日 09:15
栗原みかんさん
初めまして、コメントありがとうございます。
>本土から移住された方々、地縁が無いのにもっと声をあげて欲しいな〜と思います。
なるほど。一方で「反対運動はナイチャーばかりでウチナーンチュが入りにくい」という声もあります。どちらにせよ批判される(笑)
>辺野古出来ても小さすぎて代替になんかならない
これはまったくの認識不足でしょう。辺野古新基地建設は軍港施設が増設されバージョンアップされた恒久基地の予定です。日米合同演習場になるのはご指摘の通りですね。
初めまして、コメントありがとうございます。
>本土から移住された方々、地縁が無いのにもっと声をあげて欲しいな〜と思います。
なるほど。一方で「反対運動はナイチャーばかりでウチナーンチュが入りにくい」という声もあります。どちらにせよ批判される(笑)
>辺野古出来ても小さすぎて代替になんかならない
これはまったくの認識不足でしょう。辺野古新基地建設は軍港施設が増設されバージョンアップされた恒久基地の予定です。日米合同演習場になるのはご指摘の通りですね。
Posted by 24wacky at 2015年10月30日 20:41















