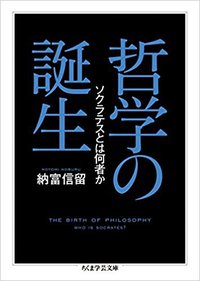2017年09月20日
ソクラテスの謎とイソノミア『哲学の起源』柄谷行人
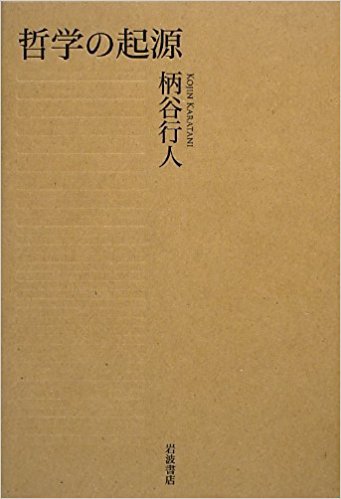
ソクラテスが告発された理由は、要約すると次の三点になる。第一に、ポリスが認める神々を認めない、第二に、新しい神(ダイモン)を導入している、そして第三に、若者たちを堕落させている。これらの嫌疑はまったく無根拠とはいえない。
しかし、ソクラテスがアテネの社会規範に対して挑戦的な存在とみなされたのはそれらの理由からではない。その根本的な理由は、ソクラテスがアテネにおいて公人として生きることの価値を否定したことにある。当時のアテネにおいては、市民とは公人として国事に参与する者を指す。公的な場で上手に言論(ロゴス)を操る技術を得るために、富裕市民は子弟に弁論術を習わせた。そのための教師がソフィストである。対して、私人であることは非政治的である。外国人、女、奴隷などがその例である。
ソクラテスの謎は、公人となることなく私人として「正義のために戦う」姿勢にあった。そもそも私人であることは非政治的であるのだから、これは背理といえる。価値転倒である。
ソクラテスを告発した者も擁護した者も、ソクラテスの謎を理解できなかった。そもそもソクラテス自身でさえそれがよくわかっていなかった。そのことをソクラテスは「ダイモンからの合図」に従ったといった。「公人として行動すべきでない」という命令もそのうちの一つである。
公人と私人の区別のない社会。それがかつてあったのがイオニアのイソノミアである。ソクラテスはそのことを知らず、ダイモンの合図を通して受けとった。
私の考えでは、ソクラテスにダイモンの合図として到来したのは、「抑圧されたものの回帰」(フロイト)である。では、「抑圧されたもの」とは何か。いうまでもなく、イオニアにあったイソノミアあるいは交換様式Dである。したがって、それが「意識的自覚的」なものでありえないのは当然である。それはソクラテスにとって強迫的であった。このような人物において、イオニア哲学の根源にあったものが「回帰」したのである。
(196ページ)
では、公人としてでなく私人として戦うとは、具体的にどうすればよいのか。ソクラテスは、アゴラ(広場=市場)に行って、誰かれとなく話しかけ、問答した。そこには決して公人となりえないような人々がいた。
問答とは、決して聴衆全体に向かわず、一人一人に話しかける方法である。その場でソクラテスは問うだけであり、どんなに相手が多くても、一人一人との問答になる。
そのやり方は、相手の命題を肯定した上で、そこから反対の命題が引き出せることを示す(産婆術)。人に教えるのではなく、人が自ら真理に到達するのを助けるという手法である。
ここで柄谷は、ソクラテスの問答が、通常「対話」と呼ばれるものとは異なることに注意を向ける。なぜなら、ソクラテスは問うだけであり、異なった意見をもった者が話し合い、説得し合うという民主主義のルールは無視しているのだから。ソクラテスの問答法が書かれたプラトンの著作は「対話篇」と呼ばれるのだが。《プラトンにおいては、問答は一定の終わり(目的)に向かって進む。そのような対話は、実際には自己対話、つまり、内省であって、他者との対話ではない。他者との対話がこんなに都合よく完結するはずがないのだ》(200ページ)。
一定の終わり(目的)に向かって進む予定調和がない問答は、先が予測できない。相手の虚偽を論破するその強引さゆえに、時に相手は怒り狂い殴りかかることもある。
これは何かに似ていると思ったら、精神科医とクライアントのセッションを思い出した。柄谷の次の指摘は示唆的である。
ソクラテスの「対話」──そう呼んでいいなら──の特徴は、対話者の関係性の非対称性にある。それに類似するのは、フロイトが創始した精神分析における分析医と患者の関係である。これは「対話」療法と呼ばれるが、通常の対話とは異なる。患者の「自覚」を引き出す産婆術に近い。逆に、ここからふりかえると、ソクラテスの問答法が相手の側に、過度の転移や抵抗をもたらしたということが想像できる。その結果がソクラテスの死刑に帰結したといえる。
(201ページ)
『哲学の起源』
著者:柄谷行人
発行:岩波書店
発行年月:2012年11月16日
2017/09/19
「自由」が「平等」をもたらすイソノミア。その無支配という概念を生んだイオニアではどのような哲学があったのか。それを語るには主としてプラトンやアリストテレスによる史料が残るのみであり、彼らの見方がそのまま哲学史の通説となってきたことに注意すべきである。いわく、イオニア学派が外的自然を探求したの…
2017/09/18
「民主主義ってなんだ?」と問われる前に、柄谷行人はそれに答えていた。哲学に関するいくつかの通説を刺激的に覆し、この間探求を続けてきた資本と国家を超える交換様式と遊動性の理論に強引なまでにつなげるというやり方で。 デモクラシーの語源はdemos(大衆・民衆)とcracy(支配)、すなわち多数決原理に…
2017/08/31
「哲学」とはなんだろうか。わたしは「哲学」のなにが気になって本書を手に取るのか。「第1章 生の逆転─『ゴルギアス』─」末尾で、著者は早くもこの答えに応答している。「哲学」とは「生き方を言論で吟味すること」である、と。師・ソクラテスを登場させた数々の対話篇というテクストは、登場人物たちと共に、読…
2017/08/20
ヨーロッパ哲学には3種類あることから本書は始まる。第一に、ソクラテスによる「問答」の哲学、「知の吟味」である。相互に相手の意見を批判的に検討する「討議」という伝統として現在まで伝わる。第二に、「上下に秩序づけられた二世界説」と「真理の探求」ないし「知の探求」である。ピュタゴラス、パルメニデス、…
2017/08/19
わたし(たち)が知っているソクラテスとはプラトンの著作に登場する「哲学者」のイメージとしてある。わたしはソクラテスに関心があるが、その関心の根拠を知りたく本書を手にした。そこでネックになるのがソクラテスはどこまでがソクラテスでどこからがプラトンの創造なのかという問題である。プラトン作は初期・…
2017/02/09
この20年とは、かつての文学批評の仕事をやめて哲学的なそれへ移る時期に重なる。しかし、その「変遷」が時系列でグラデーションのように読み取れる、というわけにはいかない。それが本書の魅力といえる。 ところで私が柄谷行人を読み始めたのは、記憶に間違えがなければ、当時住んでいた田無の図書館で借りた…
2009/09/21
「『世界共和国へ』に関するノート」のためのメモ その30柄谷行人著『クォータリーat』連載「『世界共和国へ』に関するノート」のためのメモを最後にとったのは2月のことだからずいぶんとたつ。無論その後も柄谷の連載は続いているのだが、生来の怠け癖から無精してしまった。およそ読む者のことを考慮しないゴチゴチ…
Posted by 24wacky at 20:43│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした