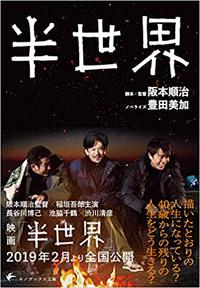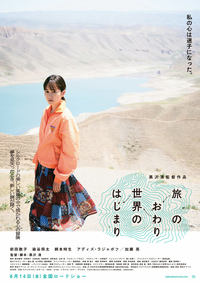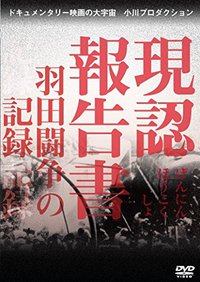2018年04月29日
『心と体と』エニェディ・イルディコー

ブダペスト郊外の食肉加工場で代理の検査官マーリア(アレクサンドラ・ボアブリー)が勤務を始めた。マーリアは他者とのコミュニケーションがうまくとれずに周りから孤立している。人生にやや疲れ片腕が不自由な上司エンドレ(ゲーザ・モルチャーニ)は彼女を気にかける。やがて二人は雪降る森を彷徨う雌雄一組の鹿になった同じ夢をみていることに気づく。
マーリアはコミュニケーション障害である。異常に記憶力が良い。音に敏感だ。細かいことにこだわる。接触過敏である。表情に乏しい彼女の微細な感情の変化、そして彼女の感受する世界を、映画は静かに丁寧に表現している。それは屠殺場のリアルな「機能美」と並列的かつ複数的に存する。
詩的な風景に点描される鹿と屠殺される牛、透き通るような美しさのマーリアと枯れた男のエンドレ、それらに聖と俗の対比を読み取ることは容易い。孤独な男女が同じ夢をみるというドラマ仕掛けを効果だけだと批判することもできなくはない。たとえそうだとしても、「マーリアは私だ」という強迫観念を観る者は抱き、それは圧倒的だ。そう、「コミュニケーション」なるものが決して自明ではないということも。
『心と体と』
監督:エニェディ・イルディコー
出演:アレクサンドラ・ボアブリー/ゲーザ・モルチャーニ
劇場:シネマカリテ
2017年作品
2017/09/08
対話を実践する試み「ミーティング文化」では、〈自分の言葉で語ること〉に価値が置かれる。 ハンナ・アーレントは「言葉と行為によって私たちは自分自身を人間世界のなかに挿入する」といった(『人間の条件』)。アーレントが面白いのは、ひとが言葉によって自分を表すときに、自分がいったいどんな自分を明…
2017/09/06
オープンダイアローグではポリフォニーが強調される。そこでは「すべての声」に等しく価値があり、それらが一緒になって新しい意味を生み出していくと。しかし、実際のミーティングにおいて、多くの声が響いていたとしても、それのみで既存の文脈がはらむ力関係を無効化できるものではない。 リフレクティング…
2017/09/05
オープンダイアローグの前提は「わかりあえないからこそ対話が可能になる」。コミュ力の対象は「想像的他者」、すなわち自己愛的な同質性を前提とする他者。その対極はラカン的な「現実的他者」で、決定的な異質性が前提となるため対話もコミュニケーションも不可能。それに対しダイアローグの対象は「象徴的他者」…
2017/09/04
エビデンス主義は多様な解釈を許さず、いくつかのパラメータで固定されている。それはメタファーなき時代に向かうことを意味する。メタファーとは、目の前に現れているものが見えていない何かを表すということ。かつては「心の闇」が2ちゃんねるのような空間に一応は隔離されていた。松本卓也がいうように、本来だ…
2017/09/03
平田オリザは演劇を日本の教育に取り入れる実践において、まず「会話」(conversation)と「対話」(dialogue)を区別することから始める。「会話」は価値観や生活習慣なども近い者同士のおしゃべり、「対話」はあまり親しくない人同士の価値観や情報の交換、というように。日本では歴史的に「対話」が概念として希薄で…
2017/02/12
『atプラス 31号 2017.2 【特集】他者の理解』では、編集部から依頼されたお題に対し、著者はそれが強いられているとアンチテーゼを掲げる。「他者の理解」こそ、共生社会にとって不可欠ではないのか。いったいどういうことか? 急増する発達障害、ASD(自閉スペクトラム症)は、最近になって急に障害者とされ…
Posted by 24wacky at 11:41│Comments(0)
│いつか観た映画みたいに