2017年03月20日
『考えるということ 知的創造の方法』大澤真幸
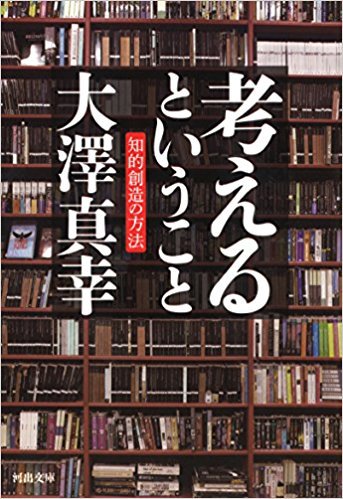
なにやらビジネスパーソン向けの手っ取り早い指南書の装いであるが、正真正銘大澤真幸社会学の一冊である。考えるとはどういうことか、大澤自身の手の内を丁寧かつ具体的に明かすという親切心にあふれている。それだけ「考える」ことの復権という使命を著者も編集者も持たざるを得ないということか。何はともあれ、考え始めると即煮詰まる私のようなタイプにはありがたい実践の書である。
なにしろ出だしがカッコいい。引用する誘惑に逆らえない。
私の仕事の大半は、読み、考え、そして書くことにある。本書は、私が本をどのように読み、いかにしてそこから思考を紡ぎ出すか、具体的に例示することを目的としている。
考えることは、人間の義務でもなければ、原初的な欲望でもない。しかし、あるショックを受けたとき、人は思考しないではいられなくなる。このショックのことを、哲学者ジル・ドゥルーズは「不法侵入」に喩えている。ありきたりの知識や解釈では、不法侵入を受け止めることができないとき、人は思考することを強いられる。
(3ページ)
「あるショックを受ける」のは、日常の経験であったり、他人の言葉であったり、読書経験であったりするだろう。まずはそのショックを感知できなければならない。次に考える作業に移るはずだが、しばしば人は、というか私は「考え」が停滞する。それが断続的になるや悶々とすること必定である。これが続くと「考える」ことをあきらめる。
大澤によれば、考えるには場所を確認する必要がある。考えている場所は、自分の身体の外にあるそうだ。「そのときに、逆説的だが、言葉を媒介にしてアイディアを自分の中に完全に内面化したような気分になってはいけない。言葉は自分の内面から絞り出されるのでは、ない」(25ページ)。私の悶々の原因は、言葉を自分の内面から絞り出そうとしていたからだったのだ。
実は、私はそのことを知っている(た)。しかし、それは大澤の著作を読み、次に考え、そして書くことを通し、知っていたことを知る。その逆説を本書は教えてくれる。
『考えるということ 知的創造の方法』
著者:大澤真幸
発行所:河出文庫
発行年月:2017年1月20日
2016/12/05
2015年にノーベル文学賞を受賞したスベトラーナ・アレクシエービッチは先日の来日講演の中で、福島第一原発事故の被災地を訪ねたことに触れ、「日本社会には抵抗の文化がないのはなぜか」と問うた(「日本には抵抗の文化がない」 福島訪問したノーベル賞作家が指摘 THE HUFFINGTON POST 2016年11月29日付)。本書…
2016/10/30
フランス革命のスローガンは「自由、平等、友愛」である。各人の自由が、すべての他者たちの自由の条件になっている。ということは、自由と普遍的で無際限の連帯(友愛)とが、同時に、相互に条件づけあうように実現している、ということである。そこに平等はなくてもよい。そのときすでに、不平等も解消されている…
2016/10/29
ハーマン・メルヴィルの中編小説『バートルビー━━ウォール街の物語』(1853年)は、資本主義の中心地となる19世紀のウォール街において、語り手の弁護士によって記述される、書記バートルビーの奇妙な生態についての物語である。弁護士が口述や筆記の仕事を頼むと、バートルビーは「私はそれをしないほうがいいと思…
2016/10/28
2015年に国会議事堂の周囲で起こされた安保関連法案に反対するデモは、敗戦後70年間で最大のレベルだった。その中心となったSEALDsという学生たちの団体は、本書で論じてきた社会や政治への指向をもつ若者像を裏付ける。しかしその間安倍内閣の支持率はほとんど下がらず、デモは敗北だったといわざるをえない。 同…
2016/10/27
『あまちゃん』の「夏(祖母)━━春子(母)━━アキ」という三代の女は、ちょうど日本の戦後史の3つのフェーズ「理想の時代/虚構の時代/不可能性の時代」に対応している。各世代は前の世代から活力や決断のための勇気を与えられる。 かつての東京での生活ではまったくやる気のなかったアキが初めて見出した生…
2016/10/26
戦後史の時代区分「理想の時代→虚構の時代→不可能性の時代」からいえば、かつて東京や大都市は「理想」が実現する場所だった。しかし、その求心力は不可能性の時代に入ると急速に衰えていった。それと同時に地元志向の若者たちが増えていく。地方の若者たちに「地元と聞いて思い出すものは?」と質問すると、返って…
2016/10/25
不可能性の時代において、「可能性の過剰」という側面に対応しているのが、鈴木健の『なめらかな社会とその敵』であり、「不可能性の過剰」という側面に対抗しようとしているのが、千葉雅也の『動きすぎてはいけない』である。前者は沈みゆくタイタニック号に乗り続け、後者はタイタニック号と運命をともにすること…
2016/10/24
「未来→過去」というように因果関係が遡行していることは不思議であるが、われわれは日常的に目撃したり、体験したりしている。 たとえば、幾何学の証明で用いられる「補助線」の働きがそうである。証明者が、「ここに補助線があればうまくいきそうだ」という直観を得るとき、それはあたかも未来からの情報に影…
2016/10/23
マンガ『テルマエ・ロマエ』は、古代ローマの建築家ルシウスが現代日本にワープし、浴場についてのアイデアを得るという内容である。ここには〈未来の他者〉といかにして連帯するかという主題に関わる手がかりがある。 『テルマエ』では、古代ローマの浴場が現代日本の浴場からのパクリであった。このように、…
2016/10/22
極端に危険な可能性を無視し、排除したことによって、楽観的なシナリオを過度に信ずるほかなくなる、ということがある。たとえば、10億円を動かす投資家がいたとする。彼は市場そのものが破綻する確率が90%あると直感的に理解している。とすれば、彼は10億円のうち1億円だけ投資するかというとそうではなく、なんと…
2016/10/21
フランシスコ会の修道士でポーランド人のコルベは反ユダヤ主義の思想をもっていた。第二次大戦時、ナチスがポーランドを侵攻し、ナチスに追われた人々の援助活動をしていた彼は、ゲシュタポに逮捕され、アウシュビッツ強制収容所に送られた。そこで餓死の刑が下されると、コルベはユダヤ人の身代わりとなり餓死室に…
2016/10/20
3・11以降、脱原発運動の大規模なデモが発生した。しかしその間国会では、原発の問題が中心的課題として議論されたとはいえない。デモによって表現される国民的関心と国会議員の行動の間に整合性がない。国会議員は国民の意志を無視すれば次回の選挙で自分が落選するかもしれないという切迫した恐れをもたなかった。…
2016/10/19
社会や政治への関心が薄く親密な仲間との関係に閉じこもる若者という通念と、次の社会調査の結果は重なる。衆議院選挙の年齢別の投票率によると、二十代の投票率は1960年代から1980年代にかけては60%前後を上下しているが、2000年を挟む3回の選挙では30%台に激減している。このような極端な減少は他の年齢層ではみ…
2016/10/18
著者は日本人の「生活全体についての満足感」という社会調査のデータから、1973年と2008年を比較し、1973年では若い世代(とりわけ男性)の幸福度が低いのに対し、2008年のグラフでは高いのが顕著であることの不可解さに注目する。なぜなら、この世代こそ、バブル崩壊後の不況の影響を直接受けた「ロストジェネレー…
2016/10/16
どのような社会にも、論理的にはもちろん可能だし、法的にも必ずしも禁じられてはいないのだが、「それ」を選択すること、「それ」をなすことは、事実上は、不可能だとされていることがある。「それ」を選択しないことを暗黙の前提とした上で、われわれには、「それ」と「あれ」の選択の自由が与えられており、われ…
Posted by 24wacky at 19:09│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした
























