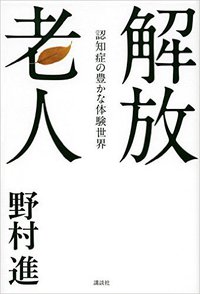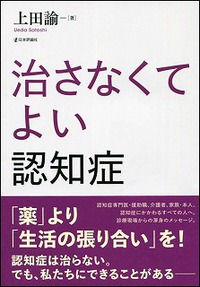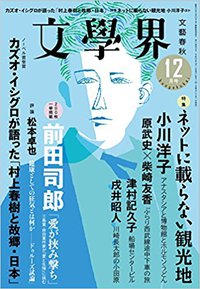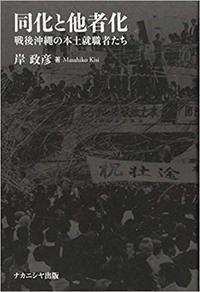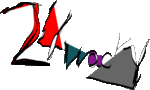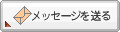2019年09月17日
『街灯りとしての本屋』田中佳祐

出版不況とともに激減していく街の本屋さんが多いなか、ユニークな個人経営の書店が増えている。本に対する愛情、リアル店舗の存在意義などが交差するなか、個性的な店主たち11名の声が、店舗外観・内観のカラー写真とともに紹介される。
それにしても十人十色、皆、考えていることはバラバラだ。これから書店を始めるため参考になる知見を得ようとすると、まったく相反する意見があったりするので混乱するかもしれない。でも、それは多様性でもあり、それを咀嚼し、自分の考えを鍛える材料にすればよい。
個人的に注目したのが、地域との関わりについての語りである。東京・向島の「書肆スーベニア」店主は、新しくできたマンション住人は、自分たちの住んでいる場所に「ナニカがあるということを全く期待していない」ので店には来ない、通勤・通学で駅との往復をするだけだ、店に住んでいるとそのような街の様子がよくわかる、と東京下町で起きている厳しい現実を語る。
千葉・松戸の「せんぱくBookbase」は、本屋をやりたい人が集まる間借り本屋だ。店主は地域の人に来てもらおうと、様々なローカルな告知を試みたもののまったく響かず、結局来てくれたのはSNSを通した人たちだったという。その苦い経験から、「この本屋は入って大丈夫だと知ってもらわんとダメなんやと」反省を口にする。
他の店主からも地域との関わりを大事にすべしという意見が多いのに対し、東京・世田谷の猫本専門店「Cat's Meow Books」の店主は、自身も含め世田谷はよそ者が多い街、立地も住宅街にあるという特性を背景に、「店主が隣近所と密接な関わりがあって、初めてお客さんが来るような店にしたくなかった」と独自の見解を示す。
本書のタイトルにもあるように、「街」と「本屋」は切り離せないという見方があり、私の関心もそこを基点としている。新刊・古書を問わず書店で起業するといより、本を媒介として、人びとが集まる場を設け、生業のひとつにする、という漠然としたイメージにとどまっているのだが。本書のインタビューで語られるトライ&エラーは、そこにカラフルな灯りをともしてくれる。
『街灯りとしての本屋』
著者:田中佳祐
構成:竹田信弥
発行:雷鳥社
発行年月:2019年7月31日
2019/08/20
ドキュメンタリー映画『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』より以前に、その魅力を報告していたのが本書。コンパクトに編集されながらも、こちらもかなりの情報量が含まれている。それらをここで後追いし記述することは控え、ここでは一点に絞って論じることにする。 〈第5章 インターネット時代に問…
2019/08/19
ドキュメンタリー映画『ニューヨーク公共図書館』の国内ヒットを受け、映画以前にいち早く同図書館の魅力を伝えた『未来をつくる図書館 ─ニューヨークからの報告─』の著者で米在住ジャーナリストの菅谷明子さんによるトークイベント「ニューヨーク公共図書館と米国の本をめぐる多様な取り組み」が18日、国立本店にて開催…
2019/08/18
京浜東北線蕨駅から徒歩6分の Antenna Books &; Cafe ココシバで開催された「 アジアの本屋さんの話をしよう ココシバ著者トーク」に参加した。出版ジャーナリストの石橋毅史さんが新著『本屋がアジアをつなぐ』にまつわる話を写真も交えながら展開。ソウル、香港、台北のユニークな書店の生まれた背景など、興味深い内…
2019/08/08
表題に関わる広範囲のアクターたちのインタビューと論考を網羅しているが、総じて期待していたほど集中して読むことができなかった。その中で、最後の内沼晋太郎「不便な本屋はあなたをハックしない」を興味深く読むことができた。 インターネットの情報が私企業に操られることに警鐘を鳴らすインターネット…
2019年09月15日
『掃除婦のための手引書 ルシア・ベルリン作品集』

注目される「発見」された作家の作品集。その中から「どうにもならない」を例に、初見の雑感。
アルコール依存症の女に深夜、発作が始まる。彼女は部屋中の現金をかき集め、歩くと45分はかかる酒屋へと向かう。失神寸前になりながらもたどり着いた開店前の酒屋の前には黒人の男たちがたむろしている。男たちは彼女にやさしく順番を譲ってくれる。ウォッカを買った彼女は息子たちが目を覚ます前に家に戻り、ジュースで割ったウォッカを飲み、「アルコールの優しさが体のすみずみまでしみわたった」。だいぶ回復した彼女は山ほどの洗濯物を洗濯機に入れる。やがて起きてきた息子たちと朝の挨拶をして朝食をすますと学校に送り出す。この一つのシークエンスで構成されるショート・ストーリーは5ページで終わる。
読み直して気づいたが、これは三人称の小説である。てっきり一人称だと勘違いしていたが、最初のセンテンスから「彼女は」と主語が明記されている。私に勘違いを起こさせるのは、その独特の文体に依る。「彼女は〜した」という主語+述語の破綻のない文章に、彼女の内面の語りが混在している。たとえば、最初のセンテンスが三人称で始まった後、次のように続く。
こういうときの裏技、呼吸をゆっくりにして心拍数を落とす。ボトルを手に入れるまで、とにかく気を落ちつけること。まずは糖分。砂糖入りの紅茶だ、デトックス施設ではそれが出る。でも震えがひどすぎて立てない。床に横になり、ヨガみたいにゆっくり深呼吸する。考えちゃだめ。今の自分のありさまについて考えるな、考えたら死んでしまう、恥の発作で。
(116ページ)
「こういうときの〜それが出る」は内面の語り、「でも震えがひどすぎて〜深呼吸する。」で三人称に戻り、「考えちゃだめ。〜恥の発作で。」では、再び内面の語りへ切り替わる。
ここでの「考えちゃだめ。〜恥の発作で。」を内面の語りとしたが、情けない「彼女」に対しメタレベルから距離をおき、しかもヒューモアを持って語りかける「私」という視点といったほうが正しいかもしれない。
むろん三人称に主人公の内面を描出する手法自体は、近代小説では珍しくない。しかし、近代小説の自明の装置としてのそれは、たんに「装置」である。これに対して、ルシア・ベルリンの「私」という視点では、メタレベルにいる「私」と眼差され語りかけられる「彼女」のあいだに、ヒューモアがあると同時に、近過ぎる、タイトな距離感がある。だから、読者は緊張と緩和を反復させながら読む。
そもそも、アルコール欲しさから堪らず深夜(早朝?)酒を買い出歩き、それでも息子たちのために洗濯機を回すことも朝食を用意することもこなす妙な生真面目さを発揮し、その殊勝な振る舞いが見せかけだったかのように、息子たちを学校に送りだした直後に再び酒を買いに走るというオチがつく構成そのものが、緊張と緩和そのものではないか。
発作を抑えようと努力する引用部分の後、「彼女」は本棚の本のタイトルを読みはじめ、いくつかの作家の名前が挙げられ、少し楽になる。ここで作者と主人公と読者はつかの間のカタルシスを共にする。私はといえば、その名前の一人、シャーウッド・アンダーソンを自分の本棚から取り出し、何十年ぶりかで読んでみたくなっている。
『掃除婦のための手引書 ルシア・ベルリン作品集』
著者:ルシア・ベルリン
訳者:岸本佐知子
発行:講談社
発行年月:2019年7月8日
2019年09月14日
『在宅無限大 訪問看護師がみた生と死』村上靖彦
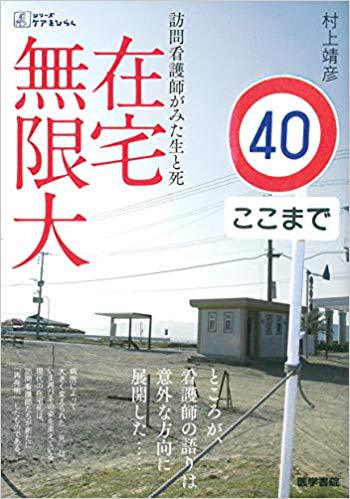
精神病理学・精神分析が専門の著者が訪問看護師へのインタビューをもとに、倫理的な問いとして何を発見し、何を学んだかが書かれている。特徴的なその手法は、多数のデータを材料に客観的な視点から比較するのではなく、看護師の実践を尊重し、あくまでその視点から記述するというもの。その聞き取りから、「快適さと安楽を生み出すこと」「小さな願いを聞き出し実現すること」「困難な状況を引き受けて応答すること」という三つの側面を抽出し、その三部構成というシンプルな形式をとっている。
「最期は畳の上で死にたい」とはよく聞く言葉だが、看取りを経験した看護師Cさんの語りとして、それは「死ぬときにならないと分からない」。しかし、死を間近にして明らかになることは、身体の快が第一の「本来」のものであり、快の源泉は自宅にあるということ。看護師にとって、患者の快適さと安楽をいかに提供できるかがポイントとなる。
「どうしたいですか?」とは、とりわけ在宅において、看護師が患者に尋ねる言葉である。「願い」とは、それを実現するために患者の持つ「力」を看護師が見極めることが前提となる。実は、「願い」も「力」の見極めも容易ではない。患者自身が自分の「力」をよく分かっていないことが少なくないからだ。その場合、看護師は患者本人と話し合い、できないと思われていたことを試し、患者の「じつはできること」を取り出そうとする。
看取りにおける予後告知で重要なことは、家族がみんなで死を引き受けることである。「もうお別れですね」と、別れが近づいていることを共有したうえで語り合うこと、それがお別れという行為となる。さよならをいうことが必ずしもお別れではない。
母親が重い障害を持つ子どもと暮らす覚悟をしたときに「心が動く」と看護師Fさんはいう。その意味を尋ねる著者に、Fさんは「パッと表情が変わったりとか、その次の行動が変容したり」と答える。著者はFさんが母親の心を動かすのかと問いかけたのだが、主役は母親であり、変化は自ずと生じ、Fさんはその触媒となることが、この応答からわかる。まさに「中動態の世界」(國分功一郎)である。
慢性期の疾患のケアであれ、看取りであれ、自分あるいは親しい人が在宅医療を受ける場合、訪問看護という仕事の奥深さとそれを担う方々のプロフェッショナルな流儀を知ることができたことは、大きな収穫である。著者によれば、本書に記述される看護師の迷いや応答は、「医療的な判断をともないつつも、その手前あるいは外側で働いているように見え」たという(221ページ)。その力がおおいに発揮されるのが在宅という場なのであろう。
『在宅無限大 訪問看護師がみた生と死』
シリーズ ケアをひらく
著者:村上靖彦
発行:医学書院
発行年月:2018年12月15日
2019/09/07
「中学生の質問箱」シリーズとして平易な会話の文体で著者がこだわったことはなにか。それを書くために、「正常」「異常」「症状」「回復」などの言葉に鉤括弧がつけられる。 第2章では、統合失調症、うつ病、躁うつ病、PTSD、転換性障害、強迫症、摂食障害、社交不安障害、不登校・いじめ、発達障害、認知症…
2019/05/11
沖縄の精神科デイケア施設で心理士として勤務した4年間をエッセイ形式で綴った学術書。現在の自分の関心領域にあまりにもハマり過ぎる内容であり、時間を忘れて一気に読んでしまった。その関心とは、1に設定が沖縄であること、2に精神疾患のケア(とセラピー)についてのリアルな現場報告であることの切実さ、3…
2018/12/08
対談─来るべき当事者研究─当事者研究の未来と中動態の世界熊谷晋一郎+國分功一郎 興味深い二人の対談において、2つの対立軸を乗り越える方向性が確認できた。1つは、能動/受動の対立軸、2つは、運動と研究の対立軸である。 まずは、能動/受動の対立軸について。 熊谷晋一郎は國分功一郎著『中…
2019/03/03
統合失調症など危機的な状況を生きる当事者とその家族。当事者は親と口をきかず部屋に閉じこもる。ときに上がる大声や暴力から、苦しみを回避したいというメッセージが著者には透けて見える。当事者と家族が対立しているように見える構造を一度ばらばらにして、当事者の振る舞いが、結果として全く正反対の暴言や暴…
2019/01/06
中学に入学し、初めて英語を学び、能動態と受動態という2つの態がある(それだけしかない)と教えられた。だが、日常的に用いている言動として、この2つでは括れない場合があるのではという漠たる疑問があった。本書によれば、中動態という態が、古代からインド=ヨーロッパ語に存在したという。中動態というと、…
2018/10/09
統合失調症を病む者の寛解期初期の状態を、著者は角を出しはじめた蝸牛にみたてる。社会の中に座を占めようとするその行動を探索行動と表現する。医師や家族そして支援者、いや、社会は、彼ら個々の行動の成否を性急に判断したり、説教したりすることに慎重になるべきだ、と。 そこから著者には次の問いが生ま…
2018/02/26
アルツハイマー型認知症となった実の母を対象に明るいタッチで捉えたドキュメンタリー・シリーズのいよいよ「ファイナル」。1作目の『毎日がアルツハイマー 』では認知症の実態を、2作目の『毎日がアルツハイマー2 』では当事者を尊重するケアの手法としての「パーソン・センタード・ケア」に焦点を当てた。今作…
2017/02/17
山形県にある佐藤病院の重度痴呆症病棟の長期取材である。半分ほど読み進めたところで、先を読む意欲が湧かないのはなぜだろう。 絶叫したり、大暴れしたり、大便を手づかみで投げつけたりする女性につかまれ、著者はその力強さの源泉を知りたいと思う。それが見つかれば、「認知症患者」が「新たな姿で立ち上…
2016/11/20
ドゥルーズは認知症についてどう語っていたかという切り口は、認知症の母と共生する私にとって、あまりにも関心度の高過ぎる論考である。といってはみたものの、まず、私はドゥルーズを一冊たりとも読んだことがないことを白状しなければならない。次に、この論考は、引用されるドゥルーズの著作を読んでいないと認識が…
2015/01/02
元日、初雪舞う中、渋谷のイメージフォーラムに『パーソナルソング』を観にいく。介護施設でひとりぽつりと車椅子にうなだれる認知症当事者に思い入れのある歌(パーソナルソング)を聞かせると、見違えたように生気が戻った反応を示す。じゅうぶんありえることだと想像はつくが、それがあたかもアルツハイマー病を治…
2014/12/02
認知症の母を持つ私にとって、いや、高齢になればすべての人が認知症になる可能性を考えれば、社会にとって必須の本である。それは、認知症(本書では、高齢のアルツハイマー型認知症の軽度から中等度を指す)に対するこれまでの理解が、まったくひどいものであり、いまだにそうである現状が本書を読むと痛切であるから…
2014/08/04
2014年企画・製作・監督・撮影・編集:関口祐加プロデューサー:山上徹二郎ポレポレ東中野で『毎日がアルツハイマー2』を観た。認知症の母にカメラを向け、決して深刻にならず掛け合い漫才のような笑いに包まれた前作『毎日がアルツハイマー』(2012年)の続編。その笑いの感覚は今作でも健在である。と同…
2019年09月08日
『クジャ幻視行』崎山多美

本書は2000年代半ばに文芸誌に発表された7つの話の短編集である。そのほとんどが「オキナワ」の「クジャ」という「マチ」を舞台とした「幻想小説」といういい方もできる。それぞれは独立しているが、最初の「孤島夢ドゥチュイムニ」がクジャに迷い込んだフリー写真家の「オレ」による一人称で始まり、最後の「クジャ奇想曲変奏」はその後日譚が描かれ、その他の短編をあいだに綴じるような構成になっている。
その多くは、語り手が夢から醒めるおぼろげな意識の語りから書き出され、著者得意の擬音語、擬態語、擬声語が続く。「──ウおおーッおおおーッおおおおーッ。/突如として、ドロの水面から阿鼻叫喚が。」(「孤島夢ドゥチュイムニ」)というように。
ほとんどの語り手と登場人物たちは、クジャから外へ出ようとしない。つまり、小説はその範囲内で語られる。語り手の前に突如現れるつかみどころのない物の怪たちの移動を追うにつれて、クジャのマチはときに死臭を漂わせながら描出される。
このように周到な異化の技法を配し、なお著者が試みようとする小説家としての企みとはなにか。基地の町(クジャ=コザ)、米兵によるレイプ、「沖縄戦」「集団自決」といった沖縄をめぐるいかにもな符牒をあえて題材として選んだことをも、よく考える必要がある。その選択自体が異化作用なのだとすれば。
「ピンギヒラ坂夜行」は、陽が落ちかけるころ、ピサラ・アンガという老婆がマチから「ひょっこひょっこ」と歩き出し、ピンギヒラ坂という坂の向こうで祈祷する場面から始まる。生き場所のない者たちが最後に逃げ込む(ピンギル)その場所で、ウガン(願かけ)するアンガは、やがて14歳の少女を幻視する。二人の行き違う会話が続き、少女は自分が50年前にこの町で生まれ、「フツーじゃない」死に方をしたというヒントを与える。アンガは自らの過去を追想するが、少女が誰かわからず焦る。最後に少女は答える。「アンガがアタシのことを思い出してくれなければ、アタシはもうどこの誰でもなくなる……」と。
この訴えこそ、小説家・崎山多美の創作の根拠をめぐる切実さといえる。夢を(意識的に)みると聞こえてくる声。それを語りに変換する。その際、やっかいなのが前述した沖縄をめぐる符牒である。「声」にはそれがついて回るので容易に避けることができない。だから書く以外ない。であればこそ、それを消費の言葉にしないための異化作用なのだ。
沖縄の共同体も同様、異化されねばならない。沖縄をめぐる同質/異質の二元論を。「マチ」とは、その記号めいたなにかである。
ここで、このマチの住人というとき、一般にいう、みずから先祖代々この土地の土着人だと深く思いこんでいる者を、含まない。殆どの住人がもともとはヨソモンである。ヨソモン、と一言で言っても、彼らの背景にあるのは、例えば、次のような事情だ。
(78ページ)
以下、正嫡子でない有象無象の生の断片が挙げられ、マチの構成員が成立する。マチの構成員が自分たちの「アイデンティティ」を表明しようとするとき、ポリフォニックなグンダンパナス(道端談義)の声は有効である。「ホラあそこはさ、あの世ってわけじゃあないけどこの世っていうのもなんかちがうって感じのするいうならば影の溜まり場みたいな所よあそこは」。
ここまでくれば、最初の「孤島夢ドゥチュイムニ」と最後の「クジャ奇想曲変奏」の語り手が、「日本人」の写真家という、外部者として沖縄を眼差し消費するいかにもな設定となっていながら、「沖縄/ヤマト」の二項対立に安易に陥ることなく、というより「闘争的に」それを刷新する設定として描かれていることには、越境の場から「期待」をしたくなる。「クジャ奇想曲変奏」の最後、オレは「沖縄の共同体」に拒否されることなく死者たちの円舞に加わり、その直後、轟音とともに押し寄せてくるブルドーザーの隊列に立ち向かう/立ちつくす。
『クジャ幻視行』
著者:崎山多美
発行:花書院
発行年月:2017年6月2日
2018/12/16
〈巻頭座談会 復帰後沖縄を巡って 高嶺朝一×長元朝浩×若林千代×仲里効〉では、沖縄の復帰後という長いスパンについて議論が展開されるが、本題に入る前に、直前に急逝した翁長雄志沖縄県前知事についての評価が話題となる。特に司会の仲里効と若林千代とのあいだで大きく評価が分かれるその内容が興味深い。 …
2017/12/31
「目取真俊特集を組む次号に書かないか」と編集委員の一人から声をかけてもらい、さて何が書けるかとしばし思いを巡らした。決まっている他の執筆陣について確認すると、編集委員に「文学系」が多いこともあり、文学評論が多いという。しかし、目取真俊といえば、本書冒頭での仲里効との対談のタイトル「行動するこ…
2015/07/06
崎山多美さんの講演タイトルが「シマコトバでカチャーシー」と題されているのを知って、わたしはとても訝しんだ。「なんだこのベタなタイトルは?」と。はじめにこう推測した。東京側の主催者が沖縄消費イメージからつけたのだろうか?それにしてはあまりにも軽率すぎる。崎山さんがそのままにするわけがないと。というこ…
2015/07/05
崎山多美講演会「シマコトバでカチャーシー」をわたしはどう受けとめたか。前記事のコメント欄にも書き加えたが、崎山さんは「シマコトバ」による朗読を試みているが、わたしはその部分を省略した。その意味について改めて書いてみる。わたしの言い訳としては、その部分を「伝える」としたら一部分のみではじゅう…
2015/07/04
7月⒋日立教大学池袋キャンパスにて立教大学日本文学会大会が開催され、崎山多美さんが「シマコトバでカチャーシー」という題で講演した。以下、その論旨を紹介する(文責は私個人にある)。「シマコトバ」「シマコトバ」は実際には「シマクトゥバ」と発音する、最近になって新しく流布されるようになった言葉です。…
2018/09/24
表題作『六月二十三日 アイエナー沖縄』は、沖縄戦終結の日とされる6月23日が章ごとに舞台設定され、以降10年ごとにそれぞれ個別の一人称の語りが綴られるというユニークな形式がとられている。各章の語り手は、それぞれ「戦後」沖縄のネガであり裸像といえる。沖縄島北部の護郷隊に選ばれ生まれ島の戦地を彷徨う青…
タグ :崎山多美
2019年09月07日
『心の病気ってなんだろう?』松本卓也

「中学生の質問箱」シリーズとして平易な会話の文体で著者がこだわったことはなにか。それを書くために、「正常」「異常」「症状」「回復」などの言葉に鉤括弧がつけられる。
第2章では、統合失調症、うつ病、躁うつ病、PTSD、転換性障害、強迫症、摂食障害、社交不安障害、不登校・いじめ、発達障害、認知症などが個別で詳しく解説される。そこで伝えたかったことは、一見すると「異常」な心の働きも、「正常」なものとして考えることができるということである。たとえば、統合失調症で生じる妄想は、心の働きそのものが崩れさろうとしているときに、心を立て直そうとしているからこそ生じる。このような心の病気の「症状」の多くは、真の意味での「症状」ではなく、むしろ病気からの「回復」の試みである、と。
本書は、心の病気の「当事者」よりも、むしろ「健常者」に向けて書かれている。本書を読み、そして学ぶことで、心の病気についての認識が改まること、「わかる」ための努力をすれば、病気の「本体」から出てくる気持ちをそれなりに想像できるようになることが期待される。
心の病気から「回復」することは、病気になる前の状態に「戻る」ことではないと、著者は断言する。「戻る」ことは、再発の危険性を増すことであるから、と。
「回復する」ということは、前の状態とは違う形の行き方を手に入れられるようになることです。病気を通り抜けることによって、自分のライフスタイルが変化し、さらには自分が変化することです。それが「回復する」ということです。
(274ページ)
本書では難解な哲学用語は避けられているが、ここでいう自分が変化するという意味での「回復」とは、明らかにドゥルーズ=ガタリの「生成変化」(devnir)が下敷きにある。「健常者」=「人間=男性」=「マジョリティ」、「当事者」=「女性」=「マイノリティ」と置き換えることによって。《ある意味では、生成変化の主体は常に homme [人間=男性]だと言える。ただし homme がそのような主体となるのは、何らかのマイノリティ性への生成変化に入り、自らのメジャーな同一性から引き剥がされる限りにおいてのことだ》(『三つの革命 ドゥルーズ=ガタリの政治革命』佐藤嘉幸 廣瀬純)。
その意味で、統合失調症の妄想といかに折り合いをつけるかという場面で、回復のために「正常なマジョリティ(多数派)」を目指さないようにすることに注意が促されている(第2章)ことは偶然ではない。だからまわりの人は、その人が「マイノリティ」としてうまくやっていくことを支援することが最重要なのだと著者はいう。もはやいうまでもないが、この場面で問われるのは、むしろ「支援」する側がマジョリティであることの自明性である。
『心の病気ってなんだろう?』
中学生の質問箱 シリーズ第12弾
著者:松本卓也
発行:平凡社
発行年月:2019年7月17日
2019/07/18
西洋思想史に「創造と狂気」という論点を設定し、体系的に読みやすく、しかも読み応えある内容に仕上げている。臨床的なワードと思想が交差され、「こんな本が読みたかった」と思える一冊。 統合失調症中心主義。それは、統合失調症者は普通の人間では到達できないような真理を手に入れているという考え。悲劇…
2018/10/08
精神病理学には3つの立場がある。記述精神病理学、現象学的精神病理学、そして力動精神医学(精神分析)という。 ヤスパースに始まる記述的精神病理学は、患者に生じている心的体験(心の状態や動き)を的確に記述し、命名し、分類する。その際、「了解」という方法がとられる。「了解」とは、医師=主体が患…
2018/04/09
精神分析を可能にした条件とは、近代精神医学が依拠した人間の狂気(非理性)とのあいだの関係を、言語と、言語の限界としての「表象不可能なもの」の裂け目というパラダイムによって捉え直すことであった。1950〜60年代のラカンの仕事は、フロイトが発見した無意識の二重構造を、超越論的システムとして次のように…
2017/01/05
本書は、ドゥルーズとガタリやデリダといったポスト構造主義の思想家からすでに乗り越えられたとみなされる、哲学者で精神科医のラカンのテキストを読み直す試みとしてある。その核心点は「神経症と精神病の鑑別診断」である。ラカンは、フロイトの鑑別診断論を体系化しながら、神経症ではエディプスコンプレクスが…
2018/01/02
今もっとも注目する松本卓也論考の概要。 ドゥルーズは「健康としての狂気」に導かれている。その導き手として真っ先に挙げられるのが、『意味の論理学』(1969年)におけるアントナン・アルトーとルイス・キャロルであろう。アルトーが統合失調症であるのに対し、キャロルを自閉症スペクトラム(アスペルガー症…
2016/11/20
ドゥルーズは認知症についてどう語っていたかという切り口は、認知症の母と共生する私にとって、あまりにも関心度の高過ぎる論考である。といってはみたものの、まず、私はドゥルーズを一冊たりとも読んだことがないことを白状しなければならない。次に、この論考は、引用されるドゥルーズの著作を読んでいないと認識が…
2016/11/19
「水平方向の精神病理学」とは、精神病理学者ビンスワンガーの学説による。彼によれば、私たちが生きる空間には、垂直方向と水平方向の二種類の方向性があるという。前者は「父」や「神」あるいは「理想」などを追い求め、自らを高みへ導くよう目指し、後者は世界の各地を見て回り視野を広げるようなベクトルを描く。通…
2019/06/10
6月9日多摩市民館にて『オキナワへ行こう』上映会&トークショー&写真展が約160名の参加者(主催者発表)を集め開催された(主催はNPO法人たま・あさお精神保険福祉をすすめる会)。 同作品はスチール・カメラマンとして精神科病院の患者を長年撮影してきた大西暢夫さんによるドキュメンタリー。大阪府堺市の…
2019/05/11
沖縄の精神科デイケア施設で心理士として勤務した4年間をエッセイ形式で綴った学術書。現在の自分の関心領域にあまりにもハマり過ぎる内容であり、時間を忘れて一気に読んでしまった。その関心とは、1に設定が沖縄であること、2に精神疾患のケア(とセラピー)についてのリアルな現場報告であることの切実さ、3…
2019/03/24
ウサギ狩りをする人は、ウサギが欲しいから狩りをするのではなく、気晴らしが欲しいからそうする。つまり、ウサギは〈欲望の対象〉であるが〈欲望の原因〉ではない。それにもかかわらず、人は両者を取り違える。 「暇」と「退屈」は、しばしば混同して使われる。暇とは客観的な条件に関わっているのに対し、退…
2019/03/03
統合失調症など危機的な状況を生きる当事者とその家族。当事者は親と口をきかず部屋に閉じこもる。ときに上がる大声や暴力から、苦しみを回避したいというメッセージが著者には透けて見える。当事者と家族が対立しているように見える構造を一度ばらばらにして、当事者の振る舞いが、結果として全く正反対の暴言や暴…
2019/01/06
中学に入学し、初めて英語を学び、能動態と受動態という2つの態がある(それだけしかない)と教えられた。だが、日常的に用いている言動として、この2つでは括れない場合があるのではという漠たる疑問があった。本書によれば、中動態という態が、古代からインド=ヨーロッパ語に存在したという。中動態というと、…
2018/12/08
対談─来るべき当事者研究─当事者研究の未来と中動態の世界熊谷晋一郎+國分功一郎 興味深い二人の対談において、2つの対立軸を乗り越える方向性が確認できた。1つは、能動/受動の対立軸、2つは、運動と研究の対立軸である。 まずは、能動/受動の対立軸について。 熊谷晋一郎は國分功一郎著『中…
2018/10/09
統合失調症を病む者の寛解期初期の状態を、著者は角を出しはじめた蝸牛にみたてる。社会の中に座を占めようとするその行動を探索行動と表現する。医師や家族そして支援者、いや、社会は、彼ら個々の行動の成否を性急に判断したり、説教したりすることに慎重になるべきだ、と。 そこから著者には次の問いが生ま…
2018/06/07
自分のバンドのサポート・ギタリストが精神科の主治医。それがいとうせいこうと星野概念の関係である。患者と主治医がいつものカウンセリングを再現するような対談。企画したいとうせいこうのねらいは、ハードルが高いカウンセリングになかなか来られない人たちのために「ちょっとした薬」のようなものを提示したい…
2018/06/02
認知の方法を著者は二つのタイプに分ける。頭の中の映像を使って思考する視覚優位と、言葉を聴覚で聴き覚え、理解し、思考する聴覚優位とに。これらの特徴は普通の人々にもあるが、発達障害ではその偏りが強くなる。著者は「偏り」を「優位性」とポジティブに表現する。自身映像思考の著者が室内設計家として成り立…
2018/05/20
冒頭からリゾームという言葉のイメージの噴出に息が切れそうになる。リゾームとは樹木やその根とは違い点と点を連結する線からなる。それは極限として逃走線や脱領土化線となる。樹木は血統であるが、リゾームは同盟である。リゾームは多様体である。リゾームは生成変化である。リゾームとは定住性ではなく遊牧性で…
2018/04/29
ブダペスト郊外の食肉加工場で代理の検査官マーリア(アレクサンドラ・ボアブリー)が勤務を始めた。マーリアは他者とのコミュニケーションがうまくとれずに周りから孤立している。人生にやや疲れ片腕が不自由な上司エンドレ(ゲーザ・モルチャーニ)は彼女を気にかける。やがて二人は雪降る森を彷徨う雌雄一組の鹿…
2018/03/21
『アンチ・オイディプス』は、「欲望機械」「器官なき身体」「分裂分析」「接続と切断」といった言葉の発明をもとに、無意識論、欲望論、精神病理論、身体論、家族論、国家論、世界史論、資本論、記号論、権力論など様々な領域へ思考を横断していくところに最大の特徴がある。「あとがき」で翻訳者の宇野邦一は、…
2017/02/17
山形県にある佐藤病院の重度痴呆症病棟の長期取材である。半分ほど読み進めたところで、先を読む意欲が湧かないのはなぜだろう。 絶叫したり、大暴れしたり、大便を手づかみで投げつけたりする女性につかまれ、著者はその力強さの源泉を知りたいと思う。それが見つかれば、「認知症患者」が「新たな姿で立ち上…
2017/02/12
『atプラス 31号 2017.2 【特集】他者の理解』では、編集部から依頼されたお題に対し、著者はそれが強いられているとアンチテーゼを掲げる。「他者の理解」こそ、共生社会にとって不可欠ではないのか。いったいどういうことか? 急増する発達障害、ASD(自閉スペクトラム症)は、最近になって急に障害者とされ…
2014/06/28
著者:蟻塚亮二発行:大月書店発効日:2014年6月10日 2010年12月当時、沖縄の病院に勤務する精神科医師である著者は、高齢者の「奇妙な不眠」に立て続けに出会う。中途覚醒を呈しながらうつ病のサインが認められないその「奇妙さ」は、同じ頃読んでいたアウシュビッツからの生還者の精神症状に関する論文…
2019年08月31日
『いやな感じ』高見順
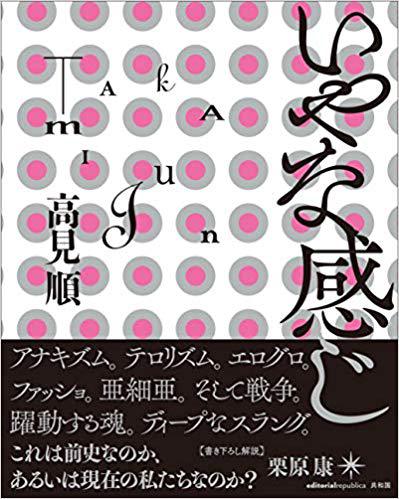
1963年に発表された本書の著者・高見順は、若き日にダダイズムの影響を受け、その後プロレタリア文学運動にも加わった小説家、詩人である。この2年後、高見は57歳の若さで亡くなっているので、晩年の長編小説という言い方ができる。
時代設定は昭和初期の約10年間、満州事変、二・二六事件、日中戦争など政治的変遷が背景としてある。主人公の青年加柴四郎は大杉栄に影響を受けたアナーキストという経歴を持つが、現在はゴロツキまがいのテロリストに成り下がっている。この主人公の一人称が、政治的出来事にときに関与し、ときに巻き込まれつつ移動する先は、東京の私娼窟、京城、北海道、上海、最後は日中戦争と、近代国家日本が植民地政策を拡げていく欲望の眼差しの先々である。
アンチヒーローの加柴が下層社会や政治青年特有の俗語をふんだんに使用するところが、エンターテイメント小説の意匠として、読む者を飽きさせない。たとえば、「リャクをやれば、それくらいの金は……」「思い切って、大口のリャクをやるか」(32ページ)の「リャク」とは恐喝のことだが、加柴がこだわるところによれば、もともとクロポトキンの『パンの略取』からくる言葉であり、私有財産否定の思想として他人から金を巻き上げることを正当化するニュアンスがある。このこだわりこそ、本書の通俗的かつ通念破壊的な魅力を現している。
アナーキストがテロリストに転じ、左翼が右翼に合流する。高邁な思想が敢えなく資本になびく。その時代的ごった煮は歴史小説を読む愉しみとしても頁をめくらせる。
本書がこの時代に再び世に出された理由はなにか。それは「いやな感じ」を顕在化させることである。誤魔化さないことである。勘違い甚だしいほどポップな装丁を片手に街へ出よう。電車内で向かいに座る女が目に留めれば、まずはしめたものだ。「いやな感じ」に「いいね!」させておびき出せ。「映え」させる程度に変態せよ。そこから奈落の底が見えてくる。
『いやな感じ』
著者:高見順
発行:共和国
発行年月:2019年6月10日
2019/03/17
全編で発せられる「日本語」を「日本人」として聞くことの異和が、劇映画的脚色をカタルシスにさせない。「日本語」の音声は、すこぶる魅力を発するチェ・ヒソ演じる金子文子のエネルギーとわずかに交わらない。それが前提であり、すべてである、というしかない。そこにとどまって、なおかつ、何をいい得るのか、わ…
2018/01/14
文芸批評家時代の若き柄谷行人は、『古山高麗雄集』(1972年・河出書房新社)の解説を次のように書き始めている。《古山氏は四十八歳まで何も書かなかった。何も書かなかったのは、やがて書こうという目的やあてがあってのことではない。また、氏が書きはじめたのは、どうしても書かねばらならいことがあったからで…
2018/01/04
分厚い『柄谷行人書評集』のなかで最も面白かったのが本書の解説として書かれた一文であった。恥ずかしながら古山高麗雄という作家をそこで初めて知ったのだが、まだ知らぬ作家についての批評が面白く、その作家に俄然興味が湧き、しかもこの作家は自分の趣味に合っているに違いないという根拠の薄い確信が伴い、実…
2009/12/14
「『世界共和国へ』に関するノート」のためのメモ その37季刊『atプラス』連載「『世界共和国へ』に関するノート(13)」(柄谷行人著)02号は「社会主義と共同組合」と題される。プルードンは国家主義的な社会主義に異議を唱えた。フランス革命の「自由・平等・友愛」というスローガンがあるが、その中で彼は自…
2019年08月22日
『ヤンキーと地元』打越正行

本書は沖縄の若い男たちの生活──その多くは中卒、または高校中退で学歴を終え、解体屋、風俗経営者、ヤミ業者などマージナルな職業につく──についての参与観察の記録である。暴力にまみれた生態の読後は息苦しい。
「地元」とは、中学校区に相当するかれらの生活範囲を指す。だが、それはたんに空間的な指示語ではないらしく、そこに狭くて濃い人間関係によるパースペクティブが重なるように、かれらには認識される。
その主な人間関係とは、「しーじゃとうっとう」(先輩と後輩)という絶対的な関係性である。その“しばり”は在学中よりむしろ「社会」に出てから強まる。著者自身が作業に従事することで見えてくる型枠解体の現場での、先輩からの理不尽な暴力とそれをやり過ごす後輩。後輩は自分が先輩になると次の後輩に対し、同じように暴力をふるう。あるいは妻や交際相手に対しても。
かれらの職業倫理が興味深い。過酷な作業は終業時間を想像しながら耐える。作業はつらいこととして、はじめに認識される。経験を積んだ後に到達する「やりがい」や「達成感」の言葉は、かれらから聞こえない。多くはその前に辞めてしまう。だがしかし、辞めずにそのまま続けたら、「やりがい」や「達成感」をかれらは得られただろうか。
あともう少しで終わりだから頑張ろうと、現場の士気を高めるつもりで声をかけた下っ端の著者は、「時間のことは口にするな」と先輩からどやされる。一週間は作業が終わる週末をひたすら想像する。土曜の夜、キャバクラで羽目をはずすことだけを楽しみにしながら。むろん、つかの間の享楽の場でも「しーじゃとうっとう」の関係性が緩められることはないのだが。
ストレスフルなその「地元」から「逃げる」場合、かれらに与えらた選択肢に「キセツ」がある(しかない)。「キセツ」は内地への出稼ぎであり、一定の賃金を稼いで戻ってくることを前提とする。本書で「キセツ」について触れられた箇所は少ない。「ナイチャー」の態度がムカついた、作業が単調だったなどの不満の声が断片的にひろわれている。あるいは、そもそもが先輩のツテで見つけることや、それほど「稼ぐ」ことはできない構造なども語られる。少なくとも問題解決へと導く逃げ場にはなっていないことがわかる。
それにしても、なぜ著者は「ヤンキーと地元」に受け入れられたのだろうか?大学院生(かれらには「大学生」と区別がつかなかったようだが)による社会調査として、などという名目は、胡散臭いことこの上なかったに違いない。「ヤンキーと地元」は外部に対し閉鎖的であるはず。この場合、ウチナーンチュもナイチャーも「外部」であることに変わりはない。著者は自身のキャラクターから、「パシリ」を名乗り出て潜り込むことに成功する。ナイチャーで、かれらからすると実は年上のパシリというポジションは、かれらが警戒を解くユニークな要素としてあったということはいえるかもしれない。ナイチャー「差別」はむろんあるとしても、逆にいえば「たしま」(他地域)より関係が遠い。年上であることで、理不尽に暴力を行使することはたいてい控えられるというメリットもあったかもしれない。
いずれにしても、パシリという便利屋に徹し、ときに額に汗してともに働き、ときにヤンチャをし合い、時間をかけて信頼関係を築いていったであろうことは推測できる。それによって閉鎖的であるがゆえに広くに知られなかったかれらの過酷さを私たちに伝えたことの評価は大きい。
それを踏まえた上で、最後に触れたいのが、参与観察者としての著者のスタンスについてである。本書が伝えようとしているのは、『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』がそうであるように、「地元」で生きることの過酷さと、そこから「逃げる」ことの困難さである、と私は読んだ。そのハードな領域と時間をたまさか共有しえた者として(「参与」)、同時に「観察」するという立場はクリティカル=臨界であったはず。そうであればこそ、逆にかれらからも常にクリティカルな眼差しを受けていただろう。それはどのような眼差しであり、それを著者はどのように受けとめたのか。そのことを書いているところもあるが、そのことの意味を吟味した考察を読みたかった。
『ヤンキーと地元』
著者:打越正行
発行:筑摩書房
発行年月:2019年3月25日
2017/02/28
「裸足で逃げる」とは、なんと沖縄の「現実」に刺さるタイトルだろう。あの亜熱帯の夜の、生暖かい、しかしひんやりとしたアスファルトを思わず踏みしめたときの素足の触覚が、混濁したいくつものエモーションを拓き、一条の微かな光線の可能性を喚起させる。コザのゲート通りをゲート側から捉えた夜景の表紙写真と…
2019/08/15
本書は生活史についての理論書である。ポップでキャッチーなタイトルに騙されてはいけない(私は騙された)。ガチガチの理論書である。著者はこれまでの著作において、生活史の聞き取りとは何かを、学術書、語りの「ダダ漏れ」、エッセイ、小説といった多岐にわたるスタイルで伝える試みをしてきたが、まだ伝わって…
2019/08/13
タイトル通り、ライフヒストリーについてのわかりやすいガイドブックである。社会学の研究者を主な対象としているが、その外へ開いていく工夫のある編集となっている。 〈2章 ライフヒストリーの可能性〉(谷富夫)はその中でもガイダンス的な役割を与えられた章である。ライフヒストリーとは何か、どんな意…
2019/08/12
滋賀県琵琶湖東側の被差別部落地域への生活史調査である。 「境界文化」とは、被差別部落の生活が、国家、官僚、大企業などの支配的文化の制度や規範から自由であるだけでなく、それらに抵触し、矛盾し、侵犯し合うことがある「生活の論理」を持っていることを指す。 それを描くには、研究者によるので…
2019/08/11
社会学者として多くの生活史の聞き取りをしてきた著者には、社会学の枠から外れる断片的なエピソードの数々が忘れられない。分析や解釈を施さぬ無意味な断片への偏愛。 最初の章「人生は、断片的なものが集まってできている」でも、お互いに関連性のないエピソードのいくつかが改行を挟んで記される。その中の…
2019/08/10
2013年の発行時に、本書を当時主宰していた沖縄オルタナティブメディア(OAM)の「沖縄本レビュー」寄稿のために読み、レビューした(データはなぜか探し出せなかった)。今回、本書を含め、その後注目を集めることになる岸政彦氏の著作をまとめて読むことにした。それは、これから着手する新しい仕事の参照とするた…
2018/02/24
第1話のタイトルにあるように、この町で生きることはディストピアといって差し支えないほどの、この本に登場する主に若者たちは壮絶な生を過ごしている。それはサウスサイドと自他共に呼称し、行政として括られた一画をさらに差別化する居場所としてある。それを読む多摩川河川敷の向こう側への私の眼差しは冷水を…
2019年08月20日
『未来をつくる図書館 ─ニューヨークからの報告─』菅谷明子
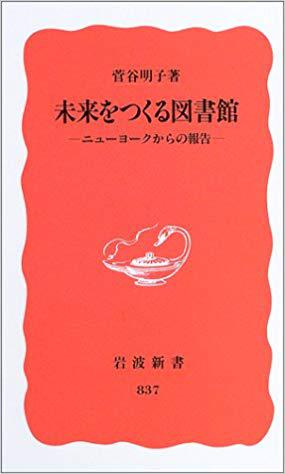
ドキュメンタリー映画『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』より以前に、その魅力を報告していたのが本書。コンパクトに編集されながらも、こちらもかなりの情報量が含まれている。それらをここで後追いし記述することは控え、ここでは一点に絞って論じることにする。
〈第5章 インターネット時代に問われる役割〉で著者は、図書館自体のウェブサイトを経由して数多くの情報を得ることすらできる現在、わざわざ図書館に足を運ばなくても良いではないかという「図書館不要論」に対し、インターネット時代こそ図書館が必要であると述べている。なぜなら、図書館の根本的な役割を究極的にいえば、それは「つなぐ」ことにあるのだから、と。個々のデジタル情報をつなぎあわせ、それらを有機的に結びつけ、新しい意味を作り出す。研究者・作家センターでは、人と人をつなぐことで新しい知が生み出され、黒人文化研究図書館では、記録の断片を紡ぐことで文化を再認識させる、というように。
次に続くパラグラフは著者自身のパッションが示され、本書のなかで私の好きなところだ。
そして、つなぐ作業がこの上なく重要なのは、混沌とした情報社会において、明確な使命を掲げる主体が意思を持って「つなぎ続ける」ことがなければ、情報はすぐに消えてなくなったり、個別に存在しているだけでは意味をなさない場合もあるからだ。そう考えると、図書館は時代を超えて貴重なものであることが明らかになる。しかし、誤解は少なくない。
(214ページ)
まず「使命」は明確でなければ意味がない。それを持つ「主体」そして「意思」をもって、つなぐこと。一度だけでは駄目だ、続けなければ。それが民主主義の時代のピープルである。
そういう人びとがいるからこそ、公共図書館がそこにある、ともいえる。同時に、「育てること」もニューヨーク公共図書館の重要な役割の一つとしてある。育て「続け」なければ、失われるだろう。
「つなぐ」は、図書館側を主体とした場合の能動態である。膨大な投資を引き出し、情報活用者を育成し、アクセスを保証し、ブランド戦略を練る飽くなきその姿勢は、正しく能動態である。しかしワイズマンのドキュメンタリーが見事に捉えているように、そこは情報と市民が「つながる」豊穣な場であり、その都度発生しているのは中動態の世界であるといえないだろうか。そのように想像すると、著者が注意深く鉤括弧をつけて表現した「つなぐ」という、情緒的に安易に使われがちな言葉を刷新できそうな気がする。
さて、私(たち)は、「地元」で、何から始めらたよいだろうか。ほとんど途方にくれる。「使命」を明確にせよ、とパブリックな呼びかけが聞こえる。
『未来をつくる図書館 ─ニューヨークからの報告─』
著者:菅谷明子
発行:岩波新書
発行年月:2003年9月19日
2019/08/19
ドキュメンタリー映画『ニューヨーク公共図書館』の国内ヒットを受け、映画以前にいち早く同図書館の魅力を伝えた『未来をつくる図書館 ─ニューヨークからの報告─』の著者で米在住ジャーナリストの菅谷明子さんによるトークイベント「ニューヨーク公共図書館と米国の本をめぐる多様な取り組み」が18日、国立本店にて開催…
2019/06/02
パブリック(公共)という言葉の意味はこういうことなのだ、と今更ながら知らされる。それはピープルと極めて親和的であるということである。日本では公共=お役所であり、ピープルからは哀しく遠い。 この場所では、本の貸し出し・蔵書はその役割のほんの一部であるということが映し出され、この映画に関心を…
2019/08/18
京浜東北線蕨駅から徒歩6分の Antenna Books &; Cafe ココシバで開催された「 アジアの本屋さんの話をしよう ココシバ著者トーク」に参加した。出版ジャーナリストの石橋毅史さんが新著『本屋がアジアをつなぐ』にまつわる話を写真も交えながら展開。ソウル、香港、台北のユニークな書店の生まれた背景など、興味深い内…
2019/08/08
表題に関わる広範囲のアクターたちのインタビューと論考を網羅しているが、総じて期待していたほど集中して読むことができなかった。その中で、最後の内沼晋太郎「不便な本屋はあなたをハックしない」を興味深く読むことができた。 インターネットの情報が私企業に操られることに警鐘を鳴らすインターネット…
2014/12/01
レンタルビデオチェーン「TSUTAYA」が図書館を運営、しかも店内には「スターバックス」が出店という佐賀県「武雄市図書館」のニュースには、ふだんから図書館を利用するしないにかかわらず、関心を持たれた方も多いのではないか。以降、無料貸し出しの公立図書館に営利サービスが導入されることの是非について少なくない…
2019/01/06
中学に入学し、初めて英語を学び、能動態と受動態という2つの態がある(それだけしかない)と教えられた。だが、日常的に用いている言動として、この2つでは括れない場合があるのではという漠たる疑問があった。本書によれば、中動態という態が、古代からインド=ヨーロッパ語に存在したという。中動態というと、…
2019年08月19日
ニューヨーク公共図書館と米国の本をめぐる多様な取り組み
ドキュメンタリー映画『ニューヨーク公共図書館』の国内ヒットを受け、映画以前にいち早く同図書館の魅力を伝えた『未来をつくる図書館 ─ニューヨークからの報告─』の著者で米在住ジャーナリストの菅谷明子さんによるトークイベント「ニューヨーク公共図書館と米国の本をめぐる多様な取り組み」が18日、国立本店にて開催され(主催は「ほんとまち編集室」)、満席になった参加者は熱心に耳を傾けた。以下、個人的な関心から要所をまとめてみた。

まず、ニューヨーク公共図書館は本のみを扱う場所ではなく、くらしそのものに情報が重要であるという認識があり、そのためのサポートとしての役割が基本にあるという点が挙げられる。アメリカ人の多くは自ら情報を取りに行く習慣があるため、個々のニーズごとの窓口が存在するということになってくる。
就職・起業・ビジネス支援は、あくまでコストと利益を考えて、公金と民間資金から投資を引き出す。アーティストを支える舞台芸術図書館では、情報は文字だけでなく映像や音声がメインとなる。このあたりは映画でも詳しく描かれていて、「え、こんなことも図書館で?」という驚きのリアクションとなる。
情報リテラシーの育成については、情報を加工しアウトプットすることの重要性が、それに乏しい日本との比較において語られた。
また、物理的空間に集う意義として、アメリカではもともと読書会が盛んであり、後半の質疑で紹介された「one city one story」という、一つの街で一冊の本を市民が読む試みや様々なブックフェスが行われるという。
菅谷さんが強調したニューヨーク公共図書館の強さとは、「最も強い者が生き延びるのではなく/最も賢い者が生き延びるではなく/唯一生き延びるのは、変化できる者である」というダーウィンの言葉にある、変化を厭わない精神である。日本人は何かと定められたルールを守ることに従順だが、アメリカ人にとって、ルールはその時々の状況に応じて変えていくものである、と。
時間がじゅうぶん設けられた後半の質疑応答では、中身の濃いやりとりが生まれた。
そもそもこのような図書館が成り立つには、幼少時からの教育が日本とは異なる。active readingといって、とにかく本を読む習慣をつくる。事実と意見を分けること、証拠はどこにあるかを意識すること、批評的に読むことなどが徹底される。
「出版社との関係はどうなのか?」という質問に対しては、いかに本を読む層を育てていくかで利害が一致するため、関係は良好だという。出版社にとって、図書館利用者は潜在的な顧客でもあるのだ。
「どうすればコミュニティのニーズをつかむことができるか?」という図書館司書の方からの質問に対して菅谷さんは、「図書館の外に出てアウトリーチすること」と即答。たとえば、休日を利用してアウトリーチに出かけ、後日上司に報告してみるところから始めるのはどうかと具体的なアドバイスをした。
個人的には、「これをやったことで結果、何が変わるのかを明確にすること」という菅谷さんのメッセージが、「ニューヨーク公共図書館的ななにか」に至る、遠くても確実な道となるのではないかと感じた。
なお、アップリンク吉祥寺で映画『ニューヨーク公共図書館』20日(火)12時50分の回の上映終了後、菅谷さんのトークショーが予定されている。

まず、ニューヨーク公共図書館は本のみを扱う場所ではなく、くらしそのものに情報が重要であるという認識があり、そのためのサポートとしての役割が基本にあるという点が挙げられる。アメリカ人の多くは自ら情報を取りに行く習慣があるため、個々のニーズごとの窓口が存在するということになってくる。
就職・起業・ビジネス支援は、あくまでコストと利益を考えて、公金と民間資金から投資を引き出す。アーティストを支える舞台芸術図書館では、情報は文字だけでなく映像や音声がメインとなる。このあたりは映画でも詳しく描かれていて、「え、こんなことも図書館で?」という驚きのリアクションとなる。
情報リテラシーの育成については、情報を加工しアウトプットすることの重要性が、それに乏しい日本との比較において語られた。
また、物理的空間に集う意義として、アメリカではもともと読書会が盛んであり、後半の質疑で紹介された「one city one story」という、一つの街で一冊の本を市民が読む試みや様々なブックフェスが行われるという。
菅谷さんが強調したニューヨーク公共図書館の強さとは、「最も強い者が生き延びるのではなく/最も賢い者が生き延びるではなく/唯一生き延びるのは、変化できる者である」というダーウィンの言葉にある、変化を厭わない精神である。日本人は何かと定められたルールを守ることに従順だが、アメリカ人にとって、ルールはその時々の状況に応じて変えていくものである、と。
時間がじゅうぶん設けられた後半の質疑応答では、中身の濃いやりとりが生まれた。
そもそもこのような図書館が成り立つには、幼少時からの教育が日本とは異なる。active readingといって、とにかく本を読む習慣をつくる。事実と意見を分けること、証拠はどこにあるかを意識すること、批評的に読むことなどが徹底される。
「出版社との関係はどうなのか?」という質問に対しては、いかに本を読む層を育てていくかで利害が一致するため、関係は良好だという。出版社にとって、図書館利用者は潜在的な顧客でもあるのだ。
「どうすればコミュニティのニーズをつかむことができるか?」という図書館司書の方からの質問に対して菅谷さんは、「図書館の外に出てアウトリーチすること」と即答。たとえば、休日を利用してアウトリーチに出かけ、後日上司に報告してみるところから始めるのはどうかと具体的なアドバイスをした。
個人的には、「これをやったことで結果、何が変わるのかを明確にすること」という菅谷さんのメッセージが、「ニューヨーク公共図書館的ななにか」に至る、遠くても確実な道となるのではないかと感じた。
なお、アップリンク吉祥寺で映画『ニューヨーク公共図書館』20日(火)12時50分の回の上映終了後、菅谷さんのトークショーが予定されている。
2019/06/02
パブリック(公共)という言葉の意味はこういうことなのだ、と今更ながら知らされる。それはピープルと極めて親和的であるということである。日本では公共=お役所であり、ピープルからは哀しく遠い。 この場所では、本の貸し出し・蔵書はその役割のほんの一部であるということが映し出され、この映画に関心を…
2019/08/18
京浜東北線蕨駅から徒歩6分の Antenna Books &; Cafe ココシバで開催された「 アジアの本屋さんの話をしよう ココシバ著者トーク」に参加した。出版ジャーナリストの石橋毅史さんが新著『本屋がアジアをつなぐ』にまつわる話を写真も交えながら展開。ソウル、香港、台北のユニークな書店の生まれた背景など、興味深い内…
2019/08/08
表題に関わる広範囲のアクターたちのインタビューと論考を網羅しているが、総じて期待していたほど集中して読むことができなかった。その中で、最後の内沼晋太郎「不便な本屋はあなたをハックしない」を興味深く読むことができた。 インターネットの情報が私企業に操られることに警鐘を鳴らすインターネット…
2014/12/01
レンタルビデオチェーン「TSUTAYA」が図書館を運営、しかも店内には「スターバックス」が出店という佐賀県「武雄市図書館」のニュースには、ふだんから図書館を利用するしないにかかわらず、関心を持たれた方も多いのではないか。以降、無料貸し出しの公立図書館に営利サービスが導入されることの是非について少なくない…
2019年08月18日
アジアの本屋さんの話をしよう ココシバ著者トーク
京浜東北線蕨駅から徒歩6分の Antenna Books & Cafe ココシバで開催された「 アジアの本屋さんの話をしよう ココシバ著者トーク」に参加した。出版ジャーナリストの石橋毅史さんが新著『本屋がアジアをつなぐ』にまつわる話を写真も交えながら展開。ソウル、香港、台北のユニークな書店の生まれた背景など、興味深い内容が語られた。
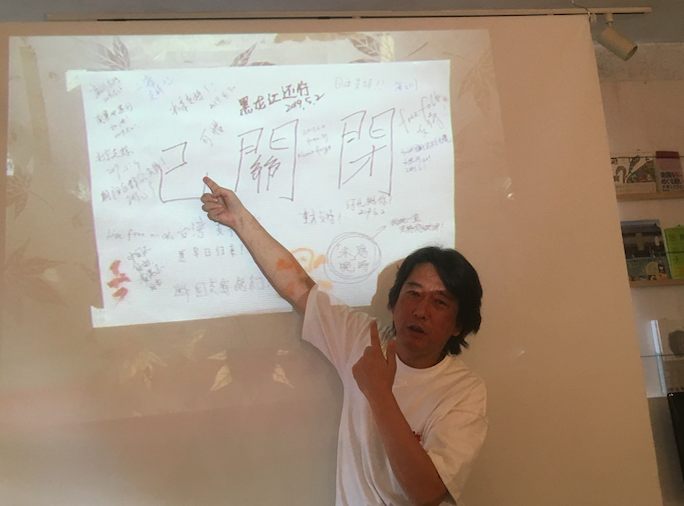
東京新聞での連載をまとめた同書の中から、石橋さんが特に話をしたいということで、中国本土の禁書を扱い、中国当局に長期間拘束された香港の「銅鑼湾書店」の店長をしていた林栄基さんへのインタビューについて時間が割かれた。同書店が成立したことについて、中国は自由であるべきだという政治的信念だけでなく、それらの本が売れるから売るという商売としてあったという。林さんは台湾でも同じような書店を開くつもりだという最新情報も披露された。
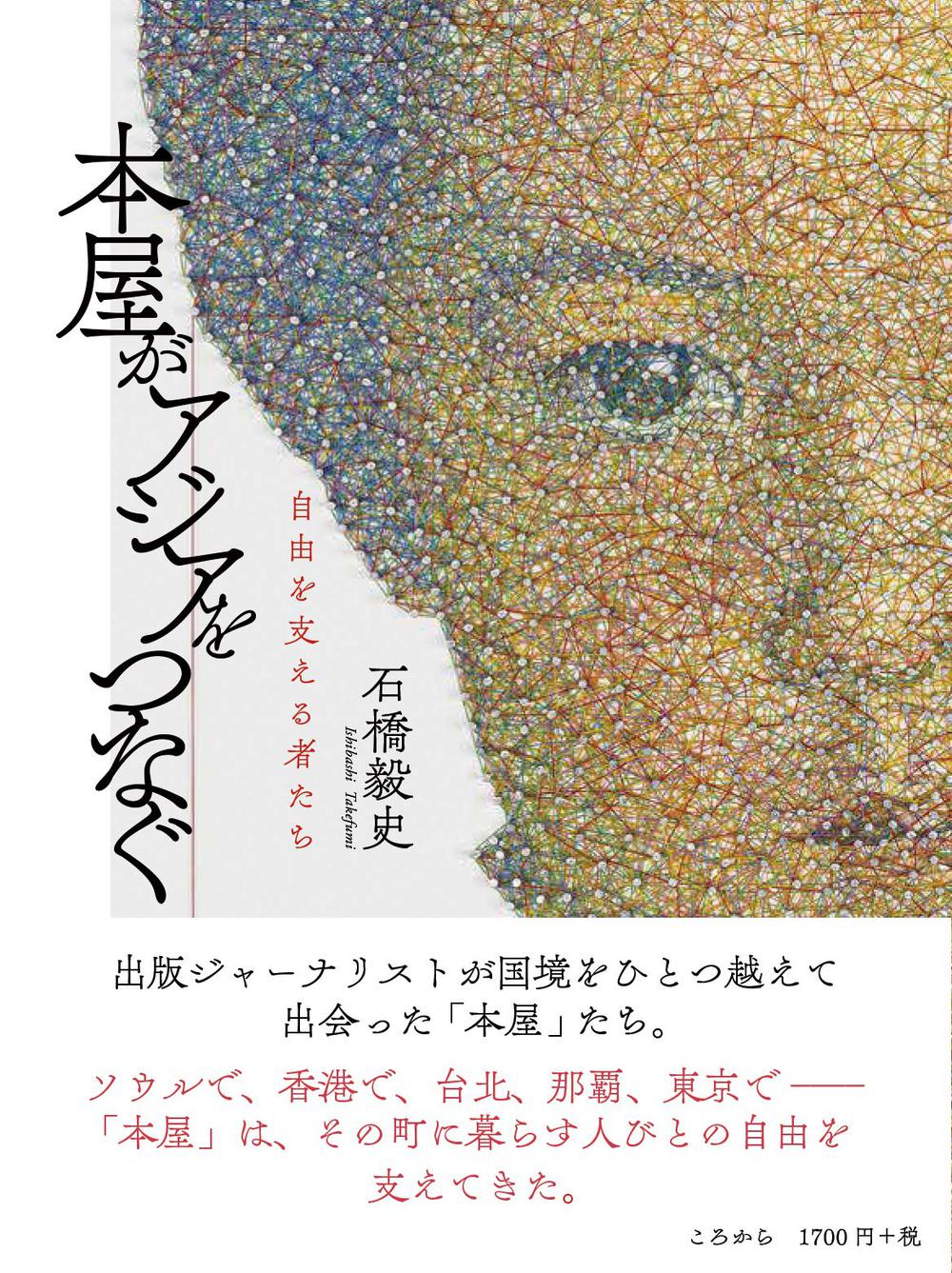
石橋さんは同書を書いた動機について、本屋が必要だということ、そしてそれが社会的必要性があってこそであることを強調した。日本と違う点は、市民の政治的成熟度の熱量にあることも加えられた。
なお、本書の版元である「ころから」は赤羽にある小さな出版社で、出版不況に対し、書店への直接卸しができるトランスビュー社の制度を採用するなど挑戦的な試みをしている。この日は代表の方も参加され、トークをフォローされていた。

一度訪れてみたかったココシバは、ゆるい雰囲気を出していて、しかしながら選書にしてもカフェメニューにしてもセンスの良さを感じさせる。とても気に入ってしまった。

イベント目的ではなく常連客としてカウンターに座っていたクルド人のご家族による手作りのお菓子がお裾分けされた。男性は滞在許可が下りず1年5ヶ月の長きにわたり入管に拘留され、不当な扱いを受けてきたという。その間支援をしてきたココシバには、クルド人コミュニティとの信頼関係がうかがえ、地域独自の課題とともにある場として機能していることがなによりすばらしい。
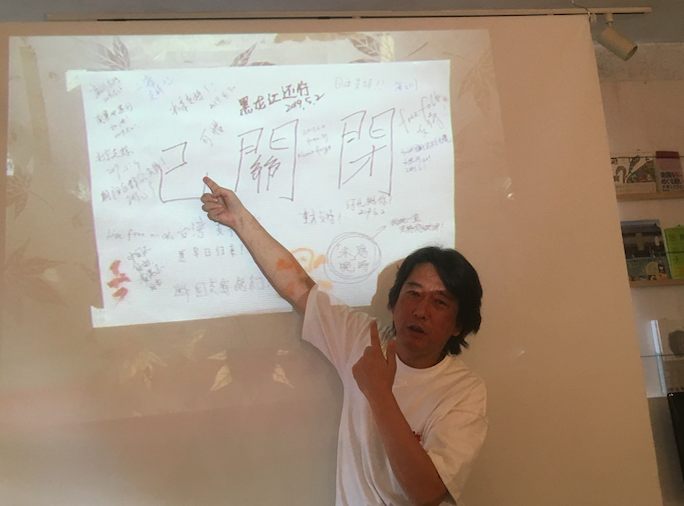
東京新聞での連載をまとめた同書の中から、石橋さんが特に話をしたいということで、中国本土の禁書を扱い、中国当局に長期間拘束された香港の「銅鑼湾書店」の店長をしていた林栄基さんへのインタビューについて時間が割かれた。同書店が成立したことについて、中国は自由であるべきだという政治的信念だけでなく、それらの本が売れるから売るという商売としてあったという。林さんは台湾でも同じような書店を開くつもりだという最新情報も披露された。
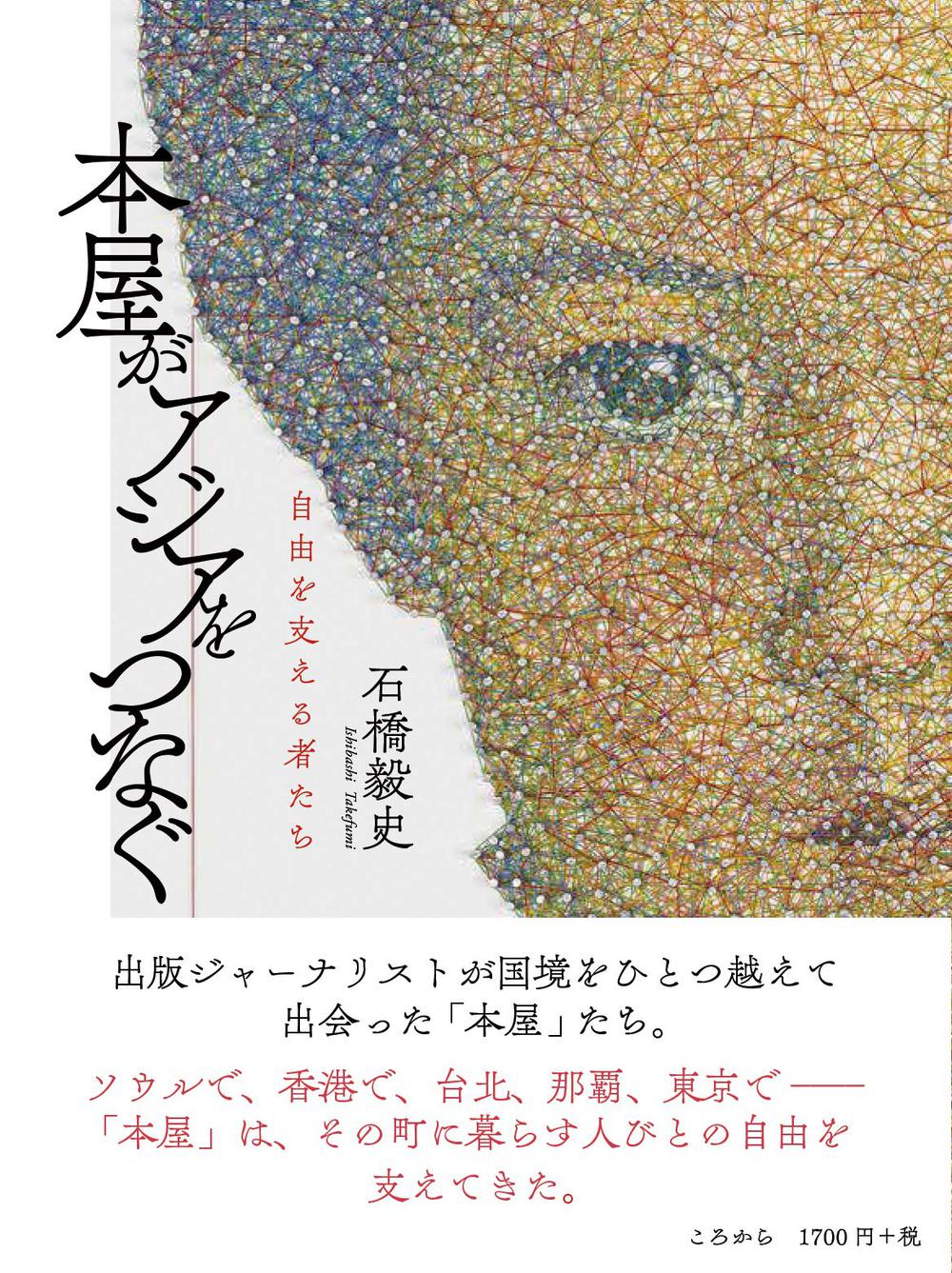
石橋さんは同書を書いた動機について、本屋が必要だということ、そしてそれが社会的必要性があってこそであることを強調した。日本と違う点は、市民の政治的成熟度の熱量にあることも加えられた。
なお、本書の版元である「ころから」は赤羽にある小さな出版社で、出版不況に対し、書店への直接卸しができるトランスビュー社の制度を採用するなど挑戦的な試みをしている。この日は代表の方も参加され、トークをフォローされていた。
一度訪れてみたかったココシバは、ゆるい雰囲気を出していて、しかしながら選書にしてもカフェメニューにしてもセンスの良さを感じさせる。とても気に入ってしまった。
イベント目的ではなく常連客としてカウンターに座っていたクルド人のご家族による手作りのお菓子がお裾分けされた。男性は滞在許可が下りず1年5ヶ月の長きにわたり入管に拘留され、不当な扱いを受けてきたという。その間支援をしてきたココシバには、クルド人コミュニティとの信頼関係がうかがえ、地域独自の課題とともにある場として機能していることがなによりすばらしい。
2019/08/08
表題に関わる広範囲のアクターたちのインタビューと論考を網羅しているが、総じて期待していたほど集中して読むことができなかった。その中で、最後の内沼晋太郎「不便な本屋はあなたをハックしない」を興味深く読むことができた。 インターネットの情報が私企業に操られることに警鐘を鳴らすインターネット…
2014/12/01
レンタルビデオチェーン「TSUTAYA」が図書館を運営、しかも店内には「スターバックス」が出店という佐賀県「武雄市図書館」のニュースには、ふだんから図書館を利用するしないにかかわらず、関心を持たれた方も多いのではないか。以降、無料貸し出しの公立図書館に営利サービスが導入されることの是非について少なくない…
2019年08月15日
『マンゴーと手榴弾─生活史の理論─』岸政彦

本書は生活史についての理論書である。ポップでキャッチーなタイトルに騙されてはいけない(私は騙された)。ガチガチの理論書である。著者はこれまでの著作において、生活史の聞き取りとは何かを、学術書、語りの「ダダ漏れ」、エッセイ、小説といった多岐にわたるスタイルで伝える試みをしてきたが、まだ伝わっていないだろうという強迫観念からか、あるいはたんにしつこく書きたいだけなのか定かでないが、今回は「これでもか」とばかりに、先行する生活史法の批判も徹底させながら展開している。
それは一言でいえば、語りを聞くということは、鉤括弧を外すということである。鉤括弧を外すといえば、語り手の語りに施す引用符をつけないことかと思う。なるほど、これまでの著作は、どれもそのようなスタイルをとっている。地の文とはスペース、インデントなどによって一応の区分けはされるが、地の文との混入による一体感のような独特の印象を読者に与えているが。
しかしそれは表面的な問題であり、鉤括弧を施すことによって、語られている内容と語りそのもの(形式)が切り離されてしまうのではないか、そもそも両者は切り離すことができないのではないかといっている。それは語り手と聞き手による共同作業であり、「私たちは、あるひとつの、あるいは複数の規範的な関係性のなかに、長い時間をかけて引き込まれるのである」(〈マンゴーと手榴弾──語りが生まれる瞬間の長さ〉)というように、持続的な実感そして実践としてある。「引き込まれる」という言葉からは、「中動態の世界」(國分功一郎)さえ、私は想像してしまう。
本書で語られる生活史は沖縄での聞き取り調査によるものがほとんどである。興味深いのは、著者にとって沖縄の語りを聞くことが、理論をより促すと思えるところである。というか、それこそ両者は相補的な関係にある。生活史を含む、沖縄についてのあらゆる定説的な言説と著者が聞き取る語りとの違和が、鉤括弧を外すその瞬間にあらわになる、というように。
飢えで苦しむ沖縄戦の渦中に貴重な食料補給となっ小麦粉が、日本軍の特攻機の攻撃で撃沈した米軍の軍艦から浜辺に流れてきたものであった、その小麦粉。普天間基地の近くに新築した家に住む女性の語りからは、「嫌なら出ていけばいい」という排除の言葉でその責任を負わせることの軽さとは比較にならない、そこで生きている個人の日々の暮らしがある。ヤンキーグループの男と半ばレイプのような初体験をした後に、女子中学生が友だちの家に逃れ、飲みたいというココア。これらのディテールはどれも、「何かについて自分たちも何か言いたくなる」瞬間に現れる。それは同時に「一般的なもの、普遍的なもの、実在するものに触れた瞬間である」。
これらの語りの多くが沖縄戦体験者、基地周辺住民、下層に属する若者というように、マイノリティといってよい人たちによるものであるのに対し、〈沖縄の語り方を変える──実在への信念〉の語りはやや異なる。それは地域誌の編纂に関わる若い世代の語りとして紹介される。これまでの沖縄の地域誌そして民俗学は、沖縄戦によって壊滅的な被害を受けたことで奪われてしまった独自の文化を対象としてきた。これらの書き手たちにとって、その独自の文化は自明でありずっと前からそうだったものとしてある。ところが、著者によれば、それはむしろ逆で、沖縄戦で奪われた後に実体化され、研究の対象となり、再び見出されたというのが正しいのではないか、と。
それに対し、中南部にある合併されてできた「A市」史編纂室のM氏は、新興住宅地を現代版の「屋取(ヤードウイ)」(琉球士族出身の寄留民たちが作った村)であると語り、それを聞き取りの対象とする、これまでにない画期的な取り組みを実践している。著者はこの語りかえを、従来のそれらに比べ、「より事実に合致したもの」「より真正なもの」として捉えられ、沖縄の語り方を変えることを意味すると評価する。
「沖縄らしさが失われていく」という語りから距離を置いたこの手の認識は、沖縄のある年代から下の世代において、むしろありふれているというのが、私の沖縄での生活感覚としてある。ただ、それは公的な場で語られることが少ない。だから外から見れば、新しく感じられるだろう。著者もそれはわかったうえで、あえて「実在への信念」という見得を切るような言葉でアジテートしている。その「世俗化」された語りについて、今後多くの議論が生まれることを期待したい。
『マンゴーと手榴弾─生活史の理論─』
著者:岸政彦
発行:勁草書房
発行年月:2018年10月20日
2019/08/13
タイトル通り、ライフヒストリーについてのわかりやすいガイドブックである。社会学の研究者を主な対象としているが、その外へ開いていく工夫のある編集となっている。 〈2章 ライフヒストリーの可能性〉(谷富夫)はその中でもガイダンス的な役割を与えられた章である。ライフヒストリーとは何か、どんな意…
2019/08/12
滋賀県琵琶湖東側の被差別部落地域への生活史調査である。 「境界文化」とは、被差別部落の生活が、国家、官僚、大企業などの支配的文化の制度や規範から自由であるだけでなく、それらに抵触し、矛盾し、侵犯し合うことがある「生活の論理」を持っていることを指す。 それを描くには、研究者によるので…
2019/08/11
社会学者として多くの生活史の聞き取りをしてきた著者には、社会学の枠から外れる断片的なエピソードの数々が忘れられない。分析や解釈を施さぬ無意味な断片への偏愛。 最初の章「人生は、断片的なものが集まってできている」でも、お互いに関連性のないエピソードのいくつかが改行を挟んで記される。その中の…
2019/08/10
2013年の発行時に、本書を当時主宰していた沖縄オルタナティブメディア(OAM)の「沖縄本レビュー」寄稿のために読み、レビューした(データはなぜか探し出せなかった)。今回、本書を含め、その後注目を集めることになる岸政彦氏の著作をまとめて読むことにした。それは、これから着手する新しい仕事の参照とするた…
2017/02/28
「裸足で逃げる」とは、なんと沖縄の「現実」に刺さるタイトルだろう。あの亜熱帯の夜の、生暖かい、しかしひんやりとしたアスファルトを思わず踏みしめたときの素足の触覚が、混濁したいくつものエモーションを拓き、一条の微かな光線の可能性を喚起させる。コザのゲート通りをゲート側から捉えた夜景の表紙写真と…
2019年08月13日
『新版 ライフヒストリーを学ぶ人のために』谷富夫編
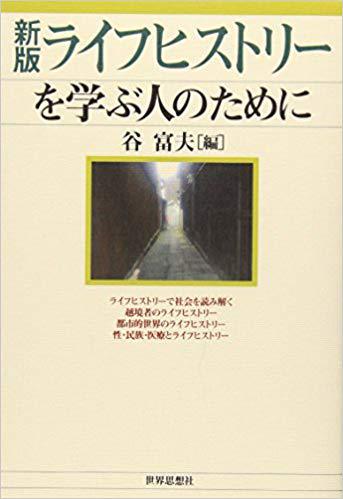
タイトル通り、ライフヒストリーについてのわかりやすいガイドブックである。社会学の研究者を主な対象としているが、その外へ開いていく工夫のある編集となっている。
〈2章 ライフヒストリーの可能性〉(谷富夫)はその中でもガイダンス的な役割を与えられた章である。ライフヒストリーとは何か、どんな意義があるのかの例として、谷自身の調査を引用する次の箇所は明快である。
それは1980年代に谷が沖縄研究をしていた過程で出会ったある若者のエピソードである。彼は1972年8月15日正午、高校野球「南九州代表校」の主将として、甲子園球場のバッターボックスに立っていた。いうまでもなく、沖縄の本土復帰の記念すべき年の大会である。試合は北関東代表校を相手に、8回表、3対5の2点差、走者2・3塁、一打同点の好機到来。
ここで彼の語りが引用される。そのときちょうど正午のタイミングで試合が中断され、1分間の黙祷が行われた後、彼は三振してしまう。「それまで燃え上がっていたものが、黙祷でスーッと冷えきった感じでした」と。沖縄には6月23日の慰霊の日があり、終戦記念日は「私ら関係ないですから。あれが野球を諦めるひとつの機会になりましたね」と語る。
ここでは、彼の語りを通し、本土の終戦記念日と異なる沖縄の慰霊の日の歴史的背景が際立つ点に価値がある。さらには、翌日の全国紙はこの様子を「感動的な」調子で報道し、彼にとっての三振を、人生においてきわめて重要な転換の契機として意味づけることはしなかったということがつけ加えられ、マスメディアの報道との役割の違いにも注意が向けられる。
〈3章 沖縄出稼ぎ者と定住──異文化接触と同化過程〉(石原昌家)では、1980年に大阪府宝塚市高松町の「沖縄ムラ」で行った聞き取り調査が例に挙げられる。戦前からの出稼ぎ者の来歴、敗戦による生活の均一化、沖縄人連盟の結成と沖縄救援活動、そして本土化と沖縄の反応など、石原の研究が概観される。様々な差別や軋轢などがありながらも、沖縄出稼ぎ者あるいは集団就職者たちは本土に「同化」し、そのことで逆に「ウチナーンチュとしてのアイデンティティ」を確認する動きが生まれたとまとめられる。
石原にとって、ライフヒストリー研究の対象者は、マイノリティやマージナルな集団に属する人たちであり、「その生の声をとおして社会の暗部や周縁部から社会全体を逆照射していく(社会全体を見渡す)うえで有効である」。
岸政彦の『同化と他者化』の後から読むと、岸がこの先行研究を批判的に読み、自らの問いを発見していったことが推測できる。
その他にも、在日韓国・朝鮮人の「世代間生活史」、寄せ場の生活史法、大阪特有の文化住宅から見た低階層集住地域における教育・地位達成など、様々な研究対象とそのための方法が報告される。
『新版 ライフヒストリーを学ぶ人のために』
編者:谷富夫
発行:世界思想社
発行年月:2008年9月10日
2019/08/12
滋賀県琵琶湖東側の被差別部落地域への生活史調査である。 「境界文化」とは、被差別部落の生活が、国家、官僚、大企業などの支配的文化の制度や規範から自由であるだけでなく、それらに抵触し、矛盾し、侵犯し合うことがある「生活の論理」を持っていることを指す。 それを描くには、研究者によるので…
2019/08/11
社会学者として多くの生活史の聞き取りをしてきた著者には、社会学の枠から外れる断片的なエピソードの数々が忘れられない。分析や解釈を施さぬ無意味な断片への偏愛。 最初の章「人生は、断片的なものが集まってできている」でも、お互いに関連性のないエピソードのいくつかが改行を挟んで記される。その中の…
2019/08/10
2013年の発行時に、本書を当時主宰していた沖縄オルタナティブメディア(OAM)の「沖縄本レビュー」寄稿のために読み、レビューした(データはなぜか探し出せなかった)。今回、本書を含め、その後注目を集めることになる岸政彦氏の著作をまとめて読むことにした。それは、これから着手する新しい仕事の参照とするた…
2019年08月12日
『境界文化のライフストーリー』桜井厚

滋賀県琵琶湖東側の被差別部落地域への生活史調査である。
「境界文化」とは、被差別部落の生活が、国家、官僚、大企業などの支配的文化の制度や規範から自由であるだけでなく、それらに抵触し、矛盾し、侵犯し合うことがある「生活の論理」を持っていることを指す。
それを描くには、研究者によるのではなく、人びとのライフストーリーによって、その歴史観や社会観から語ってもらうしかない。だから、研究者のライフストーリーと人びとのライスストーリーは明確に区別して記載されるべきだと著者はその理論的立場をのべる。だが、その部分に付された注を読むと、「筆者である〈私〉のポジションはどこにあるのかという大きな疑問は残されている」とある。つまり、その立場に揺らぎもみえる。
水利用の優先権、人力車売り、目にかけた女性を仲間数人で「拉致」しなし崩し的に夫婦になってしまう〈はしり〉などなど、語られる「生活の論理」はどれも興味深い。
それらの語りと調査者=著者の地の文が交互に記される。それらはお互いに関連しているので、確かに〈私〉のポジションを特定するのが難しい。それを意識しながら読み進める作業は、生活史の読み方を習得するまではしんどいかもしれない。
『境界文化のライフストーリー』
著者:桜井厚
発行:せりか書房
発行年月:2005年1月30日
2019/08/11
社会学者として多くの生活史の聞き取りをしてきた著者には、社会学の枠から外れる断片的なエピソードの数々が忘れられない。分析や解釈を施さぬ無意味な断片への偏愛。 最初の章「人生は、断片的なものが集まってできている」でも、お互いに関連性のないエピソードのいくつかが改行を挟んで記される。その中の…
2019/08/10
2013年の発行時に、本書を当時主宰していた沖縄オルタナティブメディア(OAM)の「沖縄本レビュー」寄稿のために読み、レビューした(データはなぜか探し出せなかった)。今回、本書を含め、その後注目を集めることになる岸政彦氏の著作をまとめて読むことにした。それは、これから着手する新しい仕事の参照とするた…
2019年08月11日
『断片的なものの社会学』『街の人生』『ビニール傘』岸政彦
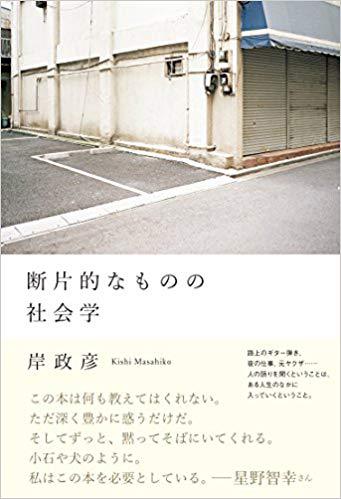
社会学者として多くの生活史の聞き取りをしてきた著者には、社会学の枠から外れる断片的なエピソードの数々が忘れられない。分析や解釈を施さぬ無意味な断片への偏愛。
最初の章「人生は、断片的なものが集まってできている」でも、お互いに関連性のないエピソードのいくつかが改行を挟んで記される。その中の一つは、夜遅く、那覇の58号線を著者がウォーキングしていたときのこと。泊埠頭のリゾートホテルの前を通りがかると、ちょうどエレベーターに乗り込む誰かの影が窓越しに見えた。ただそれだけのことなのだが、著者にとっては誰だかわからない他人と、そのホテルのエレベーターに「一緒に乗り合わせた」という感慨を抱く出来事になる。まったくの他人が、たまたまエレベーターに乗る瞬間を目にした、たまたま夜の街を歩いていた私という(無)関係性において。
「だからなんだ?」とツッコミたくなるが、次の断片を読むと少し納得できる。著者の少年時代のエピソードとして、道ばたに落ちているなんの変哲もない小石を拾い上げ、惹きつけられる瞬間。少年がその小石に意識を集中すると、やがて他の小石とは異なる、世界にたったひとつの「この小石」になる瞬間が訪れ、そのことに陶酔していたという。世界にひとつしかないものを発見した驚きにではなく、それが世界中の路上に無数に転がっていることに。
つまり、特殊でないものを眼差し、そこに「この」もの(固有性)を見出し、しかしながらその固有性に価値を見出すのではなく、反対に、それが無数にあることに安堵する、という。
これに似た経験は、いや、ものの見方は、私にもある。孤独な内面を意識しながら街を歩くときなどに顕著に。出くわす他者をモノとして情報処理する数秒毎の自身の知覚に抗い(あるいは疲れ)、そのひとりひとりの個別性に意識を向けたくなる情感の発露として。著者の本が評価されるのは、同じように「あるある」とうなづく読者が多いからだろうか。
しかしながら、これを社会学者が出会った「解釈できない出来事」(版元内容説明)などと、あたかもそこに新しい価値があるかのような評価をするのは違うのではないか。一言でいえば、これは主観の倒錯である。柄谷行人がかつて国木田独歩に見出した「風景の発見」そのものである。
国木田独歩の『忘れえぬ人々』(明治31年)は、無名の文学者である大津が、多摩川沿いの宿で知り合った秋山という人物に、「忘れえぬ人々」について語る。大津にとって「忘れえぬ人は必ずしも忘れて叶ふまじき人にあらず」、ふつうなら忘れてしまっても構わないが忘れられない人々のことである。その例として、かつて憂愁に沈みつつ瀬戸内海を汽船で渡ったとき一瞬目にした、小さな島で磯を拾っている男の姿を挙げる。大津は、この男を「人」というより「風景」として見ている。
しかし、この話にはオチがある。この宿での語り合いから二年後、東北のある地方で一人瞑想に沈む大津の机の上に「忘れえぬ人々」が置いてある。その最後に書き加えてあったのは「亀屋の主人」であって、「秋山」ではなかった、と。
柄谷は、「風景」がこのような倒錯においてこそ見出されること、風景はたんに外にあるのでなく、風景が出現するためには、いわば知覚の容態が変わらなければならないと批評する。
ここには、「風景」が孤独で内面的な状態と緊密に結びついていることがよく示されれている。この人物は、どうでもよいような他人に対して「我もなければ他もない」ような一体性を感じるが、逆にいえば、眼の前にいる他者に対しては冷淡そのものである。いいかえれば、周囲の外的なものに無関心であるような「内的人間」 inner man において、はじめて風景が見出される。風景は、むしろ「外」をみない人間によって見出されたのである。
(『定本柄谷行人集1 日本近代文学の起源』24ページ)
近代文学の「風景」とはこのような倒錯によって「発見」された。しかし、その後その起源は忘却され、なんでもない風景を描写し、そこに意味を見出す近代文学の装置を内面化した我々がいる。本書を読んで「あるある」とうなづいた私もあなたも、すでにそれを内面化し、そもそもの起源を忘れている。文学から区別されるはずの社会学者であっても、それは同じである。
自らの認識が倒錯していることに自覚的かどうか。次の章「誰にも隠されていないが、誰の目にも触れない」は、そのことに関わる。
冒頭で、どんな人でも「語り」を内側に持っていて、「何事もない、普通の」物語を生きていると記される。聞き取りの現場では、日常では隠されたそれら無数の物語が姿を現す。だが、そもそもそれらの物語は隠されているわけではなく、われわれの目の前にあって触れることができるのに、われわれがそれに気づいていないだけではないか、と著者は説く。
しかし、次に続くのはそんな聞き取りの現場での普通の「語り」ではない。唐突に、架空の話を書くとの宣言があり、ある若い夫婦の話が挿入される。静かに毎日を暮らしているその夫婦はある日旅行の計画を立てる。心配性の妻は空き巣対策として、夫には内緒で二人の生活を録音し、その音声データを留守中の部屋にエンドレスで流しっぱなしにする。二人は旅先で車の転落事故にあい死亡する。後日、人びとがその部屋に入り、二人の生活の音を聞き、すでにこの世にいないものが、思いもよらなぬかたちで残されていたことを知る。
二人の声は、二人が生きていたときにはなんの価値もない平凡なものだったが、「語り手」が失われると、それがかけがえのないもの、大切な形見に変容する。それが「ロマンチックな、あるいはノスタルジックな物語」であり、「まったく意味のない凡庸な存在が、ある悲劇や喪失をきっかけとして重要な意味を持つ」ドラマの構造として提示したことを、著者は解き明かす。
だが、少年時代の著者が「この小石」が無数に転がっていることに陶酔するのは、この「ロマンチックな物語」の定石に対してではないはずである。そこで著者は、凡庸なものが凡庸なままであったらどうか、という問いを設定する。すなわち、二人が無事に旅行から帰ってきたとしたら、二人は部屋に流れる自分たちの音声を聞いて笑いあい、そしてそのデータは二度と再生されることなく、忘れ去られるだろう。だとすれば、痛切なのは、最初の物語より後者の何事もなかった現実のほうである、と著者はいう。二人の音声のかけがえのなさは、二人にとっても、「私たち」にとっても知り得ないのであるから。その意味で「二重に無意味なものとなる」と。
さらに、著者は次のステージを用意する。それは、そもそもわれわれがこの二人の存在を知らないこと、二人が旅行に行ったかどうかも、その後無事だったかどうかも、二人の会話を再生していたかどうかも、まったく知らないという事態である。先に挙げた二つの物語のかけがえのなさは、私たちが、二人が死ぬことを先に知っていることを前提としている。これに対して、もっともかけがえのないものとは、「私たち」にとってすら、知られることも、いかなる感情を呼び起こされることもないような何かである、と。
ここまでを整理する。社会学者である著者にとって、聞き取りの現場で聞く「何事もない、普通の」物語は、その断片的な語りは、「無意味」であるからこそ美しい。それは、その「語り」を聞き取ることで初めて知ることができる。そのような普通の物語が実は世界には無数にあることをうかがい知ることが、そこで初めてできる。だが、それを知ることは、その語りの「かけがえのなさ」が減じることでもある。なぜならば、もっともかけがえのないことは、そのような無意味さが世界中に無数にあることを「私たち」が知らないことによって成り立つものであるのだから。
著者にとって、世界は意味のあることだけで成り立つわけではない。むしろ、無意味なものが無数にあることで成り立っている。その真実は「誰にも隠されていないが、誰の目にも触れない」。那覇のリゾートホテルの窓越しから、エレベーターに入りこむ誰かの影を見る一瞬とは、それが顕現するギリギリの時間差であり視差であった。私たちは断片的な語りを聞き取ることによって、その一端をうかがい知ることができるのみである。断片的な語りは無意味である。だが、無意味なものを無意味として語る/聞き取ることはそもそも背離である。架空の話をでっち上げることで、それを例示することがかろうじて可能となる。著者は自らが倒錯していることを認識しているからこそ、架空の話を挿入したのだろう。

無意味なものを無意味として提示する試みをしたのが『街の人生』(2014年)である。
『街の人生』の特徴は、五人の生活史の聞き取り内容が、研究テーマや理論的枠組みによって類型化・一般化、分析という社会学的な手法が施されることなく、生の語りがテープ起こしのように記録されている点にある。五人はそれぞれ、日系南米人のゲイの青年、ニューハーフ、摂食障害の当事者、シングルマザーの風俗嬢、元ホームレスの西成のおっちゃんというように、広い意味でマイノリティに属する人たちである。それでも著者によれば、これらは普通の人びとであり、その断片的な語りは断片的であるからこそ「普遍的な物語」なのだという。その意義はこうである。
いずれにせよ、私たちは彼ら/彼女らの語りを共に聞くことで、ほんの数時間のあいだ、「私ではない私」の人生を垣間みることになるでしょう。私たちは、他人の人生の記憶や時間、感情、経験を、語りを通して共に分かち合うことができます。生活史を読むことは、私たちが生きなかった別の私たちの人生を共有することなのです。
(「はじめに」)
さて、私の読後の感想は、読むのにいささか苦痛を覚え、すべてを読み通すことに難儀した、というものである。それはひとえに、生の語りのテープ起こしの文章を読むことの苦痛による。私(たち)は語りを「聞く」のでななく、読むのであるから。なるほど語られる内容や語りそのものは「面白い」。実際聞き取りの現場にいたら、最後まで興味深く「聞く」ことができたかもしれない。あるいは社会学に携わり、生活史の聞き取りという作業に慣れている立場であれば、その現場を想像し、集中力を切らすことなく最後まで読むことができたかもしれない。ということで、無意味な断片的な語りが美しいかどうか、私にはわからない。
とはいえ、本書が『同化と他者化』と同じ年に発行されているという事実が、私を激しく不意打ちする。そのモヤモヤが今回の岸政彦のテキストをまとめて読むという作業のそもそもの動機づけとしてある。このモヤモヤを晴らすために読み、書いている。

「私たちが生きなかった別の私たちの人生を共有すること」の愉しさは、生活史のテープ起こしを読むことよりも、むしろ小説『ビニール傘』(2017年)を読むことで得られる。
表題作「ビニール傘」の1章では、冒頭、大阪の街を舞台に、何人かの「俺」の語りの断片が続く。タクシー運転手の「俺」、清掃作業員の「俺」、コンビニ店員の「俺」、そしてようやく主人公らしき日雇い作業員の「俺」が登場し、その後2年間同棲する女と「マクド」で出会う場面へと展開する。それぞれの「俺」はかろうじてすれ違うことはあるが、それ以上絡むこともなく、お互いを知ることなく消えていく。あえて三人称にせず、読者の混乱を招いたとしても「俺」という一人称を連続させるのは、それぞれの「俺」を含みすべてを見通すポジション(神の視点)を避け、「俺」たちがお互いのことを知らないことの「かけがえのなさ」を表現したいからに他ならない。
小説はその後、美容院を辞め、ガールズバーで働いているが、部屋で眠り続けている女との静かな生活の断片が叙情的に綴られる。
続く2章は、美由紀という名前で呼ばれる女の一人称に転じる。和歌山の田舎を出てから大阪での生活、そして和歌山に戻るまでのエピソードが、あたかも生活史の語りのように続く。しかし、そこには「俺」の知らない、しかし彼女にとっては重要な出来事のいくつかが語られ(男女関係のもつれから美容院を辞めたこと、ガールズバーで唯一仲の良かった女友だちが自殺し、和歌山に帰るきっかけにもなったことなど)、そして最後まで「俺」について語られることはない。
この美由紀という女が1章に出てくる「俺」の同棲相手と同一人物であるのか否か、「俺」も本人も、そしてそれを読む私たちも知ることがない。そのような「俺」や女たちやらの普通の物語が、不景気の影が覆う大阪の街には無数にある。そしてそれらを私たちは知らない。まさに「私たちが生きなかった別の私たちの人生を共有すること」が、本を読む快楽として成立している。
著者:岸政彦
『断片的なものの社会学』
発行:朝日出版社
発行年月:2015年6月10日
『街の人生』
発行:勁草書房
発行年月:2014年5月20日
『ビニール傘』
発行:新潮社
発行年月:2017年1月30日」
2019/08/10
2013年の発行時に、本書を当時主宰していた沖縄オルタナティブメディア(OAM)の「沖縄本レビュー」寄稿のために読み、レビューした(データはなぜか探し出せなかった)。今回、本書を含め、その後注目を集めることになる岸政彦氏の著作をまとめて読むことにした。それは、これから着手する新しい仕事の参照とするた…
2017/02/28
「裸足で逃げる」とは、なんと沖縄の「現実」に刺さるタイトルだろう。あの亜熱帯の夜の、生暖かい、しかしひんやりとしたアスファルトを思わず踏みしめたときの素足の触覚が、混濁したいくつものエモーションを拓き、一条の微かな光線の可能性を喚起させる。コザのゲート通りをゲート側から捉えた夜景の表紙写真と…
2019年08月10日
『同化と他者化 戦後沖縄の本土就職者たち』岸政彦
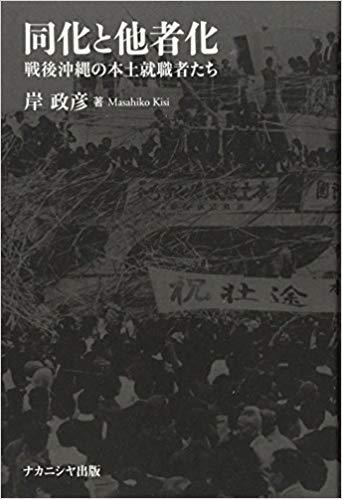
2013年の発行時に、本書を当時主宰していた沖縄オルタナティブメディア(OAM)の「沖縄本レビュー」寄稿のために読み、レビューした(データはなぜか探し出せなかった)。今回、本書を含め、その後注目を集めることになる岸政彦氏の著作をまとめて読むことにした。それは、これから着手する新しい仕事の参照とするためである。私の関心として、第一に、本書は新しい仕事にとって参照項として重要な内容である。第二に、研究書、エッセイ、小説という岸氏のテクストの多彩さと、その評価について注目している。今回は、まず本書を概観する作業にとどめる。次に、それ以降の著作をまとめて論じる。それを受けて、新しい作業に着手してみる。本書を吟味しレビューする作業は、その過程で自然に生じるようにしたい。
本書は、祖国復帰前後に沖縄から本土へ集団就職を体験した人たちへの聞き取り調査を行い、社会学的に分析した報告である。そのほとんどみなに共通するのが、本土でのホームシックや故郷を懐かしむ「ノスタルジックな語り」である。その多くは、被差別体験よりも本土の生活が楽しかったと語られる。だが、その言葉と矛盾するように、大半がその後沖縄にUターンしている。それはなぜかという問いが本書の問題提起である。
〈第一章 戦後沖縄の経済成長と労働の流出〉では、様々なデータ分析が施される。それによれば、沖縄の戦後復興の60年代は経済成長が著しく、その過程において人口移動が本格化し、沖縄社会を根底から変革するような社会変動となった。その特徴は、失業率が低いこの時期に労働力の流出が始まり、復帰後の失業率が高い時期にUターンしているというもの。戦後しばらくの低い失業率は沖縄社会の前近代性によるもので(賃労働につく割合が少なかった)、本土復帰後の近代化プロセスのなかで労働力化率が上昇し、結果、失業率が上昇したことが背景にある。これには、沖縄の貧しさが労働力の流出を促したとされる従来の図式の再考を要する。
〈第二章〉は省略し、〈第三章 本土生活者たちの生活史〉は、高度成長期の本土移動者を対象にした生活史聞き取り調査から選ばれた7名の調査内容が記される。その「ノスタルジックな語り」では、はじめに本土への憧れが語られ、都市での楽しかった暮らしが語られ、「にも関わらず」異郷の地での望郷の感情、すなわち沖縄を離れた後に本土において再構成され再経験される沖縄的なものが熱っぽく語られる。これらは「定型的な語り」といえる。
現在の生活史の方法論においては、定型的な語りは「権力」によって一方的につくられたものであり、それよりも定型的な語りを解体するような語りに価値が置かれるが、著者はそれを反批判する。なぜならば、定型的な語りが必ずしも「権力」によって一方的につくられるものではなく、「それはきわめて個性的で想像力あふれるかたちで語られているからであり、そして、これらの定型的な語りにおいて、ある時代においてあるできごとを共有したものたちが似たような形で語る語りのなかに、そのできごとを理解する鍵があるからである」(264〜265ページ)。
ここで著者は生活史方法論を整理し、自らの立場を確認する。「実証主義的生活史法」では、定型化できない語りの余剰は主要な理論的分析から切り取られる。たとえそれらが示唆的で魅力的なものだと認識したとしても、多くの夾雑物の中から、有意味な語りとそうでないものは振り分けられる。しかし、この態度は、必ずしも調査対象の現実を反映しているとはいえず、研究者の解釈枠組みに語りを一方的に押し込めるものとして批判されている。たとえば、「口承言語」の多様さを近代哲学の同一性を乗り越えるものとして評価する野屋啓一のように。
他方で、構築主義者の桜井厚は、語りとは、支配的文化が保持しているマスター・ナラティブと、それに同調したり対抗したりするコミュニティのモデル・ストーリーの二つに大別できる。関西の被差別部落を長年フィールドワークしてきた桜井によれば、マスター・ナラティブとは「部落を一般化しカテゴリー化する差別の語り」であり、モデル・ストーリーとは「部落解放同盟などによって作り上げられてきた解放の語り」に相当する。語りのなかの「とまどい、矛盾、非一貫性、沈黙」「揶揄、哄笑、冗談、照れ、笑い」などは、支配的なマスター・ナラティブやモデル・ストーリーに対する抵抗と捉えられる。そこでは、これら「大きな物語」に対抗する「小さな物語」の、われわれの解釈枠組みから外れるような語りが重要視される。
これに対し、著者は批判的な立場をとる。長い引用になるが、本書を含むここ数年発行された多ジャンルにわたる著者のテキストを理解する上で重要な箇所である。
だが、語り手が語る語りを、大きな物語への抵抗としてだけ捉えるのは一面的である。まず、大きな物語がわれわれの生活世界から独立してその外部に存在する、という考え方を疑うべきである。しばしば生活世界は、「社会システム」と対立して把握されるだけでなく、システムの論理によって外部から侵略され、その本来の姿を変えてしまったものとして(社会学者によってさえ)表象されるのだが、これは構築主義において大きな物語とそれに抵抗する小さな物語という二項対立として再現されている。この二項対立という(それ自体が大きな物語であるような)解釈枠組みは、要は、大きな物語と小さな物語を本質的に異なるもの──前者は外部から注入されるイデオロギーで、後者はそこから独立した自由意思、といったもの──として前提しているのである。しかし、大きな物語もまた、われわれの日常生活において語られ続けることによってはじめて存在しうるのである。つまり、いかに近代的な物語であっても、それはわれわれ生活者によって欲望され、習得され、新しくつくりかえられ、つねに語られ続けているのである。本章でいくつか紹介した語りの例をみても、大きな物語と小さな物語という区別には意味がない、ということがわかるだろう。これらの語りのなかでは、定型的な語りはそれぞれが非常に印象的で個性的なかたちで語られているのである。
(275〜276ページ)
この社会学者としての理論=批判を足場に対象を沖縄に向ける場合、次のような態度となる。
沖縄という場所はつねに特殊化・他者化され、しかもそれはあこがれや賞賛といった肯定的な感情(あるいは欲望)とともにそうされてきた。したがって、まず第一に、そうした他者化するカテゴリー化から少しでも距離をおき、多様なもの、柔軟なもの、主体的なもの、ふたたび(あるいはまったく新しく)構築されるものとして、つまりは脱カテゴリー化という企てのもとに沖縄を考える必要がある。この必要性を十分に認識したうえで、さらに問わなければならない。あの諸々の定型的な語りは、いったい「どこから」やってくるのだろうか?
(278ページ)
ここまできて、著者は構築主義的生活史法の側に立ちながら、それに違和感を隠さない。同方法では、調査者=聞き手は、「なにを語ったか」より「どう語られたか」を重視するため、語りが「真実か虚偽か」は問わず、オープンな態度を保持することが求められる。それによって、定型的な語りを、なんらかの社会構造によって産出される共通体験をあらわすものとして扱わない、構築主義独特の理論が導き出される。確かに、この方法によれば、沖縄を他者化・特殊化することでその多様性を抑圧する弊害を避けることができる。
だがしかし、それだけでいいのか、と著者は立ち止まる。著者は聞き取りの現場で、ひとりの大和人として立ち会った。そこで定型的な語りが語られたととき、著者は「リアリティの相互構築過程に参与した」。著者の大和人=調査者としての質問や相づちは、調査現場での相互作用を、いわば大文字の「沖縄」について語らせる方向に誘導しただろう。ただし、それはたんに会話を一定の方向へ誘導しただけではない。著者自身が、大文字の沖縄というものに「同意」したのだから。つまり、著者は大文字の沖縄の真理値を空白にすることなく、それを真実のものとして捉えたのである。第二章において、「本土就職の体験とは一見無関係のような語りまで含めて記録したのは、定型的な語りというものが、実は多様なものや過剰なもの、あるいは断片的なものや個人的なものの語りの中にこそあらわれるということを示すためであった」(286ページ)。
〈第四章 本土就職とはなにか〉では、前章の聞き取り調査で分析された「ノスタルジックな語り」について、データを参照しながらその政治的な要因などが明らかにされる。
ここでは特に、初期の集団就職の制度化について、琉球政府労働局を中心とした大規模な「本土送り出しシステム」の顕著な傾向について触れないわけにはいかない。そこにはその一大プロジェクトを何としても成功させなければならないという悲壮感があふれていた。それは大規模な市民運動としての復帰運動の思想とつながっている。当初本土就職希望者が想定より集まらなかったが、労働局にとっては「バラ色の未来」が待っている本土就職を避けるのは、無知や偏見や根拠のない不安感・恐怖感からくる、非合理的な、それゆえ矯正が必要な沖縄の人びとの態度のあらわれとして捉えられた。
労働局がそれほどまでに何としても送り出さねばと焦ったのは、当時の急増する人口問題を解決せねばという問題意識からであった。データが証明するのは、当時の沖縄経済は成長傾向にあり、貧困から外部に職を探すという動機は最大の理由として当てはまらない。
ここで労働局は就職希望者たちに対し、沖縄という前近代的な小さな島から先進的な地域に移動するほどの合理性を備えることを要求し、同時に、配属された職場では労働条件に疑問を持たず従順に従うほどには非合理的な労働者を育成することに努めるという矛盾した態度をとった。
その意味で、1966年に実施された「本土就職者合同訓練」の記録は興味深い。その場では、本土就職者の「身体」に対する管理における「ねじれ」を読みとることができる。そこで行われた講話では、真面目に働くこと、規律を守ることなど生活態度に関することが語られ、後半では沖縄文化を体得し、本土人にそれをアピールすることなどが求められた。つまり、一方で本土就職者を「日本人化」し、他方で「沖縄人化」していこうとしたのである。
復帰運動のリーダー、喜屋武真栄が語った講話の矛盾が意味するものはなにか。それは合宿訓練全体を通じて資本主義的=国民的美徳に相対するものとして沖縄的生き方が設定され、しかも徹底的に否定されていくことである。「沖縄人が日本人になることをめざすことでかえって沖縄人になっていく」という、戦後の沖縄アイデンティティの歴史的構築過程を、それはよくあらわしている。かれらは、日本人化するために、いったん沖縄人化する必要があった。文化的な沖縄化は、日本へ同化するために必要な回路であったが、それがかえって沖縄人の「沖縄人であること」を強化してしまう。
本土と沖縄の関係において沖縄人が完全に「日本人化」されることはない。むしろ、「沖縄人とはだれか」「沖縄人はどう生きるべきか」という果てしない自己言及が、ほかならぬ沖縄人自身によって担われ、結果的に「沖縄人」は強化されていく。その自己言及が、本土へ送り込まれる沖縄人たちの「他者性」の感覚や同郷性、沖縄人アイデンティティを強化していったのではないか。
〈結論 同化と他者化〉。戦後の本土就職における「過剰な還流」、すなわち、本土の生活は楽しかったのに数年でUターンしてしまうという問題を分析する際に、沖縄的同郷性を前提にしていては理解できない部分が残る。なぜ本土移動はノスタルジックに語られるのか?なぜかれらはあこがれた日本に「同化」しなかったのか?
同化せよという命令は、まずわれわれとかれらがどれくらい違うものか、同じになったのかを判定することを人に迫る。この問いかけが他者化を生み出すのである。
最後に、〈序章〉で紹介された、戦後復興期、朝日新聞により本土旅行を招待された一人の沖縄の少年の現在について触れられる。〈序章〉のなかで、本土への憧れいっぱい胸に抱えた少年は、見るもの聞くものすべてが未知の旅の過程で、本土側の「やさしい」人たちからの歓待を受け、同時に朝日新聞からは「色の黒さ」を何度も強調された記事を書かれる。その後の「ノスタルジックな語り」を予兆する内容であるが、壮年に達した現在の彼には、もはや祖国に対する素朴な憧れや愛着はなく、反戦平和運動に参加し、日本に対する強烈な批判を含む短歌を書いていた。このエピソードを冒頭と最後に設け、本文をあいだに挟むという構成は見事である。
『同化と他者化 戦後沖縄の本土就職者たち』
著者:岸政彦
発行:ナカニシヤ出版
発行年月:2013年2月20日
2017/02/28
「裸足で逃げる」とは、なんと沖縄の「現実」に刺さるタイトルだろう。あの亜熱帯の夜の、生暖かい、しかしひんやりとしたアスファルトを思わず踏みしめたときの素足の触覚が、混濁したいくつものエモーションを拓き、一条の微かな光線の可能性を喚起させる。コザのゲート通りをゲート側から捉えた夜景の表紙写真と…
2017/02/25
黒澤明の1949年の名作をリメイクする、しかも集団就職被差別からの怨恨をはらそうとする沖縄出身の青年たちに犯人を設定するという森崎東の狂気=リアリズムが炸裂する。 野良犬の比喩は早くも冒頭シーンで明確に現される。清掃工場での賃労働の帰り道、若者たちが炎天下をけだるそうに歩いている。大型ダンプが…
2008/03/17
昨日のハチドリワークショップは盛況のうちに終わった。JanJanに近々記事をアップする予定です。オイラの問題提起部分は時間が押し、後半部分をカットせざるを得なかった。以下に全原稿をアップします。ーーーーーーーーーーーーー【草稿】沖縄で改めてスローを考えるみなさんこんにちは。那覇…
2019年08月08日
『ユリイカ 総特集書店の未来 本を愛するすべての人に』

表題に関わる広範囲のアクターたちのインタビューと論考を網羅しているが、総じて期待していたほど集中して読むことができなかった。その中で、最後の内沼晋太郎「不便な本屋はあなたをハックしない」を興味深く読むことができた。
インターネットの情報が私企業に操られることに警鐘を鳴らすインターネット活動家のイーライ・パリサーは、インターネットが人のなかで起きていることを把握し、何をするか予想できるなら、人の気持ちを改ざんしたり、操作したり、代替することもできる、人間をハックすることができる、と述べた。
これに対し、憲法学者のキャス・サンスティーンは、街路や公園などの公共空間では、人は選ぶつもりのなかった見解や情報とたびたび出会うことで、個人が自らと異なる「他者」の見解にさらされ、集合的な「共有経験」をもつことができることを重要視した。
著者はいう。インターネット同様、情報を扱う書店という空間は、人々をハックする場所にもなりうるが、「自分以上に自分を知っている誰か」に知られることなく、「選ぶつもりのなかった見解や情報」と出会い、別の関心を持てたり、影響を受けることもできる、と。
とはいえ、本が売れないことの二項対立として安易なネット批判をしているわけではない。amazonへの一定の評価、取次の必要性も確認される。「大きな出版業界」と「小さな出版界隈」という区分けも、現状認識として押さえておきたいポイントである。
尚、下北沢の「本屋B&B」経営者でもある内田氏にはいくつかの著作があるが、『これからの本屋読本』はインターネットに無料で公開されている。遅ればせながら読んでみたい。
875
『ユリイカ 総特集書店の未来 本を愛するすべての人に』
6月臨時増刊号
発行:青土社
発行年月:2019年6月1日
2019/06/02
パブリック(公共)という言葉の意味はこういうことなのだ、と今更ながら知らされる。それはピープルと極めて親和的であるということである。日本では公共=お役所であり、ピープルからは哀しく遠い。 この場所では、本の貸し出し・蔵書はその役割のほんの一部であるということが映し出され、この映画に関心を…
2016/07/11
図書館の新刊コーナーで手にとり読んでみようと思ったのは、ずばりこのタイトルに関心があるからだった。内容は事例紹介のようだ。この手の本は平均的なものが多い。だから、欲しい情報が得られればそれでよしとしよう。まあ、そんな動機で借りることにした。一読、期待以上の内容であった。かなりいい本である。…
2014/12/01
レンタルビデオチェーン「TSUTAYA」が図書館を運営、しかも店内には「スターバックス」が出店という佐賀県「武雄市図書館」のニュースには、ふだんから図書館を利用するしないにかかわらず、関心を持たれた方も多いのではないか。以降、無料貸し出しの公立図書館に営利サービスが導入されることの是非について少なくない…
2019年08月07日
『火口のふたり』白石一文
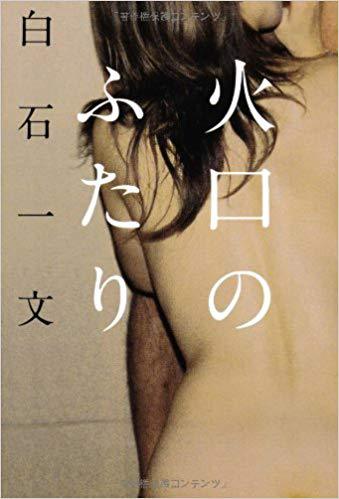
荒井晴彦が脚本と監督をするということで、その対策として読む。
主人公・賢治の一人称により従妹の直子との再会から、お互い相性のいい過去を思い出すように溺れる。賢治は妻子持ちだったが浮気が原因で離婚、自分で起こした会社も倒産寸前。直子は自衛隊員の年上の男との結婚式を目前に控えていた。東日本大震災後の閉塞感を富士山噴火前夜というカタストロフへと連結し、二人のまぐわいの〈いま・ここ〉の情感を隠喩させる。ダメ男からみた自由だが現実的な女という男目線の構図に真新しさはない。
という小説の通俗性を荒井晴彦がどう映画的文体として造るか。そこに注目している。
『火口のふたり』
著者:白石一文
発行:河出書房新社
発行年月:2012年11月20日
2019/06/08
「夜空はいつでも最高密度の青色だ」石井裕也 生きづらさを抱える美香(石橋静河)と慎二(池松壮亮)のボーイ・ミーツ・ガール。二人が見上げる渋谷の青い夜空は幽かな希望の徴かそうでないのか。日銭にありつく工事現場作業員、死に直面しても動じないよう感情を押し殺す看護師。二人が働く環境は青色と隔てられ…
2017/09/02
『しあわせのパン』の三島有紀子と”ザ・情念”荒井晴彦というミスマッチが正統的なドラマを成立させてしまった。それを可能にするのが、クセのある役者も子役もなんでも来いとばかりに受けまくり、同時に相変わらず浅野忠信がそこにいるとしかいいようがないごとく振舞う浅野忠信の可能性の中心である。 再婚同…
2019年08月04日
ライブ・エイドのボブ・ゲルドフとボノ

強引に夏休み気分になろうと、YouTubeでライブ・エイドの映像をみて1985年の夏を懐かしんでいる。プリテンダーズ、トム・ペティ、エルトン・ジョン、スティングとフィル・コリンズの競演、デヴィッド・ボウイの「ヒーローズ」など、当時テレビの生中継を通しで鑑賞した記憶を思い起こしながら。
その中で、昔を懐かしむ以上のある気づきがあった。それは、ボブ・ゲルドフ(ブームタウン・ラッツ)「I Don't Like Mondays」(邦題「哀愁のマンデイ」)のシリアスなパフォーマンスであった。いうまでもないことだが、ボブ・ゲルドフこそ、イギリスのミュージシャに呼びかけた第三世界の飢饉問題へのチャリティ・ムーブメント「Do They Know It's Christmas?」(1984年)から、アフリカ飢餓救済基金を行うためのライブ・エイドへと主導したキー・パーソンである。
「I Don't Like Mondays」は、1979年1月にカリフォルニア州サンディエゴで少女が自宅向こうの小学校で起こした無差別殺人事件を基に書かれた。その動機を尋ねられた彼女が「I Don't Like Mondays」と答えたとされる。「父親も母親も16歳のティーンエイジャーの気持ちがわからない。その理由がわからない。理由なんてあるのか?」と唄うゲルドフのパフォーマンスは、ロンドンのウェンブリー・スタジアムに集まった7万2千人といわれる観衆も同じだろうとほのめかすような孤高を感じさせる。そしてそれは、日本を含む現在の世界的な不寛容なモードをも刺す。
バッキング・ボーカルの「Tell me why ?」と「I Don't Like Mondays」のリフレインが世界飢饉の問題と結びつく現場で私たちが考えること、感じること。 終わらない日常(Mondays)の孤絶を抱える他者が、もしかしたら私であることを想像すること。
同じステージに立つU2は「Sunday Bloody Sunday」を演奏した。この曲は、1972年1月、北アイルランドのロンドンデリーで、デモ行進中の市民27名がイギリス陸軍に銃撃され、14名の死亡者、13名の負傷者を出した「血の日曜日事件」をモチーフにしている。マーチングバンド風アレンジのドラムと、それに合わせたボノのカクカクとしたパフォーマンスは、明らかに民族的なアイデンティティを表現している。
U2はその後、「ヨシュア・ツリー」(1986年)というロック史上に残る記念碑的アルバムをリリースする。ブライアン・イーノ、ダニエル・ラノワ両名のプロデュースにより、ロックにアンビエントのアレンジが加えられ成功した奇跡的な作品となった。おそらくライブ・エイド出演の時点で、「ヨシュア・ツリー」のダブリンでのレコーディングを行なっていたのではないか。その後U2はこの大ヒットアルバムを引っさげ、全米ツアーを成功させ、世界的な成功への道を歩む。それとともに、そのスタイルから民族的な彩りは薄れていく。
ボブ・ゲルドフとボノには、アイルランド出身でイギリスデビュー、アクティヴィストとして前面に出る姿勢という共通項がある。ボブ・ゲルドフはどちらかというと、アメリカのグローバリズムに反対の姿勢をイギリスで貫く傾向がみえる。一方のU2はアメリカ=音楽的ルーツであるブルースを探すことが自分(たち)探しであるという物語に説得力を持たせた。ボノはその成功を土台に、アクティビストとして数々の実践を重ねていった。
ボブ・ゲルドフは2005年、アフリカで貧困やエイズのために戦う献身が評価され、2006年のノーベル平和賞候補者にノミネートされた。その後、ボノによって設立されたアフリカを支援するための組織とも深い関わりを持つ。
私がU2の成功やボノのアクティヴィストとしての活躍を知っていて、ボブ・ゲルドフのその後の音楽や活動についてほとんど無知だっこと自体、アメリカの資本主義グローバリズムの下にあることの証左である。今年の来日ツアーで「ヨシュア・ツリー」を再現するU2にも目配せしつつ、その後のボブ・ゲルドフの音楽もじっくり聞いてみよう。
2018/12/01
この映画の要素を3つ挙げてみる。1、ロックバンドのサクセスストーリー、2、セクシャリティを含めたフレディ・マーキュリーのカリスマ的なキャラクター、3、ラストの「ライブ・エイド」までに至るライブ・パフォーマンスの圧倒的臨場感。さらに付け加えるならば、これは1〜3に関連するが、終演後会場を後にす…
2019年08月02日
『アンダー・ユア・ベッド』安里麻里
一人の女に対する一方的な欲望の表現として「変態」的な関わり方をする。そのイタすぎる挙動が映画の売りとなる。一人の女に対する偏執に限らず、ヒッチコック『サイコ』から数えて、その偏執狂ネタの亜流は枚挙にいとまがない。だから、この映画も量産されるそのうちの一つに過ぎないだろうと高を括りたくなる一方で、いや、だからこそ、そのありがちな素材を選びあるいは与えられ、観るものの心を揺さぶる映画的クオリティにまで「変態」させるのが映画ではないのかという呼びかけが、「安里麻里」という固有名から否応なく発せられる。その呼びかけに応答するためにレイトショーに出向いた。
アンダー・ユア・ベッド、つまりいつでも女のそばにいたいという欲望を抑えられず寝室のベッドの下に潜み、女の(性)生活を監視するアンモラルというモチーフは、早くもオープニングのシークエンスで惜しみなく現前する。ベッドの上でいきなり始まる夫と女の音。ベッドの軋み、女の喘ぎ。頭上のその振動に三井直人(高良健吾)は片手でそっと触れようとする。触れたかどうかわからないほど微妙に。その表情は、恍惚なのか哀切なのか煩悶なのか、それとも憤怒なのか。そう、この映画は他者からの安易な感情移入を拒否する高良健吾の多様な表情のドラマなのだ。
三井をそうさせた過去。少年時代から一貫して存在感が薄いゆえ、他人の記憶に残らない孤独な心象風景。たった一度だけ、大学の講義室で背後から囁くように「三井君」と声をかけてくれた佐々木千尋(西川可奈子)の忘れられぬ思い出。追憶は百パーセント純度の欲望となる。西川可奈子は、透明だが同時に粘つくような声音を相手が高良健吾のときにのみ発する。半無意識に扇情させ欲情させるその声音の力は、後半、DV夫から受ける凄まじい暴力シーンでの西川の身体表現以上に映画として大きい。そしてその呼びかけの声はラストシーンでの救い(の可能性)として決め台詞となる。

上映終了後のトークショーがまた面白かった。安里の映画美学校時代の恩師に当たる黒沢清との対談。まず、舞台に上がる際、客席袖を舞台に向かって走る安里(女タランティーノのファンサービスか!)、それにつられて小走りで続く黒沢。黒沢清が走っている?二度と見られない映画以上のパフォーマンス!
黒沢といえば幽霊。千尋の家を探り出し、家の前に佇む三井の前に、玄関から現れ、三井に気づかず目の前を通り過ぎていく千尋の、何かしら問題を抱えた仄暗さが示唆される演出について、「幽霊のようだともいえる」と黒沢。三井が千尋の家の前にオープンさせた観賞魚店のドアを開けて千尋が入ってくるカットの、背後から日照を浴び表情がおぼろげになっているところも幽霊のようだ、と。うむ、なるほど。
千尋が夫のDVから逃れようと乗り込む車と、三井の少年時代の回想シーンで父親から車内に置き去りにされる車がBMWであるという細かい指摘をし、何か意味があるのかと黒沢。「やっぱりBMWに乗っている人はヤバイ人が多い、ということで…」と真偽の定かでないボケで返す安里。
前半の三井のモノローグから、後半千尋のモノローグへ一転するところを評価する黒沢。我が意を得たりと安堵の笑みを見せる安里。
黒沢から送られた昔のメールが安里から紹介される。「アサトのホンは物語を飛躍させようと無茶をする。その無茶が過ぎると、観客は心の動揺をごまかそうと笑う。笑ってもいいと思わないで欲しい。今の君にとって、これは危険な誘惑だ。頼むからしないでくれ。観客の心を凍らせねばならない。笑う余裕なんか与えたら失敗だ」(安里麻里のツイッターから抜粋)。幽霊にとり憑かれた監督らしい忠言である。
ところで安里麻里といえば、その劇場長編デビュー作『独立少女紅蓮隊』(2004年)を、当時支配人をしていた沖縄のミニシアターで上映させてもらった。その時もトークショーを開き話を聞かせてもらったが、その変わらない印象から良き思い出が甦った。いつかまた必ず、彼女が監督する沖縄についての映画を観てみたい。そのときこそ何か関わってみたいという一方的な妄想を抱く。アンダー・ユア・ベッドで。
『アンダー・ユア・ベッド』
監督:安里麻里
出演:高良健吾/西川可奈子/安部賢一
劇場:テアトル新宿
2019年作品
2019/06/28
ウズベキスタンへのロケ、登場人物が撮影クルーという設定、役者たちが中央に配置しカメラに向かってポーズをとる宣伝写真がすでに映画の「出来高」とは別の何かを予言してしまっている。 それぞれの役者たちが「旅」先のようなロケ地で完璧な職業人と化して映っている。演技によって撮影クルーのリアルさが現…
2017/09/25
『岸辺の旅』で脳裏について離れない浅野忠信のパッと消えるラストについて、蓮實重彦は次のように指摘している。「生きていない人の影」の「出現と消滅」は黒沢作品の主要テーマであるが、それまでの作品と比べて、「きわめてぶっきらぼうに、いるものはいる、いないものはいないという描き方」だと。その「ぶっき…
2017/09/23
映画的な衝撃を受け笑ってしまうショットの数々。冒頭からして凄まじく笑える。『Seventh Code』のラストショットから始まるのか、まさか!?という驚き。 長澤まさみの総体がよい。松田龍平の淡々ぶりがよい。いつものように不意に上手からインする笹野高史はもはやお約束の境地か。 黒澤作品ではお馴染…
2017/09/22
けったいな映画だ。いや、映画はけったいだ。いやいや、黒沢清の映画はけったいだ。ゆえに、黒沢清はけったいだ、とはならない。たぶん。 どうして冒頭からいきなりロシアなのか。前田敦子の入り方があまりにも乱雑ではないか。それはそうと、前田敦子がガラガラひきずるキャリーバッグが重そうでうっとりして…
2016/07/08
元刑事で犯罪心理学者の高倉(西島秀俊)は妻康子(竹内結子)と一軒家の新居に引っ越ししてきた。挨拶回りで訪ねた隣家の西野(香川照之)に対する二人の印象は「感じが悪い」。しかし「感じの悪さ」を観る者に与えるのは西野の異様さだけではない。ロケーションで選ばれた両家の外観、過去に行方不明事件が起き、…
2019年07月26日
『追われゆく坑夫たち』上野英信
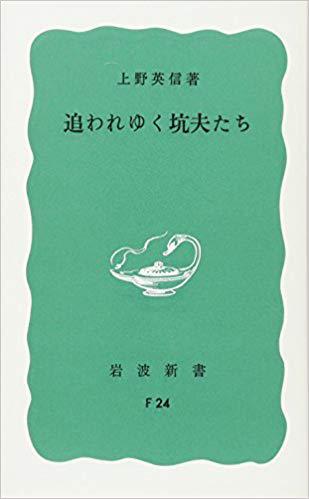
戦後筑豊の中小炭鉱に坑夫として自ら働き、その奴隷的な労働状況を記録する。それは「悲惨」だとか「この世の地獄」だとかいう修飾語では表現を尽くせない。これをまともに読める立場にいる者はたまさか余裕があってよかろうと、読みながら思ってしまった。というのは、自分の現在が物心共に危うい状況にあるので、そのリアルさをまともに受けとめてしまうから。
むろん、ここで描かれる非人間的な過酷さと今の私のそれが同レベルだなどというつもりはない。しかしながら、人間が働くことの社会的な意味を問うていくと、究極的にはここに行くつくだろうと、私には想像ができる。想像できるということは、すでにその可能性に身を置いているということにほかならない。この先もまた生き地獄のような労働環境だとわかっていながら、日銭を求め中小炭鉱を渡り歩く坑夫たちの、野たれ死ぬ以外の終わりのなさを、私は自らの労働することの(無)意味として避けられず錯視してしまう。
ところが、その例えなき重さに比して、本書はすいすいと読み進むことができる。それは「文体」のなせる技にあるのではないか。内容は澱みそのものだが、「文体」に澱みはない。だから新鮮さを失わない。自らその過酷さを体験しているはずの著者の独白はほとんどなく、架空の三人称として、それは記述される。
「中小炭鉱がこの悲惨さを生んだというよりも、特殊日本的な労働者・農民の悲惨さが中小炭鉱を生んだのであ」るとするならば(182ページ)、その地平は現在まで続いている。坑夫の時代はそれが直截的であるがゆえに社会の目から隠蔽されたが、現在は網の目のように「関節」的であるがゆえに、それをギックリ腰のように身体に打撃として受けて初めて気がつく。
『追われゆく坑夫たち』
著者:上野英信
発行:岩波新書
発行年月:1960年8月20日
タグ :上野英信