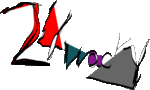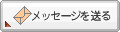› 「癒しの島」から「冷やしの島」へ › 2014年12月
› 「癒しの島」から「冷やしの島」へ › 2014年12月2014年12月02日
書評『治さなくてよい認知症』
認知症の母を持つ私にとって、いや、高齢になればすべての人が認知症になる可能性を考えれば、社会にとって必須の本である。それは、認知症(本書では、高齢のアルツハイマー型認知症の軽度から中等度を指す)に対するこれまでの理解が、まったくひどいものであり、いまだにそうである現状が本書を読むと痛切であるから、とりわけ私の浅い経験からも思い当たることが多々あり、衝撃的だからこそ必須なのである。
まず、認知症は治らない。だから治そうと努めなくてよい。治そうとする周りの「善意」が、本人にとってどれだけ暴力的であるかを著者は強調する。家族にしてみれば治ってほしいのは気持ちとしてうなずけるが、実際は治らないのである。それをあたかも治るかのように診察する医師、報じるメディアの罪は大きいと著者は警鐘を鳴らす。なによりも重要なのは、周囲が「治らなくてもよいと早期に認識すること」なのだと。
ではどうしたらよい?周囲は認知症の人に対し「慰め、助け、共にする」こと、これに尽きると著者はいう。本人にとっては、「家族ら介護者との交流、周囲の人たちと共にする日々の食事や『用事』、慕われ頼られる感じを持てる日常など、社会性と活動性と役割を持った生活ができているか」が大切である。すなわち、自己肯定感の回復である。
認知症診療は「生活を診る」ことにほかならないと著者は喝破する。これは現実の診療に対するアンチテーゼである。実際の診療は、症状や認知機能にばかり注目しがちだという。抗認知症薬を処方し、改定長谷川式簡易知能評価尺度(HDS-R)でその程度を判定する。それしかしない。私が毎月母の診療に付き添って目にしてきた光景と重なる。そこで抜け落ちているのは「生活」であると著者は批判する。
認知症に対する無理解で最たるものは、不機嫌、イライラ、抑うつ、暴言、妄想、暴力、徘徊といった症状が、認知症という脳気質性の疾患、脳の神経機能障害によって生じるものであるという誤解である。これら反応性の症状は、急激な環境変化に直面したとき、失われた能力への過度な期待がかけられたとき、拒絶や無視などにさらされたときに生じることが多い、つまり、精神的反応によるものであるという。これらの症状が生まれたとき、周囲はそれを認知症の症状だと思い込み、当人を非難したり、抑え込んだり、薬を処方したりする。そうではなく、そういった周囲の無理解な態度こそ、その原因なのである。だから「生活を診る」必要があるのだ!
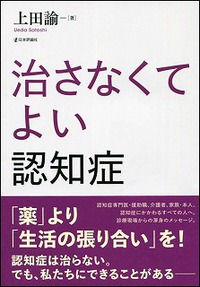
『治さなくてよい認知症』
著者:上田諭
発行:日本評論社
発行年月:2014年4月30日
まず、認知症は治らない。だから治そうと努めなくてよい。治そうとする周りの「善意」が、本人にとってどれだけ暴力的であるかを著者は強調する。家族にしてみれば治ってほしいのは気持ちとしてうなずけるが、実際は治らないのである。それをあたかも治るかのように診察する医師、報じるメディアの罪は大きいと著者は警鐘を鳴らす。なによりも重要なのは、周囲が「治らなくてもよいと早期に認識すること」なのだと。
ではどうしたらよい?周囲は認知症の人に対し「慰め、助け、共にする」こと、これに尽きると著者はいう。本人にとっては、「家族ら介護者との交流、周囲の人たちと共にする日々の食事や『用事』、慕われ頼られる感じを持てる日常など、社会性と活動性と役割を持った生活ができているか」が大切である。すなわち、自己肯定感の回復である。
認知症診療は「生活を診る」ことにほかならないと著者は喝破する。これは現実の診療に対するアンチテーゼである。実際の診療は、症状や認知機能にばかり注目しがちだという。抗認知症薬を処方し、改定長谷川式簡易知能評価尺度(HDS-R)でその程度を判定する。それしかしない。私が毎月母の診療に付き添って目にしてきた光景と重なる。そこで抜け落ちているのは「生活」であると著者は批判する。
認知症に対する無理解で最たるものは、不機嫌、イライラ、抑うつ、暴言、妄想、暴力、徘徊といった症状が、認知症という脳気質性の疾患、脳の神経機能障害によって生じるものであるという誤解である。これら反応性の症状は、急激な環境変化に直面したとき、失われた能力への過度な期待がかけられたとき、拒絶や無視などにさらされたときに生じることが多い、つまり、精神的反応によるものであるという。これらの症状が生まれたとき、周囲はそれを認知症の症状だと思い込み、当人を非難したり、抑え込んだり、薬を処方したりする。そうではなく、そういった周囲の無理解な態度こそ、その原因なのである。だから「生活を診る」必要があるのだ!
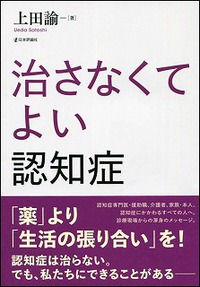
『治さなくてよい認知症』
著者:上田諭
発行:日本評論社
発行年月:2014年4月30日
2014年12月01日
書評『つながる図書館 ──コミュニティの核をめざす試み』
レンタルビデオチェーン「TSUTAYA」が図書館を運営、しかも店内には「スターバックス」が出店という佐賀県「武雄市図書館」のニュースには、ふだんから図書館を利用するしないにかかわらず、関心を持たれた方も多いのではないか。以降、無料貸し出しの公立図書館に営利サービスが導入されることの是非について少なくない議論が起こったことも記憶に新しい。本書は武雄市図書館にかぎらず、いま、日本中の図書館に発生している大きな変化について、最新の取材を通し報告している。
その変化の背景には「官から民へ」の小泉構造改革という政策がある。自治体予算削減の流れとしての地方自治法改正(2003年)の下、公共サービスに民間サービスを導入する指定管理者制度が設けられた。以来、運営コスト削減をねらい、営利企業やNPO法人に運営委託を代行することが可能となった。それによって、実際に民間委託を導入した公立図書館が変化したことはもちろん、導入していない公立図書館にとっても、時代の流れに逆らえず変化しないわけにはいかないようだ。
その変化を表すキーワードが「課題解決型図書館」である。つまり、ユーザーやその地域が抱える何らかの課題を解決するためのレファランス機能という専門性を持つこと。それが「無料貸本屋」批判を解消するためにも必要だったのだ。だがこれにも背景がある。地方分権一括法(1999年)により「公立図書館館長に司書資格はいらない」とされたことで、逆に司書の重要性を図書館の基幹部分として改めて位置づけ直すという反省が、公立図書館に携わる人たちのあいだに生まれたのだという。新しい公共図書館の種を蒔いた糸賀雅児慶応義塾大学教授が語る次の言葉はその事情をよく現している。「地域のことをよく知り、図書館が所蔵する本や雑誌、資料について熟知している司書なら、地域や住民たちが抱える課題を解決するためのコンテンツを発信できる。」
〈第1章 変わるあなたの街の図書館〉で紹介される、東京都武蔵野市の「武蔵野プレイス」はその変化のよい面を印象づけるには最適な場所である。中央線武蔵境駅から徒歩1分の「市民の居場所」に入ると、静かな音楽と開放感のあるエントランスホールが迎え、オープンスペースのカフェでは雑誌が閲覧可能。さらに他のフロアには、「図書館機能」だけなく、「生涯学習支援機能」「青少年活動支援機能」「市民活動支援機能」の4つの機能が備わっている。興味深いのは、それらがよくある複合施設とは異なる点である。たとえば、図書の展示を通して生涯学習支援につなげたり、市民活動グループが青少年活動のためにイベントを開催するなど、それぞれの機能が有機的に関わるような「複合機能施設」としてあり、建築もそれを可能にさせる工夫を凝らしたデザインになっているという。
〈第5章 「武雄市図書館」と伊万里市図書館」が選んだ道〉は最も読み応えのある章である。民営化の極北を行くような「武雄市図書館」と、あえて指定管理者制度を採らなかった「伊万里市図書館」という、同じ佐賀県内の対照的な2つの「視察が絶えない」図書館を論じる著者の姿勢は「中立」である。両者の魅力を伝えることで、さらにお互いの個性が際立つ。「武雄市図書館」に「民営化」を導入した樋渡市長の弁、「ここには何もないという地元民の自虐史観を払拭し、誇りを取り戻してもらいたい」という「思想」には是非があるだろう。一方で、市民にとって何が必要かを大切にする「伊万里市図書館」には、将棋や碁をさすリタイア男性たちの憩いの場があるという。民営化に従えば非効率とみなされ淘汰されそうなスペースも、古瀬館長によれば、必要な場だという。そして、大学受験に何回も失敗した若者がいつしか老人たちと友だちになり、いっしょに碁を指しながら人生相談に発展するといった心温まるエピソードが語られる。
尚、指定管理者制度の是非については二箇所で直接論じられている。〈第二章 新しい図書館の作り方〉では、指定管理者制度について以前は懐疑的だったが導入後考えが変わったという、千代田図書館リニューアルに携わった国立国会図書館電子情報部司書監の柳与志夫さんの評価として、メリットとデメリットがあると証言される。また第五章では、指定管理者制度以前にあった業務委託が、そもそも図書館側からの要望によるものだったとする意外なエピソードが紹介される。さらに図書館業務を含めた民間委託化された公共事業の俯瞰的な財政的検証があれば良かったのだが。
〈第6章 つながる公共図書館〉で紹介される新しい試みは、指定管理者制度の流れとは直接関連しないが、「公共」の意味を再考させる。千葉県船橋市の「船橋まるごと図書館」、東京都世田谷区下北沢のコワーキングスペースから生まれた「リブライズ」は、それぞれSNS時代の新しいコミュニティ志向がうかがえ刺激的である。リアルな小さなコミュニティがネットも活用しながら顕在化することはドキドキする。しかし、その媒介(メディア)は本という誰にもなじみのモノである。「船橋まるごと図書館」を運営するNPO法人「情報ステーション」の岡直樹代表理事の言葉はシンプルで新しい。「小さい子から高齢の方まで世代を選ばず全ての人が集まれる場所は、図書館以外にありません。」
 『つながる図書館 ──コミュニティの核をめざす試み』
『つながる図書館 ──コミュニティの核をめざす試み』
著者:猪谷千香
発行:ちくま新書
発行年月:2014年1月10日
関連サイト:
武蔵野プレイス
武雄市図書館
伊万里市図書館
船橋まるごと図書館プロジェクト
リブライズ
その変化の背景には「官から民へ」の小泉構造改革という政策がある。自治体予算削減の流れとしての地方自治法改正(2003年)の下、公共サービスに民間サービスを導入する指定管理者制度が設けられた。以来、運営コスト削減をねらい、営利企業やNPO法人に運営委託を代行することが可能となった。それによって、実際に民間委託を導入した公立図書館が変化したことはもちろん、導入していない公立図書館にとっても、時代の流れに逆らえず変化しないわけにはいかないようだ。
その変化を表すキーワードが「課題解決型図書館」である。つまり、ユーザーやその地域が抱える何らかの課題を解決するためのレファランス機能という専門性を持つこと。それが「無料貸本屋」批判を解消するためにも必要だったのだ。だがこれにも背景がある。地方分権一括法(1999年)により「公立図書館館長に司書資格はいらない」とされたことで、逆に司書の重要性を図書館の基幹部分として改めて位置づけ直すという反省が、公立図書館に携わる人たちのあいだに生まれたのだという。新しい公共図書館の種を蒔いた糸賀雅児慶応義塾大学教授が語る次の言葉はその事情をよく現している。「地域のことをよく知り、図書館が所蔵する本や雑誌、資料について熟知している司書なら、地域や住民たちが抱える課題を解決するためのコンテンツを発信できる。」
〈第1章 変わるあなたの街の図書館〉で紹介される、東京都武蔵野市の「武蔵野プレイス」はその変化のよい面を印象づけるには最適な場所である。中央線武蔵境駅から徒歩1分の「市民の居場所」に入ると、静かな音楽と開放感のあるエントランスホールが迎え、オープンスペースのカフェでは雑誌が閲覧可能。さらに他のフロアには、「図書館機能」だけなく、「生涯学習支援機能」「青少年活動支援機能」「市民活動支援機能」の4つの機能が備わっている。興味深いのは、それらがよくある複合施設とは異なる点である。たとえば、図書の展示を通して生涯学習支援につなげたり、市民活動グループが青少年活動のためにイベントを開催するなど、それぞれの機能が有機的に関わるような「複合機能施設」としてあり、建築もそれを可能にさせる工夫を凝らしたデザインになっているという。
〈第5章 「武雄市図書館」と伊万里市図書館」が選んだ道〉は最も読み応えのある章である。民営化の極北を行くような「武雄市図書館」と、あえて指定管理者制度を採らなかった「伊万里市図書館」という、同じ佐賀県内の対照的な2つの「視察が絶えない」図書館を論じる著者の姿勢は「中立」である。両者の魅力を伝えることで、さらにお互いの個性が際立つ。「武雄市図書館」に「民営化」を導入した樋渡市長の弁、「ここには何もないという地元民の自虐史観を払拭し、誇りを取り戻してもらいたい」という「思想」には是非があるだろう。一方で、市民にとって何が必要かを大切にする「伊万里市図書館」には、将棋や碁をさすリタイア男性たちの憩いの場があるという。民営化に従えば非効率とみなされ淘汰されそうなスペースも、古瀬館長によれば、必要な場だという。そして、大学受験に何回も失敗した若者がいつしか老人たちと友だちになり、いっしょに碁を指しながら人生相談に発展するといった心温まるエピソードが語られる。
尚、指定管理者制度の是非については二箇所で直接論じられている。〈第二章 新しい図書館の作り方〉では、指定管理者制度について以前は懐疑的だったが導入後考えが変わったという、千代田図書館リニューアルに携わった国立国会図書館電子情報部司書監の柳与志夫さんの評価として、メリットとデメリットがあると証言される。また第五章では、指定管理者制度以前にあった業務委託が、そもそも図書館側からの要望によるものだったとする意外なエピソードが紹介される。さらに図書館業務を含めた民間委託化された公共事業の俯瞰的な財政的検証があれば良かったのだが。
〈第6章 つながる公共図書館〉で紹介される新しい試みは、指定管理者制度の流れとは直接関連しないが、「公共」の意味を再考させる。千葉県船橋市の「船橋まるごと図書館」、東京都世田谷区下北沢のコワーキングスペースから生まれた「リブライズ」は、それぞれSNS時代の新しいコミュニティ志向がうかがえ刺激的である。リアルな小さなコミュニティがネットも活用しながら顕在化することはドキドキする。しかし、その媒介(メディア)は本という誰にもなじみのモノである。「船橋まるごと図書館」を運営するNPO法人「情報ステーション」の岡直樹代表理事の言葉はシンプルで新しい。「小さい子から高齢の方まで世代を選ばず全ての人が集まれる場所は、図書館以外にありません。」
 『つながる図書館 ──コミュニティの核をめざす試み』
『つながる図書館 ──コミュニティの核をめざす試み』著者:猪谷千香
発行:ちくま新書
発行年月:2014年1月10日
関連サイト:
武蔵野プレイス
武雄市図書館
伊万里市図書館
船橋まるごと図書館プロジェクト
リブライズ