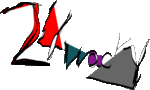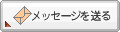› 「癒しの島」から「冷やしの島」へ › 2016年07月
› 「癒しの島」から「冷やしの島」へ › 2016年07月2016年07月31日
『その夜は忘れない』

東京の雑誌記者加宮(田宮二郎)は「原爆記念」取材で、17年たった今も残る傷痕を追い求め、広島に入る。ところがいく先々の被爆者はみなあっけらかんとし、加宮を拍子抜けさせる。地元のテレビ局ディレクターで親友の菊田(川崎敬三)からも、だからいっただろうと軽口を叩かれる。菊田に誘われ入ったバーのママ秋子(若尾文子)とお互い惹かれあうが、秋子こそその肉体に傷痕を抱える被爆者であった。
加宮が広島に入っていく導入から、團伊玖磨の過剰な音楽とともに「魔界」入りしていくあたりが見事だ。ジャーナリストとしての関心をふるいにかけられる加宮の職業意識と、適度に軽薄なキャラクターが溶解していく様がアップテンポで描かれていく。真夏の広島の暑さに急き立てられるように取材先を求めて歩く加宮の足元のカットバック。一転ただひたすら美しい秋子とのメロドラマという展開では、モノクロームの接写により、田宮二郎の肉体にひかる汗の陰影と、暗い背景を背に若尾文子の目元に当てられた照明のはかない明るさが生と性を喚起させる。吉村公三郎はうまい。
しかしながら映画のテーマは「反戦平和」というより、それを自明のものとして語ってしまう者たちの当事者性を問うことにあるだろう。傷痕は語り得ないということを伝えるために、秋子は川の底から石を拾い、加宮にそれを握ってみろという。加宮の掌のなかで脆くも粉々になることで戦さの記憶を喚起させる石ころ。それは自らの当事者性の欠如を加宮が知らしむ瞬間でもある。夜空と川の暗黒と対照的な粉々な石粒の白というドラマはその残酷さを明瞭に映し出す。
『その夜は忘れない』
監督:吉村公三郎
出演:若尾文子/田宮二郎/川崎敬三/角梨枝子/江波杏子/中村伸郎
1962年作品
劇場:ユーロスペース
特集上映「原爆と銀幕 止まった時計と動き始めた映画表現」
2016年07月24日
『東京戦後地図 ヤミ市跡を歩く』

先日友人の誘いで谷中にある沖縄料理屋「あさと」を訪れた際、店舗の入る木造アーケードに関心が向いた。それは地元にもかつてあった「マーケット」の形状をいかにも思い起こさせるようであったから。初音小路と名づけられたその飲屋街は、夜になれば各々の店の灯で明るくなるものの、先に昼間訪れたときには薄暗い路地といった塩梅で、初めて足を踏み入れるにはちと勇気がいる気を漂わせていた。本書は東京の街でふと見かけるそんなマーケットやレトロ感溢れる飲屋街が、戦後ヤミ市の名残であることを貴重な写真や図を紹介しながら教えてくれる。
終戦後、人々は「ヤミ」の売買を始める。駅前の建物疎開地や、米軍の焼夷弾で生じた焼け跡などによって広場となった場所で、生き延びるためのエネルギーが自然発生的にその空間を生じさせた。最初は青空市場だったものが、伝統的露天商(テキヤ)の管理の下、バラック様の仮設店舗に発展する。駅前通りを埋め尽くしたアナーキーな状態に業を煮やした警視庁は、ヤミの横行を一部黙認しつつ露天商組織と結託し秩序維持を図り店舗化する。流通システムの合理化も伴った連鎖式店舗の集合体、すなわちマーケットの誕生である。
谷中のページでは、まさに初音小路が取り上げられている。現在の谷中銀座商店街入り口に日本国憲法制定後初の総選挙で日本社会党から首相となった片山哲の私邸があり、その周辺で営業していた露店が撤去令を受け、現在の場所へ移転したという。このように行政主導で移転させることを露店「換地」という。23の売り場が公設市場のように生鮮食料品、日用品全般の物品販売業、甘味喫茶店、飲食店から成り、共同仕入れ、共同宣伝方式をとり、マイク、折込広告で呼びかけていたという読売新聞の記事が引用される。活況だった開業時の様子と、ほとんどが飲み屋となっている現在とのコントラストを私に促す(入り口左にあるせんべいやが1950年の写真に写っているという!)。
当然ながら、我が地元・蒲田が紹介されているのはうれしい。JR蒲田駅西口にできたマーケットの場所を地図で確認すると、現在のサンライズ蒲田、サンロード蒲田、そしてバーボンロードといった商店街であることがわかる。マーケットが整理された結果として、あの明るいアーケードと迷宮と化した裏手の混沌のミックスがある(1959年の火災保険特殊地図によれば、バーボンストリートのあたりが「のみや」「のみや」「のみや」・・・と小さな飲み屋しかないところがいかにもで笑ってしまう)。
他にも「山手線と西武新宿線にはさまれた一画に残るヤミ市時代の名残」高田馬場、「若者たちが集う人気スポット、三角地帯の暗黒時代」三軒茶屋、「ヤミ市マーケット時代の区画を残す貴重な飲食店街」大井町などなど、いずれも興味深い。欲を言えば、当時を知る地元の人々の証言といった物語性も加われば、なお読み応えがあっただろう。いずれにしても、庶民の営みから戦後と今を見据える知的作業は愉しい。
『東京戦後地図 ヤミ市跡を歩く』
著者:藤木TDC
発行所:実業之日本社
発行:2016年6月21日
2016年07月11日
『ローカルメディアのつくりかた 人と地域をつなぐ編集・デザイン・流通』

図書館の新刊コーナーで手にとり読んでみようと思ったのは、ずばりこのタイトルに関心があるからだった。内容は事例紹介のようだ。この手の本は平均的なものが多い。だから、欲しい情報が得られればそれでよしとしよう。まあ、そんな動機で借りることにした。一読、期待以上の内容であった。かなりいい本である。
なにより紹介される全国の紙媒体のローカルメディアのそれぞれがユニークで面白い。編集者であり、展覧会・イベントのディレクターでもある著者のど真ん中の得意分野だからということをおいても、それぞれのローカルメディアが詳しく魅力的に書かれている。つまり、まったくハズレがないように読める。
百花繚乱といってよいローカルメディアであるが、共通項もある。その多くが、物語性を魅力の元としている。『東北食べる通信』(岩手県花巻市)は生産者と消費者の関係を深めるために、食べ物付き情報誌という方法をとる。つまり、食材が雑誌についてくる。食べ物を注文するとパンフレットが同封されてくるパターンと似ているが、逆である。飽食の時代に皆食べることには関心が高いが、その生産者までには思いが至らない。生産現場の危機的状況を消費者に知らしめる必要がある。ここまでは産直運動の理念と似ている。しかし、『東北食べる通信』は、食の生産に携わっている人の生き様が商品で、食べ物は付録であるという発想の転換がなされている。生産者や食材にまつわるストーリーが商品なのである。それによって、生産者と消費者の濃いネットワークが発展していく。
もう一つの共通項は、ローカルメディアをつくろうと思った最初の動機や計画が、取材で実際に地域の人たちと関わるようになるにつれ、様々な気づきを得、教えられ、協力があり、その過程で真のミッションが生まれ、変容していくという点が見逃せない。むしろ、そのプロセスこそが重要であり、一回やったらやめられなくなるほどワクワクするようだ。たんなる事例紹介で終わらない本書の魅力とは、そのプロセスを丁寧に追体験するかのように書かれているところにある。言葉を換えて、著者はあとがきでこう記す。「現在、各地で生まれつつあるローカルメディアは、内外の人にメッセージを伝える目的ではなく、地域の人と人がつながるための手段になった瞬間に、その本領を発揮していた」。
情報=コンテンツ=最終商品ではない。つながるための手段が大事。つまり、貨幣経済における商品交換はなされているが、それよりもメインなのはつながるという「交換」である。人々は無意識のうちに資本制経済をボイコットしているのかもしれない。そう思えてしまうほど、つながることの欲は深い。
『ローカルメディアのつくりかた 人と地域をつなぐ編集・デザイン・流通』
著者:景山裕樹
発行所:学芸出版社
発行:2016年6月1日
2016年07月09日
『是枝裕和X樋口景一 公園対談 クリエイティブな仕事はどこにある?』

何を隠そう私はクリエイターという言葉の響きがきらいだ。過去何度かクリエイターとして名指しされたことがあるが、そこはかとなく不愉快であった。曖昧なのに何がしかの権威を持つような含みが嫌なのか。だから、本書冒頭に紹介される「クリエイティブな仕事とクリエイティブでない仕事があるのではない。その仕事をクリエイティブにこなす人とクリエイティブにこなさない人間がいるだけだ」という言葉は一応合点がいく。クリエイティブというのは職種ではなく、仕事をする態度であるという意味として。一応というのは、世の中にはどう考えてもクリエイティブでない仕事はあるよね、そういう仕事をやったことがない人がいえる言葉でしょ、と凡庸なツッコミを入れたくもなるからだ。
クリエイティブ以外にも、本書ではクリエイター談義に欠かせないタームについての議論が展開され面白い。「自分」(自己表現)、「才能」などなど。
是枝裕和は、ディレクターが吸いたいタバコを吸いたいタイミングで用意することがアシスタントディレクターの仕事として要求されるが、それがクリエイティブなのかと疑問を持つ。同時に、そこで「自分には向かない」と思いがちだがちょっと違う見方をしてみてはどうかととどまることを勧める。
僕は、映像はつくっているけれど、自分を作家だとは思っていないんです。自分のなかに溢れんばかりのイマジネーションがあるわけではない。何かと関わったときに、「あっ」と発見するとか、知らなかったことに出会ってそれを形にしていく媒介だと思っている。テレビのディレクターとはそういうものだと思っているんです。そのために視野を広くするとか、人とコミュニケーションできる言葉をもつとか、そのへんはスキルとしていくらでも鍛えられます。
僕は全くそうしたスキルのない人間だったから、それが仕事によって鍛えられたんだけれど、そのときにはそれほど「自分」は必要ないというか、あるとむしろ邪魔になる。だから、「自分なんてたいしたものじゃない」と気づくことができれば、「自分」が大事になって仕事を辞める人はもうちょっと減るんじゃないかな。(37ページ)
「自分なんてたいしたものじゃない」といえば、「ひらめき」(才能)というのもたいしたものではない。ひとり部屋のなかで悩みに悩んで思いつく「ひらめき」によって、そのとき自分は天才ではないかとうぬぼれてしまうが、人間が思いつくものというのは、すでに誰かによって思いつかれている。それよりも、そんな「ひらめき」をたくさん持ち寄ってたたき台とし、他人とコミュニケーションすることによってできてくるなにかの方がはるかに大事なのだ。
樋口景一は「才能ってなんだろう」という議論のなかで、カンヌ国際広告祭審査委員長のコロンビア人の審査基準が「勇敢さ」であったというエピソードを紹介している。こんなことを言うと問題が起きるのではという常識や分別を押しのけてあえて言い切る勇敢さを。
「勇敢さと臆病さは同居していて、勇敢にものを伝えるときには、自分が本当にこれを言っていいんだろうかというドキドキした臆病さと葛藤しなくてはいけない。葛藤しないでいきなり出て行こうとするのはただ無謀でしかない。無謀と勇敢は違っていて、いろいろ怖がって、自分の中で試行錯誤しながらそれでもやることに意味がある。外に出て行く姿勢が自分の勇敢さであって、それが審査基準ではないか」(84ページ)
これは精神論として語られるべきではない。その勇敢さが作品に現れるというようにとらえるべきだろう。そこに人びとはクリエイティブを感じ、心を動かされるのだ。
二人の対談を読み進めていくと、どうやら答えは結果ではなくプロセスにありそうだ。ドキドキした臆病さと葛藤しつつ前に出るというプロセスが。
作品は社会の役に立つのかという問いに対し、社会を変えるという前に、その取材対象と出会って自分が変わることが先であると是枝は答え、こう続ける。「撮ることによって答えが見つかったり、逆に撮ることによって何かがわからなくなったり、そういう自己の揺らぎや自己変革みたいなものが、作品にとって大事なんだ。結果じゃないんだけど」
この議論をアクティヴィズムとエンターテイメントの違いと言い換えてみる。むろんアクティヴィズムにも、その過程で自己の揺らぎや自己変革を伴う場合があるだろう。社会批評性のあるエンターテイメントもあり得る。問題なのは「その仕事をクリエイティブにこなす人とクリエイティブにこなさない人間がいるだけだ」と、まとめてみたくなる。
いや、待てよ。私は両者の境界をあえて曖昧にしたいのだろうか。それとも、境界を越境する、その「態度の変更」に可能性をかけているのか。わからなくなってきた。
『是枝裕和X樋口景一 公園対談 クリエイティブな仕事はどこにある?』
著者:是枝裕和 樋口景一
発行所:廣済堂出版
発行:2016年6月20日
タグ :是枝裕和
2016年07月08日
『クリーピー 偽りの隣人』

元刑事で犯罪心理学者の高倉(西島秀俊)は妻康子(竹内結子)と一軒家の新居に引っ越ししてきた。挨拶回りで訪ねた隣家の西野(香川照之)に対する二人の印象は「感じが悪い」。しかし「感じの悪さ」を観る者に与えるのは西野の異様さだけではない。ロケーションで選ばれた両家の外観、過去に行方不明事件が起き、実はこの引っ越し先で起きる出来事と関係のある日野の空き家の外観などが、採光を落とした撮影によって陰鬱さを増幅させる。高倉の新居内で開け放たれた窓からそよぐ風によって動くカーテンも、なぜか開放感とは程遠い微妙な不気味さを与える。映画が前進する過程で増幅されていくこれらの総体がクリーピー(気味の悪い)という主題であろう黒沢清にとっては、映画を撮ることと観ることの共犯関係がクリーピーであることを露見させているようだ。
大学の講義室で学生を前に高倉が犯罪心理学を語るシーンがある。警察にも学者にも解釈不能なサイコパスが存在すると解説する高倉は、犯罪を取り締まる刑事であるにしてはあまりにも犯罪心理に興味を持ちすぎる、それを面白いと感じてしまう性向を隠さない。であるがゆえに、それと対をなすように不気味な挙動を繰り返す西野を、観る者は初めからサイコパスではないかと推測するだろう。高倉と西野はドラマ構成上持ちつ持たれつの関係にある。
確信犯的な二人よりも、見るからに不気味な西島の支配下にやすやすと落ちていく康子や西野の娘を演じさせられる澪(藤野涼子)が実はクリーピーなのだ。どうして西野の言いなりになるのか、西野の用意周到な手口も映画はその過程を描かない。薬を打たれるという振る舞いは説得力がなくとってつけたようだ。映画のクライマックスで、犯罪心理に没頭し自分を顧みない高倉に対し康子が不満を持っていたこと、高倉の転職と高倉家の引っ越しがそのわだかまりを払拭するきっかけとして期待されていたことが康子によって吐露される。それに初めて気づいたような高倉は康子に謝罪し、やり直しを求める。エンターテイメントが何度となく再現してきた安っぽいメロドラマを西島と竹内が演じさせられている、という見方すら可能だ。
近所付き合いのない隣人がもし異常者だったら?というエンタメ風切り口からこの映画を観た者は、映画の完成度の高さに満足しつついささか混乱するに違いない。それこそが、エンターテイメントの文法を壊し、再生させる作家のたくらみに乗っけられているのだが、それもクリーピーだろうか。
『クリーピー 偽りの隣人』
監督:黒沢清
出演:西島秀俊/竹内結子/香川照之/川口春奈/東出昌大
公開:2016年6月
劇場:T・ジョイPRINCE品川
2016年07月07日
『デジタル・ジャーナリズムは稼げるか メディアの未来戦略』

著者は簡潔にいう。インターネットは「マス」という概念そのものを殺した。かつてメディアは大勢の個人をマスとして一括りにし、そこに一方的に情報を送ればよかった。しかし、個別にコミュニケーションをとることがビジネスモデルとなっている今や、コンテンツはもはや最終製品ではなく、コミュニティとそのメンバーに情報を伝えるためのツールとしてある。彼女ら/彼らが求めている情報を的確に提供できているか、すなわち、「ジャーナリズムの最も重要な価値とは、利用者の目標の達成に役立つということだ」と(「第1章 マスは存在しない」33ページ)。
ジャーナリズムがコンテンツビジネスでないとしたら何だ?ジャーナリズムはサービス業である。ニュースを作って流して終わり、ではなく、その結果が重要なのだ(第2章 コンテンツ対サービス)。ここでは、紙からデジタルへの移行を振り返りつつ、あまりに重厚膨大になり過ぎたがゆえに、固定観念にとらわれ現実認識を妨げているジャーナリズムへの率直な批判がある。その裏返しには、コンテンツの価値を大転換させたグーグル的な世界を評価する著者の姿勢がみえる。
利用者の目標の達成に役立つとは具体的に何を指すのか。著者はガーディアンの有名な編集長、アラン・ラスブリジャーの次の考えを踏襲する。ジャーナリズムには「ファスト・ジャーナリズム」と「スロー・ジャーナリズム」がある。前者は、今、何が起きているのか絶えず最新の情報を流す従来の報道機関を指す。それに対し後者には色々なかたちがありえる。たとえば、大学の調査・研究のようにシンクタンクとしての役割が。あるいは教育という役割がある。これはジャーナリストが上から目線で一方的に情報を流すことではなく、個々が自らの欲求、要求に応じて情報を手に入れ、能力を身につけることができるようになることを指す(第6章 ジャーナリストの役割)。
問題はこれで食えるのかどうかである。ジャーナリズムはこの点分が悪い。そもそも価値ある情報は高く売ることができないという矛盾がある。情報は短時間のうちに価値が劣化してしまうからだ。著者はここでエンターテイメントとの比較論を展開する。エンターテイメントは、時間が経ってもその価値は減らない。また、情報に比べ著作権を保護してもらいやすいと。いうまでもないが、エンターテイメントは「食える」。
ジャーナリズムもエンターテイメントも物語を使うが、前者は情報を伝えるための手段として使うのに対し、後者は人を楽しませるためにそうする。見方を変えれば、エンターテイメントにも高い情報価値を持ち、啓発的になることがあるし、ジャーナリズムであっても人を惹きつけ、楽しめるものになることはある。本書ではたとえばこんなビジネスが紹介されている。「ストーリーツアー」は物語を現場で直接体験させるサービスである。「ナラティブリー」はニューヨークについての魅力的な物語をメディア・ミックスで提供する。これらは人々の関心を集めればビジネスになることを実践している(第23章 情報の価格設定のパラドックス)。
ところで、私は沖縄オルタナティブメディア(OAM)3年目のNPO法人化に際し、仲間たちと次のようなミッションをつくった。《OAMは、スローメディアとして人と地域の現場からつながりをつくり、市民参加型の映像配信・記録などを通して、沖縄から世界を結いなおします》。その実践の一つの試みとして、「あすの那覇市を考える2013市議選挙プロジェクト」を立ち上げた。それまで、公民館解体、小学校統廃合問題を市民メディアとして追いかける過程で、反対運動を継続してきたが結局行政の施策が強行されてしまった久茂地地域の市民たちの気づき、「どうして行政は自分たちの声を聞かないのだろう?」「市民はどうしてこれほど無力なのか?」「そもそも政治とは?」といった疑問から、選挙に対し個々の政治の力を培うという目標を達成するために、市民たちといっしょにつくりあげていくプロジェクトであった。
私はジャーナリズムとアカデミズムとアクティヴィズムをも包含するエンターテイメントという新たな試みを内に抱えている。本書はそのアイデアとパラレルでもある。
『デジタル・ジャーナリズムは稼げるか メディアの未来戦略』
著者:ジェフ・ジャービス
訳者:夏目 大
発行所:東洋経済新聞社
発行日:2016年6月9日