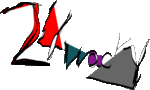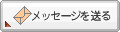› 「癒しの島」から「冷やしの島」へ › 2015年01月
› 「癒しの島」から「冷やしの島」へ › 2015年01月2015年01月17日
『ジミーとジョルジュ 心の欠片を探して』
原因不明の激しい頭痛を訴えるネイティブアメリカンのジミー(ベニチオ・デル・トロ)は、かつて第二次大戦に派兵されていたときの負傷が原因ではないかと疑う。精神分析医であり文化人類学者でもあるジョルジュ(マチュー・アマルリック)はジミーとの対話=セッションを繰り返しながら、むしろ戦争体験前のジミーの過去について質問を繰り返す。
ネイティブアメリカンの歴史と文化人類学的関心。たった一つのセリフで語られるジミーの沖縄戦派兵の経験。ジョルジュ・ドュブルーの背景にうかがえるフロイト、マルセル・モースなどの20世紀ヨーロッパの知的興奮。
映画は独特の持続的時間でセッションを表現している。その終盤にジョルジュはジミーに語る。「君の魂は傷ついている」。持続的時間の後だからこそ、この言葉はジミーを治癒する。それは亡命ユダヤ人としてのジョルジュ自身の魂の帰還でもあるのだろう。
この持続的時間のセッションは、他にない至高の映画的経験である。
 2013年作品
2013年作品
監督:アルノー・デプレシャン
出演:ベニチオ・デル・トロ/マチュー・アマルリック/ジーナ・マッキー
劇場:シアターイメージフォーラム
関連サイト:
ジミーとジョルジュ 心の欠片を探して
ネイティブアメリカンの歴史と文化人類学的関心。たった一つのセリフで語られるジミーの沖縄戦派兵の経験。ジョルジュ・ドュブルーの背景にうかがえるフロイト、マルセル・モースなどの20世紀ヨーロッパの知的興奮。
映画は独特の持続的時間でセッションを表現している。その終盤にジョルジュはジミーに語る。「君の魂は傷ついている」。持続的時間の後だからこそ、この言葉はジミーを治癒する。それは亡命ユダヤ人としてのジョルジュ自身の魂の帰還でもあるのだろう。
この持続的時間のセッションは、他にない至高の映画的経験である。
 2013年作品
2013年作品監督:アルノー・デプレシャン
出演:ベニチオ・デル・トロ/マチュー・アマルリック/ジーナ・マッキー
劇場:シアターイメージフォーラム
関連サイト:
ジミーとジョルジュ 心の欠片を探して
2015年01月11日
『百円の恋』
安藤サクラという女優が気になってしかたない。『愛のむきだし』(2009)で園子温はどこからこんなけったいな女をひっぱってきたのだとあきれ、『かぞくのくに』(2012)ではしたたかなその存在感を見せつけられ、『百円の恋』ではひたすら女優で映画を観てしまう。
なんだろう、この顔は。あのぴたりとしたそこにいることは。
 2014年作品
2014年作品
監督:武正晴
出演:安藤サクラ/新井浩文
劇場:テアトル新宿
関連サイト:
『百円の恋』
なんだろう、この顔は。あのぴたりとしたそこにいることは。
 2014年作品
2014年作品監督:武正晴
出演:安藤サクラ/新井浩文
劇場:テアトル新宿
関連サイト:
『百円の恋』
2015年01月06日
お父さん もういいのさ さようなら
今日の午前10時30分に父が亡くなったという電話をもらった。
1ヶ月前、1枚の葉書が届いた。父のいとこを名乗る女性からのもので、父が重篤で危ない様子だと告げていた。その方と連絡をとり、父の入院先へ向かった。父は人工呼吸器をはめられ意識がなく、看護婦の説明では予断を許さない状態であるという。私からの知らせを聞いた兄は、翌日リハビリ入院先の熱川から車椅子の移動で駆けつけたが、やはり意識はなかったということだった。
父のいとこからの電話では、それからの若干の事情が説明された。その後父は意識を回復し、簡単なコミュニケーションがとれるまでになった。息子が来たことを知らされ、とても喜んでいたらしい。
彼女からは、少しためらいがちに、財産処理に立ち会ってほしいといわれ、それはできないと答えた。仮葬に立ち会うことも断った。骨は父の実家の墓にということでよいかときかれ、それで構わないと応じた。それで終わった。
父はギャンブル依存症であった。私が小学生の頃、会社の多額の金を使い込み、数年後、それを助けてくれた人の金をまた使い込み、そしてさらに数年後借金をしてしまい・・・というところまできて、母は子ども3人を連れ、父の元を離れた。私が小学6年生のときのことだ。それらのトラブルごとに、一家は引越しを繰り返し、子どもたちはそのたびに転校を余儀なくされた。
以来、母は3人の子どもを女手ひとつで育て上げた。父とはそれ以来、会うことはなかった。
1ヶ月前、1枚の葉書が届いた。父のいとこを名乗る女性からのもので、父が重篤で危ない様子だと告げていた。その方と連絡をとり、父の入院先へ向かった。父は人工呼吸器をはめられ意識がなく、看護婦の説明では予断を許さない状態であるという。私からの知らせを聞いた兄は、翌日リハビリ入院先の熱川から車椅子の移動で駆けつけたが、やはり意識はなかったということだった。
父のいとこからの電話では、それからの若干の事情が説明された。その後父は意識を回復し、簡単なコミュニケーションがとれるまでになった。息子が来たことを知らされ、とても喜んでいたらしい。
彼女からは、少しためらいがちに、財産処理に立ち会ってほしいといわれ、それはできないと答えた。仮葬に立ち会うことも断った。骨は父の実家の墓にということでよいかときかれ、それで構わないと応じた。それで終わった。
父はギャンブル依存症であった。私が小学生の頃、会社の多額の金を使い込み、数年後、それを助けてくれた人の金をまた使い込み、そしてさらに数年後借金をしてしまい・・・というところまできて、母は子ども3人を連れ、父の元を離れた。私が小学6年生のときのことだ。それらのトラブルごとに、一家は引越しを繰り返し、子どもたちはそのたびに転校を余儀なくされた。
以来、母は3人の子どもを女手ひとつで育て上げた。父とはそれ以来、会うことはなかった。
2015年01月02日
『パーソナルソング』
 元日、初雪舞う中、渋谷のイメージフォーラムに『パーソナルソング』を観にいく。
元日、初雪舞う中、渋谷のイメージフォーラムに『パーソナルソング』を観にいく。介護施設でひとりぽつりと車椅子にうなだれる認知症当事者に思い入れのある歌(パーソナルソング)を聞かせると、見違えたように生気が戻った反応を示す。じゅうぶんありえることだと想像はつくが、それがあたかもアルツハイマー病を治す画期的医療であるかのように喧伝されるとすれば、眉に唾をつけたくなる。アメリカのドキュメンタリーのひとつの手法として定着しているザッピング的モンタージュ手法によって、いかにもこれみよがしになされるとなればなおさらである。
トレーラー(予告編)を見たときのそんな一抹の不安の念は、映画が始まり、94歳の黒人男性の変化を捉えたシークエンスから、とたんに解消されていく。その男性ヘンリーは、会いに来た娘の名前も思い出せず、うなだれたその視線はうつろだ。
音楽で記憶をとりもどすプロジェクトを始めたソーシャルワーカーのダン・コーエンはヘンリーにiPodのヘッドフォンをセットする。ヘンリーがかつて熱心に教会に通っていたという情報から保存していたゴスペル曲が流される。ヘンリーは大きく目を見開きながら言葉を発する。「歌ってもいいのかい?」
さらに音楽にあわせて身体でリズムをとりだすなど、ヘンリーの明らかな変化をキャッチしたコーエンは、昔の記憶を呼び起こすことをうながす質問をする。ヘンリーは、子どもの頃自転車にのってお金がもらえたことなどを語りだし、顔を上気させ、自分に起こった変化にとまどうように涙を潤ませる。映像は、ヘンリーの昔の写真や同時代の映像を挿入しながら、彼の内面を観る者に共有させる。
同様のセッションは続く。劇的な変化はヘンリーのみならず、みな、ヘッドフォンから音楽が流されると、閉ざされていた表情が代わり、目に見える興奮を隠さない。ひとりひとりにそれぞれのライフヒストリーがあり、パーソナルソングがあることの提示に、観る者はある豊かさをつかむ。Alive Inside。原題である、「内面は生きている」という豊かさの驚きを。
その中でも個人的に特にグッときてしまったのは、初期のアルツハイマーと診断された中年女性メリールーのセッションである。一見「健常」の彼女は、フォークとスプーンの違いがわからず、エレベーターの上下のサインの違いも分からない。日常生活に不安を抱え、献身的に寄り添う夫に対し罪悪感を抱いている。そんなメリールーが愛おしそうに孫に接しているところをみて、コーエンは彼女もAlive Insideであることを確信し、iPodをわたす。映画では、彼女がスタートボタンを押して流れてくるメロディーが、薄くオーヴァーダビングされ、見る者も彼女といっしょにそのメロディーを聴くという疑似体験をする。ビーチボーイズの「アイ・ゲット・アラウンド」が聞こえ、メリールーがティーンエイジャーのように歓喜の声を漏らす一瞬の時差の後、それを見て聴いている私も感情の高ぶりを抑えきれなくなる。メリールーと同じ初期のアルツハイマー病を持つ自分の母のことを重ね合わせて見てしまったのはいうまでもない。
トレーラーは、アメリカそして日本で認知症人口が増加し大きな社会問題となっていること、アルツハイマー病には完全な治療法がまだないことが警鐘として鳴らされるところから始まる。さらに続く「1000ドルの薬より、1曲の音楽を!」というコピーは、本編においても医療問題の矛盾として丁寧に紹介される(「薬では患者の心は治療できないんだ」)。この魅力的なプロジェクトを医療手段として認めてもらおうとするが、なかなか受け入れてもらえないコーエンの奮闘ぶりも描かれている。
しかしながら、この奇跡的なドキュメンタリーが現していることは、「治さなくてよい認知症」が音楽を通して「治る」という「結果」ではないだろう。Alive Inside、つまり、内面が生きているのであれば、治るも治らないもないはずだ。そのことを当事者以外のわたしやあなたに認識させてくれる音楽のもつ力に驚こうではないか。
「彼らには世界との関わりが必要なんだ」。施設に何年もいるにもかかわらず、外に出たいとあらゆるドアを開こうとする男性の姿は、日本の施設でも決して珍しくない痛ましい光景だろう。管理された施設の孤独の世界で、その孤独の薄闇を突き抜けるように、ヘッドフォンという閉ざされた世界から伝わるパーソナルソングという矛盾。その矛盾を開くのは、外の世界との関わりを開くのは、共に音楽を聴いているあなたやわたしだ。
『パーソナルソング』は沖縄では桜坂劇場で上映予定があるようだ。その機会には多くの人に観ていただきたい。
2014年作品
監督:マイケル・ロサト=ベネット
出演:ダン・コーエン、オリバー・サックス、ボビー・マクファーレン
劇場:イメージフォーラム
関連サイト:
パーソナルソング
関連記事:
書評『治さなくてよい認知症』
書評『ブログ 認知症一期一会 認知症本人からの発信』
『毎日がアルツハイマー2』