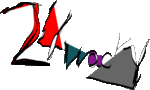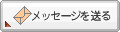2018年10月23日
『自由という牢獄 責任・公共性・資本主義』大澤真幸

社会が多様な人々に対して開放的であろうとすると、自由への制限は大きくなる、言い方を変えれば自由と開放(平等)は矛盾するとされる一般的な考え方を再考する「第3章 〈公共性〉の条件──自由と開放をいかに両立させるのか」を、私は沖縄の政治的状況と関連させて読む。カント、マルクス、アーレント、ハーバーマス、ジジェク、スピヴァク、アガンベン、ロールズ、サド、網野善彦らによる思想を参照しながら本書は2000年前後に書かれたが、それらは〈いま・ここ〉の沖縄に私という媒介を通し突き刺さる。
9・11テロ直後、アメリカ国内に炭疽菌がばら撒かれた。当初それはアル・カイダによるテロではないかとされたが、炭疽菌は国内からばら撒かれた。つまり、「敵」は遠い中東にではなく近くの身内にいるという恐怖がそこに加わった。それは地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教信者たちが隣のアパートの住人かもしれないというそれと似ている。「われわれ(アメリカ)/タリバン」「われわれ/オウム」という対立は、実は「われわれ」自身に内在している。「敵」との葛藤は、われわれ自身の内的な分裂、内的な矛盾にほかならない。このような「敵」をも範囲に納めた普遍的な公共性を構築することはいかにして可能か。
スピヴァクは、自らについて語ることが排除され、語ることが不可能な従属的な地位に立たされている人々を「サバルタン」と呼んだ。テロが起きるまで「われわれ」から見捨てられてきたアフガニスタンの人々もまたサバルタンといえる。普遍的な公共性を構築するとは、このような排除をいかに克服するかという問題でもある。
アーレントは公共性について「現れ」という言葉を使っている。公共的であるということは、そこに参加する者たちが、他者たちに対して現れているということである。人が他者に対して「何what」としてではなく「誰who」として現象している状態をいう。著者はこのことを、「他者が私に対して応答してくれる状態」と言い換える。それがサバルタンでないということである。
アーレントが理想的な公共性として眼差した古代ギリシャの社会は、オイコス(家共同体)/ポリス(都市国家共同体)という二層構造をなしている。アーレントはこれを私的/公的と定義した。一方、アガンベンは、単に動物的に生きている「剥き出しの生」/善き生と区分けした。アガンベンは、この二層構造が単に分離されているのではなく、ポリスの公共性が剥き出しの生をオイコスの方へと排除することで成立すること、公共性は剥き出しの生に依存しているという解釈を加えた。
ところで、アガンベンは、人民peopleという西欧語には、解消しがたい両義性があると指摘している。peopleは、一方では、政治的主体、市民の集合の全体を表しているが、他方では、恵まれない者、貧民、惨めな庶民といった、政治から排除された階級をも表している。アーレントは、人民主権が声高に宣言されたフランス革命において、ロベスピエールが「人民、この不幸な者たちが我を称える」といったことに注意を促している。つまり、人民という概念は、内的な敵対性を孕んでいる。
サドはフランス革命の人権宣言に対し、快楽を享受する権利、身体を用いて快楽を無限に享受する権利を加えることを要求した。身体的な快楽を享受するとは、最も私的な要素に思えるが、サドにおいては逆転され、「閨房」という私的な空間こそが公共的空間となる。
ハーバーマスは、社会福祉的法治国家の登場によって、国家権力が私的領域に介入し、市民的公共性が解体されていったことを批判した。アーレントは、「社会(経済)」の浸透によって公共的空間が解体されたという解釈をした。両者ともに経済や生命への関心に公共性の困難を見出したという点で一致している。それに比べて、サドは、むしろその身体こそが公共性を完成させる要素であるとした。完全な公共性への不可欠な要素としてふさわしいのは、果たしてどちらか。一般的には前者が正しいように思われるが、著者は後者を選ぶ。「つまり、公共性は、私的な快楽への──ときに生理的な身体に直接訴えかけるような私的な快楽への──執着に規定されて、構成されているのではないか」と。
アガンベンは、主権の源泉を「ホモ・サケル(聖なる人間)」に見出した。ホモ・サケルとは、古代ローマ法の中で見出されるカテゴリーである。その条件は、第一に、その人物を殺しても罰せられないこと、第二に、その人物を供儀に用いることができないことである。
1995年に沖縄で起きた米兵による少女暴行事件では、沖縄中の怒りが大規模な運動に発展し、日米地位協定の見直しを訴える県民総決起大会には8万5千人を結集させた。著者はこの動きを「ほとんど「革命」とも見なし得る」と表現する。しかしながら、1998年の県知事選では、保守陣営から立候補した基地容認のスタンスをとる稲嶺恵一が基地反対の現職候補の大田昌秀に勝利した。著者はこの意外性に注目する。選挙は、それぞれの利害関心を支える価値観の間の闘争である。基地にまつわる利害や「平和」「経済」といった価値観にもとづいて政治的空間を構成した場合、普遍的な参加を可能にする公共性は描きえないとしたうえで、こう述べる。
だが、九五年の運動は、こうした利害や価値観の闘争とは異なったものだったのだ。九五年の運動が異様な喚起力をもったのは、すべての沖縄県民が、米軍が駐留していることに由来する、それぞれに多様な困難を、少女の暴行の悲劇に投影することができたからである。少女への暴行は、沖縄の困難を集約的に表現するマスターキーとなったのである。このことの帰結が、日米地位協定の見直しへの要求である。すなわち、暴行が多様な苦難の集約点であったがために、個人的な補償を超える、日米関係の総体の再定義を迫るような、普遍的要求を結実しえたのだ。
すべての人が、少女暴行事件に基地による被害を投影しえたのは、それが、多様な被害や苦難のすべての隠喩になっているからである。だが、このことは、少女暴行事件の悲劇の中に、基地の存在に発する人々の多様な苦労を通約する共通の何かがあった、ということではない。そもそも、女性への暴行は、長い間、基地の被害として、承認されてすら来なかったのだ。公認された基地問題とは、土地を奪われた住民の私的所有権の侵害であり、また騒音等の公害や環境問題であった。公害の苦しみと暴行の悲劇の間に、共通の何かがあると考えてはならない。このことは、前者の被害を前面に出した闘争は──つまり九八年の県知事選では──、反基地のスローガンは普遍的な動員力を持たなかった、という事実からも明らかであろう。
それならば、暴行事件が公共化の作用をもちえたのは、なぜなのか。それは──逆説的なことだが──、暴行(レイプ)が、決して公共的に表現されえない、個人の内的な核に対する冒瀆だったからではないか。暴行は、公共的な表現を徹底的に拒む、排除された一点である。排除された特異点だけが、多様な利害や価値観の上に分解している人々が、自らを無際限に同一化しうる普遍的な集約点となりえたのである。共通の利害や価値観によって集合しようとすれば、政治空間は、互いに通約しえぬほどに対立する多数の党派に分解し、弛緩するしかない。沖縄の事例は、誰も、積極的には「共通の何か」を見出しえないような排除された一点だけが、逆に、普遍性を機能させるポイントたりうる、ということを暗示しているのだ。
264〜265ページ
ここでの論点を再度抽象化させると次のようになる。人が行為しているとき、その行為の選択性は他者に帰属している。〈私〉が行為しているとき、〈私〉に内在する他者が、その行為を選択し、決定している。〈私〉はその他者の選択に、直接に同一化していることによってこそ、その行為をなしうる。ときに、その内なる他者は、否認され、隠蔽されている。そのような他者は締め出されることにおいて、行為は、能動的なものとして現実化する。
著者の発想の転換はここにある。われわれは普遍的な開放性を有する公共空間を求めてきた。メンバーたちが積極的に共有している価値観──たとえば善や正義、あるいは「イデオロギーよりアイデンティティ」──や、共通の利害関心──たとえば「安保法制反対」「辺野古新基地建設反対」──によって、連帯しうる者の間のみに、公共的な空間が可能だと。だが、残念ながら、そんな要素はないということがわかった。
だが、ここで着想を変えてみるのだ。行為の可能性についての考察は、われわれに、ある副産物をもたらしてくれた。行為の自由な主体として──行為に対する潜在的な可能性を有するものとして──人はみな、言ってみれば、他者に貫かれているのである。行為の主体である限りは、誰もが、他者を内在させており、その他者の呼びかけに応ずるようにして振る舞っている。要するに、行為において、誰もが、「自己」であると同時に、「他者」に変容しているのである。アイデンティティを構成する積極的な内容に、つまり「自己」が何者であるかを規定する要素に助けを求める限り、普遍的な公共性は、絶対に不可能だ。だが、行為において、人は、自己自身として一貫性を保ちえてはいない。〈私〉は、〈私〉に留まってはいない。〈私〉は、己ならざる者へと自己を開き、その己ならざる者そのものになってさえいるのだ。そうであるとすれば、われわれは、万人を貫く内的な他者性においてこそ、〈普遍的に〉連帯することができるのではないか。共有している何かによっては、もはや、普遍的公共空間は構築しえない。誰もが、自己同一性の内に安住しえないという否定的な要素だけが、〈普遍的公共性〉への道を開くのである。
287〜288ページ
さらにつけ加えるとすれば、〈私〉の一見能動的な行為を、受動的なものとして再規定する他者もまた、能動的ではないということである。他者もまた徹底的に受動的である。それゆえに超越的な他者もまた、他者性に貫かれている。それは、たとえば触覚の領域にうかがえる直接に身体的な体験、あるいは身体の受動性を受容しあう愛の関係のような体験を思い浮かべればよい。ここで、快楽を享受する私的な空間こそ公共的であるとするサドの宣言につながる。
雑感
「自己同一性の内に安住しえないという否定的な要素だけが、〈普遍的公共性〉への道を開く」。それは柄谷行人がカントに見出した「自然の狡知」を思い起こさせる。カントによれば、人間の「反社会的社会性」は「自然」であり、それを取り除くことはできない。「国際連盟」はこれを前提として構想された。カントは、人間の理性や道徳性によるよりも、 「反社会的社会性」という本性(自然)が引き起こす戦争が国家連合を実現すると考えた。
「 行為において、人は、自己自身として一貫性を保ちえてはいない。〈私〉は、〈私〉に留まってはいない。〈私〉は、己ならざる者へと自己を開き、その己ならざる者そのものになってさえいるのだ」。これはドゥルーズ=ガタリの「生成変化」に似ている。《男性が女性に「なる」ためには、女性が女性に「なる」ことが不可欠である。マジョリティがマイノリティに「なる」ためにはマイノリティがマイノリティに「なる」ことが必須であるように》という、あの「なる」に。
1998年のみならず、2014年そして記憶に新しい2018年の沖縄県知事選が、「共通の利害や価値観によって集合しようとす」る両陣営による選挙であったことは言うまでもない。さらに後者2つは、「アイデンティティを構成する積極的な内容に、つまり「自己」が何者であるかを規定する要素に助けを求める」スローガンを掲げた候補者が勝利した。それは圧倒的な勝利であったかもしれないが、普遍的な公共性は、そこにない。
『自由という牢獄 責任・公共性・資本主義』
著者:大澤真幸
発行:岩波現代文庫
発行年月:2018年9月14日
2017/03/20
なにやらビジネスパーソン向けの手っ取り早い指南書の装いであるが、正真正銘大澤真幸社会学の一冊である。考えるとはどういうことか、大澤自身の手の内を丁寧かつ具体的に明かすという親切心にあふれている。それだけ「考える」ことの復権という使命を著者も編集者も持たざるを得ないということか。何はともあれ、…
2016/12/05
2015年にノーベル文学賞を受賞したスベトラーナ・アレクシエービッチは先日の来日講演の中で、福島第一原発事故の被災地を訪ねたことに触れ、「日本社会には抵抗の文化がないのはなぜか」と問うた(「日本には抵抗の文化がない」 福島訪問したノーベル賞作家が指摘 THE HUFFINGTON POST 2016年11月29日付)。本書…
2016/10/30
フランス革命のスローガンは「自由、平等、友愛」である。各人の自由が、すべての他者たちの自由の条件になっている。ということは、自由と普遍的で無際限の連帯(友愛)とが、同時に、相互に条件づけあうように実現している、ということである。そこに平等はなくてもよい。そのときすでに、不平等も解消されている…
2016/10/29
ハーマン・メルヴィルの中編小説『バートルビー━━ウォール街の物語』(1853年)は、資本主義の中心地となる19世紀のウォール街において、語り手の弁護士によって記述される、書記バートルビーの奇妙な生態についての物語である。弁護士が口述や筆記の仕事を頼むと、バートルビーは「私はそれをしないほうがいいと思…
2016/10/28
2015年に国会議事堂の周囲で起こされた安保関連法案に反対するデモは、敗戦後70年間で最大のレベルだった。その中心となったSEALDsという学生たちの団体は、本書で論じてきた社会や政治への指向をもつ若者像を裏付ける。しかしその間安倍内閣の支持率はほとんど下がらず、デモは敗北だったといわざるをえない。 同…
2016/10/27
『あまちゃん』の「夏(祖母)━━春子(母)━━アキ」という三代の女は、ちょうど日本の戦後史の3つのフェーズ「理想の時代/虚構の時代/不可能性の時代」に対応している。各世代は前の世代から活力や決断のための勇気を与えられる。 かつての東京での生活ではまったくやる気のなかったアキが初めて見出した生…
2016/10/26
戦後史の時代区分「理想の時代→虚構の時代→不可能性の時代」からいえば、かつて東京や大都市は「理想」が実現する場所だった。しかし、その求心力は不可能性の時代に入ると急速に衰えていった。それと同時に地元志向の若者たちが増えていく。地方の若者たちに「地元と聞いて思い出すものは?」と質問すると、返って…
2016/10/25
不可能性の時代において、「可能性の過剰」という側面に対応しているのが、鈴木健の『なめらかな社会とその敵』であり、「不可能性の過剰」という側面に対抗しようとしているのが、千葉雅也の『動きすぎてはいけない』である。前者は沈みゆくタイタニック号に乗り続け、後者はタイタニック号と運命をともにすること…
2016/10/24
「未来→過去」というように因果関係が遡行していることは不思議であるが、われわれは日常的に目撃したり、体験したりしている。 たとえば、幾何学の証明で用いられる「補助線」の働きがそうである。証明者が、「ここに補助線があればうまくいきそうだ」という直観を得るとき、それはあたかも未来からの情報に影…
2016/10/23
マンガ『テルマエ・ロマエ』は、古代ローマの建築家ルシウスが現代日本にワープし、浴場についてのアイデアを得るという内容である。ここには〈未来の他者〉といかにして連帯するかという主題に関わる手がかりがある。 『テルマエ』では、古代ローマの浴場が現代日本の浴場からのパクリであった。このように、…
2016/10/22
極端に危険な可能性を無視し、排除したことによって、楽観的なシナリオを過度に信ずるほかなくなる、ということがある。たとえば、10億円を動かす投資家がいたとする。彼は市場そのものが破綻する確率が90%あると直感的に理解している。とすれば、彼は10億円のうち1億円だけ投資するかというとそうではなく、なんと…
2016/10/21
フランシスコ会の修道士でポーランド人のコルベは反ユダヤ主義の思想をもっていた。第二次大戦時、ナチスがポーランドを侵攻し、ナチスに追われた人々の援助活動をしていた彼は、ゲシュタポに逮捕され、アウシュビッツ強制収容所に送られた。そこで餓死の刑が下されると、コルベはユダヤ人の身代わりとなり餓死室に…
2016/10/20
3・11以降、脱原発運動の大規模なデモが発生した。しかしその間国会では、原発の問題が中心的課題として議論されたとはいえない。デモによって表現される国民的関心と国会議員の行動の間に整合性がない。国会議員は国民の意志を無視すれば次回の選挙で自分が落選するかもしれないという切迫した恐れをもたなかった。…
2016/10/19
社会や政治への関心が薄く親密な仲間との関係に閉じこもる若者という通念と、次の社会調査の結果は重なる。衆議院選挙の年齢別の投票率によると、二十代の投票率は1960年代から1980年代にかけては60%前後を上下しているが、2000年を挟む3回の選挙では30%台に激減している。このような極端な減少は他の年齢層ではみ…
2016/10/18
著者は日本人の「生活全体についての満足感」という社会調査のデータから、1973年と2008年を比較し、1973年では若い世代(とりわけ男性)の幸福度が低いのに対し、2008年のグラフでは高いのが顕著であることの不可解さに注目する。なぜなら、この世代こそ、バブル崩壊後の不況の影響を直接受けた「ロストジェネレー…
2016/10/16
どのような社会にも、論理的にはもちろん可能だし、法的にも必ずしも禁じられてはいないのだが、「それ」を選択すること、「それ」をなすことは、事実上は、不可能だとされていることがある。「それ」を選択しないことを暗黙の前提とした上で、われわれには、「それ」と「あれ」の選択の自由が与えられており、われ…
2017/03/08
本書は思想家の「入門もの」であるが、ハンナ・アーレントがドイツを離れて亡命するきっかけに切り口をしぼっている。アーレントが亡命したのはナチスの迫害を逃れるためであったことはいうまでもないが、「出来事」としてより注目すべき点がある。それは、それまで信頼していた友人たちがナチスのイデオロギーに幻…
2016/11/18
2012年10月、普天間基地への米軍機オスプレイ強行配備と阻止行動の敗北は、私自身にとって画期的な出来事としてある。沖縄オルタナティブメディア(OAM)として一連の顛末を現場中継し、目撃し、阻止行動に加わった。阻止行動は排除され、翌日オスプレイは空高く飛来し、沖縄の地に着地した。その時、私は自分…
Posted by 24wacky at 22:13│Comments(0)
│今日は一日本を読んで暮らした